日本のスゴ技!トンネル工事の裏側に潜入
今回のテーマは「トンネル」。日本は山が多い国で、全体の7割以上が山地。だからトンネルがとても重要で、全国のトンネルの長さを合計すると約9000kmにもなります。番組では、そんな日本のトンネル技術がどれほどすごいのか、どれだけお金や手間がかかっているのかを紹介しました。海外でも使われている技術や、驚きの重機も登場し、見ごたえのある内容でした。
トンネル大国・日本の秘密に迫る
日本は、国土のおよそ7割以上が山地という、とても起伏の多い地形を持っています。そのため、都市や地域をスムーズにつなぐためには、道路や鉄道を山の中に通す「トンネル」がとても大切な役割を果たしています。実際に、日本国内にあるトンネルの総延長は約9000kmにものぼり、これは日本列島の長さ(約3300km)よりもはるかに長いことになります。番組では、こうした背景から発展してきた日本のトンネル建設技術の最前線を取り上げ、さまざまな事例とともに、その裏側にある知恵や努力をわかりやすく紹介しました。
海外でも評価される日本の技術力
現在の日本のトンネル技術は、長年にわたる経験と改良を重ねてきた結果、高い安全性と精度を誇ります。特に、硬い岩盤を正確に掘り進める重機の進化や、土砂崩れを防ぐ補強工法などが注目されています。これらの技術は日本国内にとどまらず、たとえばイギリスとフランスを結ぶ**英仏海峡トンネル(ドーバー海峡トンネル)**のような海外の大型プロジェクトにも導入されるなど、**世界で活躍する“日本のインフラ力”**として知られています。
地図に残る仕事の背後には莫大なお金と時間
番組では、日本のトンネル工事にかかる費用や期間のリアルにも注目。単なる穴を掘る作業ではなく、地下水・地質の調査、巨大な掘削機の導入、工事中の安全確保など、あらゆる工程で莫大なコストと労力がかかることが紹介されました。完成してしまえば通り過ぎてしまう存在かもしれませんが、その裏側には何年にも及ぶ努力と緻密な技術が積み重ねられているのです。
番組を通じて見えた「日本の足もと」のすごさ
一見すると地味に思われがちなトンネルですが、実は日本の物流や生活、交通を支える要の存在です。今回の放送では、その地味な存在の中にある驚くべき技術と情熱が、親しみやすく伝えられていました。見終わった後には、きっと誰もが「トンネルを見る目が変わった」と感じるような、そんな番組内容でした。
山をくり抜く山岳トンネルと重機の工夫
日本では、トンネルの多くが「山岳トンネル」と呼ばれるもので、山を直接くり抜いて通すタイプが主流です。これは山地が多い日本の地形に合った方法で、道路や鉄道をつなぐために欠かせない技術です。番組では、そんな山岳トンネルをどのように掘っているのか、その裏側の工夫が紹介されました。
岩盤を掘り進めるトンネルボーリングマシーンの力
まず登場したのは、トンネルボーリングマシーン(TBM)。この巨大な機械は、硬い岩盤をぐいぐいと掘り進めながら、トンネルの形に整える役割を果たします。トンネルの直径に合わせたサイズで設計され、刃のようなカッターで回転しながら地中を掘り進みます。作業員の安全を確保しながらも、効率よく大量の岩盤を掘削できる点が大きな特徴です。
爆薬を仕込む穴も正確に掘るドリルジャンボ
次に紹介されたのはドリルジャンボ。この機械は、爆薬を仕込むための穴を、計画された位置と角度で正確に開けることができます。複数のアームが自在に動くため、人の手では難しい場所でも正確な穴あけが可能。その後の発破作業を安全かつ効果的に行うための土台となる大切な工程です。
壁を補強する2ブームロックボルト自動施工機
さらに注目されたのが2ブームロックボルト自動施工機という重機です。これは、掘削後のトンネルの壁に鉄の棒(ロックボルト)を打ち込み、壁を崩れにくくする作業を自動で行うもの。掘削時に感じる抵抗や圧力を機械が自動で測定し、最適な力で施工できるという、まさに賢い機械です。この自動化によって、作業の精度と安全性が高まり、時間の短縮にもつながっています。
最先端の重機が支えるトンネル建設の現場
これらの重機の導入によって、これまで何年もかかっていた工事が大幅に短縮されるだけでなく、安全性も格段に向上しました。危険な作業を人が直接行わずにすむため、事故のリスクも減り、より多くの現場で活躍しています。日本の山岳トンネルは、こうした最新の機械の力によって、難しい地形でもしっかりと道を通すことができているのです。
難工事として語り継がれる飛騨トンネルの挑戦
岐阜県・富山県・愛知県をつなぐ東海北陸自動車道の一部として建設された飛騨トンネルは、日本のトンネル建設史に残る極めて困難なプロジェクトでした。全長は約11kmにもおよび、2008年の開通まで実に12年もの歳月をかけて完成したこのトンネルは、まさに“山を貫く”という言葉そのものの大工事でした。
掘削の進行を止めたやわらかい地盤の難しさ
当時、最新鋭のトンネルボーリングマシーンが導入されましたが、工事が順調に進んだわけではありません。やわらかい地層にぶつかったことで、掘削した土砂が崩れてマシーンが詰まるというトラブルが発生。そこで、セメントなどで周囲の地盤を固めながら少しずつ掘り進めるという手法が繰り返されました。しかも1kmごとに地層の性質が変わるため、先に小型のトンネルボーリングマシーンで試し掘りをして地質を調べるという慎重な工程が必要でした。
残り300mで起きた大量の土砂噴出
さらに工事開始から約9年が経ったある日、残り300mというところで突如大量の土砂が土石流のようにトンネル内に噴き出すという緊急事態が発生しました。小型の掘削機はその勢いに押されて破損。そこで方針を転換し、反対側からダイナマイトによる発破での掘削に切り替えました。この切り替えは、現場の判断力と柔軟な対応の成果でもありました。
完成までの12年、費用1000億円、そして無事故の記録
最終的に、着工から9年6か月でトンネルが貫通し、その後2年をかけて内部の仕上げや設備工事が行われました。総事業費は約1000億円にものぼる一方で、死亡事故ゼロという快挙を達成。この事実は、技術だけでなく、安全への強い意識と現場の努力の賜物といえます。困難を乗り越えて完成した飛騨トンネルは、日本のトンネル建設技術の集大成ともいえる存在として今も語り継がれています。
全国にあるユニークなトンネルたち
番組では、日本各地に存在するちょっと変わった見た目や構造のトンネルも紹介されました。普段は通り過ぎてしまいそうな場所にも、地域性や工事の背景が色濃く残っていて、注目して見ると意外な面白さがあります。
獅子舞の顔が目印の寄国土トンネル(埼玉県秩父市)
まず紹介されたのは、埼玉県秩父市にある寄国土(よりくにど)トンネル。このトンネルの入り口は、まるで獅子舞の顔のようなデザインになっていて、車で走っているとその外観が突然目に飛び込んできます。中に入ると普通のトンネルなのですが、そのインパクトのある見た目から観光客の間でもちょっとした話題になっています。地域の伝統行事である獅子舞をモチーフにしており、秩父らしさを表現したユニークなトンネルです。
工事の都合で生まれた“狭すぎる”トンネルたち
番組ではもうひとつ、途中で幅が極端に狭くなるトンネルも取り上げられました。これはもともと地質調査や先行掘削用として作られた細いトンネルを、のちに広げて本格的な道路にする予定だったものの、国道建設の計画変更で工事が止まってしまったケースです。そのため、「所見のドライバーは思わず止まってしまう」と言われるほどのギリギリサイズの通路になっていて、通るのに少し勇気がいるような雰囲気を醸し出しています。
日本各地に残るクセ強トンネルの存在
こうしたユニークなトンネルは、愛媛県の大峠隧道や岩谷隧道、静岡県掛川市周辺などにも点在しています。地元の人たちにはなじみ深くても、外から訪れた人には驚きを与えるようなトンネルが多く、まさに“知る人ぞ知る”存在です。景色や構造、歴史的背景などが融合したこれらのトンネルは、日本の地域文化の一部として見ることもでき、ドライブや旅の中で注目する価値のあるスポットです。
世界初!通行を止めずに岩を撤去する大工事
番組で紹介されたのは、群馬県と長野県の県境に位置する上信越自動車道・北野牧トンネルで進められている非常に珍しい工事でした。このトンネルの真上には、長年の風雨や地形変化で不安定になった巨大な岩盤があり、将来的に落石の危険がある場所として注目されていました。しかし、この自動車道は地域の物流や観光を支える重要な道路。長期間通行止めにすることはできません。
高速道路の上に巨大な足場を組む前代未聞の挑戦
そこで取られた手段が、なんと道路の上に巨大な足場を組んで岩を撤去するというもの。これは、通行を維持しながら岩を安全に取り除くという世界初の工法です。上下で異なる作業環境を両立させるという難しさがあり、足場の設置だけで約16億円という巨額の費用がかかりました。それでもこの方法が選ばれたのは、地域住民や経済活動への影響を最小限にとどめるためです。
巨岩を削るための工法にも工夫が満載
工事では、かたい岩に直径3mほどの穴を開け、そこに亀裂を入れることで岩盤を少しずつ崩すという手法が採用されています。発破などの大がかりな方法は使えないため、細かく岩を削りながら慎重に進めることが求められました。この繊細な作業には高い技術と経験が必要で、日本の土木チームの力量が試される場面でもあります。
道路の安全と経済を両立させるトンネル上の挑戦
この工事は、日本の交通インフラを守るうえでの新しい試みとして、国内外の専門家からも注目を集めています。「通行を止めずに危険を取り除く」という発想は、今後のインフラ保全のヒントにもなりそうです。普段何気なく走っている高速道路の上でも、見えないところでこれほどの工夫と努力が積み重なっているのだと気づかされるエピソードでした。
地下鉄のバイト経験と芸能人の苦労
番組では、トンネル工事の大変さを実感できるエピソードとして、出演者の鈴木浩介さんが語った地下鉄トンネル内装工事のバイト経験が紹介されました。若い頃に実際に現場で働いたことがあるという鈴木さんは、作業環境の厳しさや重い資材を扱う大変さ、限られた空間での作業の難しさなど、リアルな現場の様子を体験していたことを明かしていました。空調や照明が十分ではない地下空間で、何時間も作業を続ける大変さは、テレビの画面越しでは伝わりにくい現場の一面です。
また、藤本美貴さんも自身の芸能活動の経験から「立ち位置やダンスを覚えるのが大変だった」と語り、一見まったく違う分野であっても、細かい動きや正確さが求められる点で通じる部分があると共感を寄せていました。自分の位置を間違えないように、チームで息を合わせて動くことの大切さ。それは、トンネル工事でも、舞台やライブでも共通して必要な要素です。
こうした出演者の体験談を通して、トンネル建設にかかわる人たちが日々どれほど精密で責任ある作業を行っているかが、より身近に伝わってきました。トンネルがただの「道」ではなく、人の努力やチームワークの積み重ねで作られていることを改めて感じさせてくれる場面でした。
おわりに
今回の放送では、日本のトンネルがただの道ではなく、多くの努力と工夫、安全対策によって支えられていることがよく伝わってきました。重機や工法の進化、現場の人たちの知恵が、日本を支えるインフラを作っているということを改めて実感できる内容でした。地味に思われがちなトンネルにも、こんなにたくさんのドラマや技術が詰まっていると知ると、道路を走る時の見方も変わりそうです。
飛騨トンネル周辺を訪れるなら外せない観光スポット

ここからは、私からの提案です。飛騨トンネルを目的に訪れたら、周辺にはそのまま立ち寄れる魅力的な観光地がたくさんあります。トンネルという土木の世界を感じたあとは、歴史、自然、温泉といった飛騨ならではの豊かな文化や風景も一緒に楽しめます。
飛騨高山の古い町並と歴史エリア
高山市内には江戸時代からの情緒あふれる町並みが今も残っており、歩くだけでまるで時代をさかのぼったような気分になります。格子戸の町屋や、石畳の小路、用水路に流れる清水など、どこを見ても絵になります。特に「高山陣屋」は江戸時代の役所をそのまま残した貴重な建物で、内部の見学も可能です。また、「飛騨の里」では合掌造りの古民家が再現され、飛騨地方の暮らしや文化を学ぶことができます。宮川沿いの朝市や地酒を楽しめる酒蔵巡りも人気のアクティビティです。
世界遺産・白川郷の合掌造り集落
飛騨と並んで人気なのが白川郷・荻町合掌造り集落。三角屋根の茅葺き民家が連なる景観は、まさに日本の原風景です。和田家や旧遠山家などは内部を見学でき、昔の生活を知ることができます。集落の中心を流れる庄川にかかる「であい橋」を渡ると、風情あふれる町並みに包まれます。さらに、集落全体を一望できる「荻町城跡展望台」からの眺めは絶景。季節ごとの美しさ(春の新緑、夏の青空、秋の紅葉、冬の雪化粧)も楽しめます。
白山白川郷ホワイトロードで大自然ドライブ
ドライブ好きなら外せないのが「白山白川郷ホワイトロード」です。白山国立公園内を走る全長33kmの山岳道路で、標高の高い場所を通るため視界が一気に開ける絶景が続きます。途中には滝や展望台もあり、紅葉の時期(9〜10月)や夏の新緑が特におすすめ。ただし、冬季は通行止めになるので注意が必要です。
大白川露天風呂で山と湖に癒される
白川郷から車で30分ほどの場所にある大白川露天風呂(平瀬温泉)は、自然の中にぽつんとある秘湯です。白水湖のすぐそばにあり、硫黄の香り漂う乳白色のお湯に浸かりながら山々と湖を一望できます。アクセスは少し険しい山道を進みますが、到着すればそこはまさに非日常。夏は新緑、秋は紅葉、晴れた日は星空も堪能できます。
観光スポットまとめ表
| 目的 | 見どころや内容例 |
|---|---|
| 歴史・文化を感じる | 飛騨高山の古い町並、高山陣屋、飛騨の里、酒蔵巡り |
| 世界遺産体験 | 白川郷の合掌造り集落、和田家、遠山家、であい橋、展望台など |
| 絶景ドライブ | 白山白川郷ホワイトロード、滝スポット、高原ビュー |
| 温泉で癒し | 大白川露天風呂(平瀬温泉)、白水湖と山々の景色に包まれて入浴体験 |
飛騨トンネルのスケールや技術に驚いたあと、地域の自然や暮らしにふれることで、「人と自然が共にある風景」や「技術と文化のつながり」をじっくり体感できます。旅のテーマを少し広げて、飛騨エリアの奥深さを味わう旅にしてみてはいかがでしょうか。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

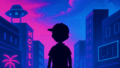

コメント