日本の“発酵食品”が世界でブーム その陰で広がる危機とは
最近、世界の有名レストランや食通の間で話題になっているのが「日本の発酵食品」。しょうゆやみそ、納豆といった昔ながらの日本食材が、海外の一流シェフたちに“魔法の調味料”として再評価されているのです。例えばニューヨークでは、しょうゆ情報センター主催のイベントにシェフが殺到。彼らが注目するのは、発酵によって食材の旨みを最大限に引き出す「微生物の力」。
さらに、健康志向の高まりも後押ししています。腸内環境を整える発酵食品の効果が科学的にも注目され、「発酵=ウェルビーイング(心身の健康)」という新しい価値観が広まりつつあります。海外ではみそスープが“発酵スープ”として再解釈され、納豆を使ったビーガン料理まで登場。バージニア州では日本の発酵技術を学ぶシェフ向けスクールも立ち上がるなど、まさに“第二の日本食ブーム”が到来しています。
ところが皮肉なことに、このブームの発信地である日本では、発酵文化の存続が危機的状況に陥っています。原料の高騰、後継者不足、そして地球温暖化による農産物の変化。番組は、そんな“ブームの陰で進行する危機”に焦点を当てていました。
伝統の味が途絶える!?沖縄の味噌蔵に起きた異変

取材班が訪れたのは沖縄県那覇市。戦前から続く老舗の味噌蔵では、近年の物価高が直撃していました。原料の大豆や米麹の価格が高騰し、経営は限界に。そこに追い打ちをかけたのが“令和の米騒動”。全国的に加工用米が入手できなくなり、一時は味噌の製造を中止せざるを得なかったといいます。
蔵元の女性は、「百年以上続いた味噌造りの灯が消えるかもしれない。まさかこんな形で途絶えるとは」と語りました。味噌は地域の気候風土と共に育まれてきた“生きた文化”。一度生産が止まれば、微生物の系譜が失われ、同じ味は二度と再現できません。発酵は人と自然の共同作業であることを、改めて痛感させられるエピソードでした。
消えゆく郷土の味 ― ハタハタずしと天日干し大根

スタジオに登場したのは、発酵デザイナーの小倉ヒラクさんと、微生物学の専門家内野昌孝さん。小倉さんは「いま特に危険なのは、秋田県のハタハタずしと宮崎県の天日干し大根」だと指摘しました。
ハタハタずしは秋田を代表する冬の発酵食。塩漬けしたハタハタに米麹と野菜を重ね、乳酸発酵させることで生まれる酸味とうま味が特徴です。しかし近年、ハタハタの漁獲量が激減。温暖化による海水温上昇の影響で、魚が深海に移動してしまい、伝統の味が消えかけています。
一方、宮崎の天日干し大根も深刻です。江戸時代から続く伝統製法では、やぐらを組み、大根を冬の日差しで干し上げます。しかし農家の高齢化が進み、やぐらを組める人が減少。後継者のいない地域では、毎年の干し場が空き地になっている現状もあるといいます。自然に寄り添う発酵文化は、人の手があってこそ守られる。その「人の技術の継承」が最大の課題となっているのです。
対馬の『せんだんご』に見る、命をつなぐ発酵の知恵
番組後半では、長崎県対馬市の郷土食『せんだんご』が紹介されました。さつまいもを4か月かけて発酵させて作る保存食で、厳しい自然環境を生き抜くための知恵が詰まっています。かつてはどの家庭でも作られていましたが、今では作り手が高齢化し、生産量は激減。現在は一部の家庭と地域グループだけが細々と伝統を守っています。
しかし、ここでも希望の光がありました。東京農業大学と対馬市が連携し、発酵を早める微生物の働きを研究。これまで4か月かかっていた熟成期間を、わずか2週間で再現できる新製法を開発したのです。番組で登場した内野昌孝教授は「伝統の味を守るには、科学と文化の協働が必要です」と語りました。古き良き知恵に、現代の科学が寄り添う。その姿勢こそが、次世代への継承の鍵となるのです。
小豆島の木桶プロジェクトが示す再生の道
さらに番組では、香川県小豆島の老舗しょうゆ蔵にも密着。江戸時代末期から続く蔵で、5代目の山本さんが直面したのは“木桶の消滅危機”でした。しょうゆの香りや味を育てる木桶は、長年の使用で自然に呼吸するように発酵を助ける重要な存在です。しかし、プラスチックタンクの普及で需要が激減し、職人もほぼ絶滅状態に。
「このままでは木桶文化が途絶える」と危機感を抱いた山本さんは、自ら桶作りを学び始めました。さらに全国の蔵元に声をかけ、共に木桶を復活させる運動を開始。こうして誕生したのがKIOKEプロジェクトです。全国25の蔵が連携し、木桶しょうゆの魅力を発信するブランドを立ち上げました。その結果、木桶しょうゆの輸出額は5年で3倍に増加。いまでは海外の高級スーパーやホテルでも扱われるようになり、小豆島には年間1万人を超える外国人観光客が訪れています。
山本さんは番組で「木桶はただの容器ではない。日本の気候と職人の技が作り出した“文化の器”」と語りました。その言葉には、発酵を支える“モノづくりの精神”が息づいています。
発酵文化を守る鍵は“物語”にある
番組のラストで、小倉ヒラクさんは「発酵食品を守るには、買って支えること、そして自分で作ってみることが大切」と語りました。地域の食には、それぞれに“物語”がある。海とともに生きたハタハタずし、山の恵みに寄り添う天日干し大根、寒さに耐えるために生まれた雪納豆――どれも人々の暮らしと結びついた文化遺産です。
発酵とは単なる食技術ではなく、人と自然が協力し合う“共生の知恵”。その背景を知ることが、食をより豊かに味わう第一歩なのです。
まとめ:ブームの先にある“文化としての発酵”を未来へ
この記事のポイントは次の3つです。
・海外では発酵食品が「健康・美味・文化」の象徴として人気だが、日本国内では原料・人手・技術の継承が危機にある。
・伝統と科学を融合させた新たな試みが始まりつつあり、対馬の『せんだんご』や小豆島のKIOKEプロジェクトはその象徴。
・発酵を守るには、消費者一人ひとりが地域の物語を知り、“買って応援する”意識を持つことが大切。
発酵食品の香りや味わいは、単なる「おいしさ」を超えて、日本人の暮らしの記憶を伝えています。ブームの熱狂の先にあるのは、“文化としての発酵”をどう未来に残すかという問い。日本の発酵が再び世界を魅了するためには、私たち自身がその価値を見直し、次の世代へ語り継ぐことが何よりも重要です。
(参考:NHK総合『クローズアップ現代』2025年10月29日放送「日本の“発酵食品”が世界でブーム その陰で危機が」)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


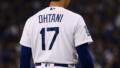
コメント