驚きのポテンシャル!発泡スチロールの秘密を探る
「スーパーのトレーや宅配の箱に使われている発泡スチロールって、ただの梱包材でしょ?」と思っていませんか?実は2025年の今、私たちの生活をあらゆる形で支え、驚くほど多くの場面で活躍しているんです。この記事では、NHK総合の人気番組【有吉のお金発見 突撃!カネオくん】(9月14日放送)で紹介された“発泡スチロールの秘密”をまとめます。読めば、あなたの身近な発泡スチロールを見る目がガラッと変わるはずです。
軽い!強い!環境にも優しい工場の秘密
茨城県猿島郡にある老舗の発泡スチロールメーカーの工場では、まず石油から作られた直径1mmほどの小さなビーズを原料にします。このビーズを専用の機械に入れて加熱すると、なんと約50倍の大きさにふくらみ、あの軽くて丈夫な発泡スチロールが誕生します。
できあがった発泡スチロールの98%は空気。そのため非常に軽く、しかも断熱性や防湿性に優れているのが大きな特徴です。だからこそ、マイナス何十度という極限の寒さにさらされる南極・昭和基地の建物や、鮮度が命の食品輸送の現場など、過酷な環境で欠かせない存在になっています。
さらに注目すべきはリサイクルの仕組みです。1990年代後半から再利用が本格的に進み、不要になった発泡スチロールを回収して再び資源に活かす取り組みが広がりました。2025年現在、その有効利用率は94%に達しており、資源循環の面でも着実な進化を遂げています。発泡スチロールは「ただの梱包材」というイメージを超えて、環境にも優しい素材へと進化しているのです。
広島駅の路面電車を支える発泡スチロール
広島駅の路面電車ホームへと続く高架橋には、実は大量の発泡スチロールが使われています。その理由はとてもシンプルで「軽いから」。もし通常のコンクリートを使用すると、地下道の上では重さに耐えられず施工が難しくなります。しかし発泡スチロールなら重機を必要とせず、人の手だけで設置できるほど軽量。それでいて強度もしっかり確保できるため、土木建築の現場で重宝されているのです。
この工法は広島駅だけでなく、高速道路の盛り土やサービスエリアの基盤など、全国各地のインフラにも広がっています。実際に大手建設会社の大林組が採用した事例も紹介され、軽量素材としての可能性の大きさにスタジオの出演者たちも驚きの表情を見せていました。
普段何気なく利用している駅や道路。その足元を支えているのが、身近な発泡スチロールだと知ると、素材への見方が大きく変わりますね。
食品トレーの進化が“ツマ”を消した?
スーパーでよく目にする食品トレーも、実はほとんどが発泡スチロール製です。茨城県にある国内最大級の工場では、年間でなんと250億枚もの食品トレーを生産しています。この工場では、ネタが動かないように工夫された寿司用トレーや、見た目を美しくするためのフィルム印刷による柄付きトレーなど、日々進化した製品が作られています。
特に大きな変化をもたらしたのが、2015年頃から普及した「段差付きトレー」です。それまで刺身の盛り合わせには「見栄えを整えるためのツマ(大根のけん)」が必ず添えられていました。しかし段差を利用することで刺身が立体的に配置できるようになり、ツマを置かなくても十分に美しい盛り付けが可能になったのです。
この工夫は、ただ見た目を変えただけでなく「食べられずに捨てられるツマを減らす」という食品ロス削減にも大きく貢献しました。毎日多くの人が利用するスーパーの食品トレーが、環境への配慮や食文化の変化を後押ししているのは驚きですね。
アートや街のシンボルに変身する発泡スチロール
発泡スチロールは、その軽さと加工のしやすさを生かして、オブジェ制作の分野でも大活躍しています。
静岡県伊豆の国市にある専門工房では、最新のイタリア製アーム型ロボットを導入。3Dデータを読み込ませることで、自動で発泡スチロールを削り出し、年間1000点以上の展示物を製作しています。削る場所に合わせてドリルを自動交換する仕組みまで備えており、正確でスピーディーに造形できるのが特徴です。仕上げや塗装は職人の手作業で行われるため、完成品はリアルで迫力あるオブジェとなります。
一方で、埼玉県川越市のヤジマキミオさんは、あえて手作業にこだわる発泡スチロールアーティスト。企業や自治体から依頼を受け、街のシンボルや看板などをこれまでに500点以上手掛けてきました。発泡スチロールのブロックに下書きをし、熱で溶かしながら形を削り出し、さらにヤスリで磨き上げ、最後に彩色して完成させます。その過程を経て仕上がったオブジェは、美術館や恩賜上野動物園など、誰もが訪れる場所で目にすることができます。
身近な発泡スチロールが、芸術や街づくりにまで役立っていると知ると、素材の可能性を改めて感じられますね。
身近に感じる発泡スチロールのありがたさ
スタジオでは、ゲストたちが身近で体験した「発泡スチロールに助けられているエピソード」を語りました。
女優の木竜麻生さんは「魚を注文すると付いてくる紐付き発泡スチロール箱を、そのままクーラーボックス代わりに使っている」と話しました。軽くて保冷力もあるため、アウトドアや買い物でも便利に再利用できるといいます。
俳優の松尾諭さんは、最近になって「自分の自家用車の運転席の下に発泡スチロールが使われていた」ことに気づき、意外な場所での利用に驚いたそうです。
お笑い芸人の信子さんは、自宅で飼っている猫が発泡スチロールを爪とぎにしてボロボロにしてしまうと告白。
そらちゃんの成長エピソード
番組に小学6年生の頃から出演している田牧そらさんは、先日19歳の誕生日を迎えました。記念に選んだのは、なんともユニークな餃子型のポーチ。通販で探したものの、商品代金よりも送料のほうが高くつくことが分かり、「それなら直接買いに行こう」と思い立ち、宇都宮市まで足を運んだそうです。
現地では念願のポーチを手に入れるだけでなく、せっかく来たからと本場の餃子をたっぷり堪能。
まとめ:発泡スチロールは未来を支える素材だった
今回の放送で見えてきたのは「発泡スチロール=ただの箱」というイメージの誤解。実は暮らし、インフラ、食品、アート、さらには環境保護まで幅広く役立っています。
この記事のポイントは以下の通りです。
-
発泡スチロールの98%は空気。軽くて断熱・防湿に優れる
-
広島駅や高速道路などインフラを支える重要素材
-
食品トレーの進化で食品ロス削減にも貢献
-
オブジェやアート作品にも幅広く利用
-
私たちの身近な暮らしに根付く存在
今後も新たな使い道が開発され、さらに暮らしに役立つ可能性を秘めています。発泡スチロールを見かけたら「未来を支える素材」として少し誇らしく感じられるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


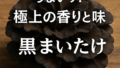
コメント