江戸時代に100万人が訪れた大山詣りの秘密
2025年7月5日放送の「ブラタモリ」では、神奈川県伊勢原市にある大山を巡り、江戸時代に大流行した「大山詣り」の歴史や魅力が紹介されました。タモリさんと佐藤茉那アナウンサーが、江戸っ子たちがなぜ大山を目指したのか、そして大山が「雨を降らせる山」と呼ばれる理由を探っていきました。
大山詣りは、江戸時代、年間100万人もの参拝者が訪れた人気行事でした。今回は、その背景にある歴史や自然、江戸の人々の暮らしとの関わりを分かりやすく解説します。
| 場所・内容 | 説明 |
|---|---|
| 大山(神奈川県伊勢原市) | 標高1252メートル。江戸時代から信仰の対象。 |
| 大山詣り | 江戸時代、粋でいなせな江戸っ子が目指した参拝登山。 |
| 大山阿夫利神社 | 大山の山頂付近にある神社。雨を降らせる神として信仰。 |
| 大山ケーブルカー | 日本唯一、離合ポイントに駅があるケーブルカー。 |
| 納め太刀(6メートル) | 江戸時代、意味を込めて奉納された大きな太刀。 |
| 登拝門 | 山頂へ向かう参道の入口。夏の開山期だけ開いていた。 |
| 東海道五十三次・藤沢宿 | 江戸時代、帰り道で立ち寄る観光地のひとつ。 |
来週のこの時間は【知的探求フロンティア】AIは人間を超えるか?タモリ×山中伸弥×松尾豊が語る未来の衝撃|2025年7月12日放送
粋でいなせな江戸っ子が大山を目指した理由

江戸時代に大人気だった大山詣りは、単なる登山や観光ではなく、信仰と暮らしが深く結びついた特別な行事でした。大山は、昔から「雨を降らせる山」として知られ、江戸の町を火災から守ってくれる存在として多くの人々に信仰されてきました。火事の多かった江戸では、雨はとても大切で、大山の恵みの雨が町の安全を守ると考えられていたのです。
特に、江戸の火消したちが大山を信仰し、参拝する姿が多く見られました。火消しは町の安全を守る仕事をしているため、雨を降らせる神様への感謝と祈りの気持ちを込めて大山に登ったのです。
また、大山詣りは信仰だけでなく、楽しみや遊び心もたくさん詰まっていました。暑い夏の日、江戸っ子たちは避暑もかねて大山を訪れ、道中の自然や滝を楽しみました。大山のふもとや山中には、涼しい滝や水場が点在し、そこで涼をとるのが江戸っ子の粋な過ごし方でした。
具体的には次のような楽しみ方がありました。
・滝で体を冷やすことができ、夏の暑さを忘れられる
・道中の茶屋や休憩所で一息つくのも楽しみのひとつ
・ふもとの宿場町で名物料理やお土産を買う
・家族や仲間と一緒に大山登山をすることで思い出づくり
こうした楽しみ方と、信仰の気持ちをうまく組み合わせて、大山詣りは江戸の人々の間で大流行しました。単に真面目に参拝するだけでなく、旅の中で自然や涼しさ、美味しいものを味わい、最後に山頂の神様に手を合わせるという流れが、「粋でいなせ」な江戸っ子らしい文化だったのです。
このように、大山詣りは江戸の人々にとって、信仰・自然・遊びが一体となった大切な行事でした。今も昔も、山の恵みと涼しさを求めて多くの人が訪れる理由がよくわかります。
大山が雨を降らせる本当の理由とは

今回の番組では、タモリさんと佐藤アナウンサーが大山がどうして雨を呼ぶのかを地質や気象の観点から詳しく紹介しました。大山は、ただの高い山ではなく、長い年月をかけてできた特別な場所だったのです。
およそ1500万年前、今の大山や伊豆半島は、もっと離れた場所にありました。当時、フィリピン海プレートという大きな地盤がゆっくり動き、伊豆半島が本州に近づいてきたのです。伊豆が本州とぶつかることで、大地が押し上げられ、今の丹沢山地や大山が誕生しました。この時にできた大山は、急な斜面や高い山頂を持つ特徴的な山になったのです。
その後、自然の仕組みが重なり、大山は雨を降らせやすい場所となりました。特に、夏になると相模湾から暖かくて湿った南風が吹いてきます。この湿った空気が大山にぶつかると、急な斜面で空気が上へと押し上げられ、上空で冷やされていきます。冷えた空気は水蒸気を含み、やがて雨雲ができて雨が降るのです。
具体的には次のような流れです。
・相模湾から湿った暖かい風が大山に向かって吹く
・急な山の斜面にぶつかり、空気が上昇する
・上空で冷やされた空気が雨雲を作る
・雨が降り、江戸やその周辺の町に水をもたらす
この自然の仕組みのおかげで、大山は昔から「雨を降らせる山」と呼ばれ、多くの人に信仰されてきました。特に火事が多かった江戸の町では、大山の恵みの雨がとても重要だったのです。
だからこそ、大山詣りはただの観光ではなく、江戸の町を火災から守ってくれる雨の神様に感謝を伝える、大切な行事となっていたのです。大山の地形や気候の秘密を知ると、昔の人々が大山に特別な思いを抱いていた理由がよくわかります。
珍しい大山ケーブルカーと山頂の神社へ

今回の旅でタモリさんと佐藤アナウンサーが利用したのが、大山ケーブルカーです。このケーブルカーは、とても珍しい特徴を持っています。日本全国のケーブルカーの中でも、列車がすれ違うポイントに駅が設置されているのはここだけです。この独特の構造は観光客にとっても話題で、乗っているだけでちょっとした探検気分を味わえます。
大山ケーブルカーは、ふもとの駅から山の中腹に向けて運行しています。山の斜面に沿ってぐんぐん登っていく景色は迫力があり、途中には森や急な坂道が続きます。列車がすれ違う瞬間は特に見どころで、タイミングが合えばその様子を間近で見ることができます。
ケーブルカーを降りた場所は、大山阿夫利神社の参道です。この神社は、昔から多くの人に信仰されてきた場所で、山の中腹に広がる自然とともに、厳かな雰囲気に包まれています。山からは相模湾や町並みを一望でき、晴れた日には遠くまで見渡せる絶景スポットでもあります。
江戸時代には、この神社だけでなく、近くに大山寺もありました。大山寺は修行の場や祈願の場としても知られ、多くの参拝客や修行者が集まる場所でした。当時の人々にとっては、山を登りながら自然の恵みを感じ、神社やお寺で手を合わせることで、心も体も清められる大切な時間だったのです。
現在もこの場所は、信仰と観光の両方が楽しめる人気スポットとして、多くの人が訪れています。自然の中をケーブルカーで登り、歴史ある神社や美しい景色を堪能できるこの場所は、今も昔も変わらず人々の心をひきつけています。
江戸時代の巨大な納め太刀と現代の奉納
番組の中で紹介された納め太刀は、江戸時代から続く大山詣りの伝統のひとつです。この太刀は、なんと長さ約6メートルにもなる巨大なものです。しかし、重要なのは太刀の大きさそのものではなく、奉納するという行為に込められた意味です。
江戸の人々は、大山を「雨を降らせる神様」として信仰してきました。そこで、自分や家族の無事、町の安全、商売繁盛などの願いを込めて、太刀を大山に奉納したのです。大きな太刀には、たくさんの人の思いが詰まっていました。奉納された太刀は、単なる装飾品ではなく、人々の祈りの象徴として大切に扱われてきました。
納め太刀は次のような特徴があります。
・約6メートルの巨大な太刀
・太刀の大きさよりも「奉納する気持ち」が大切
・江戸時代から続く信仰の伝統
・願いごとや感謝の気持ちを込めて奉納される
今回のブラタモリでは、タモリさん自身も実際に大山で太刀を奉納しました。このシーンでは、現代でも大山詣りの伝統がしっかり受け継がれていることが伝わってきました。昔の人々と同じように、今も大山に願いを込めて太刀を納める文化が残っているのです。
大山詣りは、ただの観光ではなく、長い歴史の中で育まれた信仰と文化が今も息づいていることを感じさせる場面でした。太刀の奉納を通して、多くの人が大山の神様に感謝や願いを届けてきた歴史が、今も変わらず続いているのです。
登拝門と山頂へのリモート参拝
大山の山頂へと続く道の入口にあるのが登拝門です。この登拝門は、江戸時代には特別な意味を持つ場所でした。当時、山頂への道は夏の開山期だけに限られていて、登拝門もその期間だけ開かれていたのです。参拝客たちは、夏の限られた時期に門が開かれるのを待ち、山頂を目指していました。
現在では道や施設が整備されており、登拝門もきれいな状態で残されています。当時の雰囲気を感じさせる石段や鳥居も見られ、江戸の人々がどんな思いで山に登ったのかがよくわかります。
今回の番組では、タモリさんと佐藤アナウンサーが山頂と中継をつなぎ、リモートでのお参りを行いました。実際に山頂まで登らなくても、映像を通じて神社や山頂の様子を感じることができる、今の時代ならではのスタイルが紹介されました。
リモート参拝の特徴は次の通りです。
・登らなくても山頂の様子をリアルタイムで見られる
・神社の雰囲気や自然の風景を映像で体験できる
・体力に自信がなくても気軽に参拝できる
江戸時代には、苦労して山を登ること自体が修行であり、大きな意味を持っていましたが、現代は誰でも安全に参拝を楽しめる工夫がされています。リモート参拝は、山頂の雰囲気を感じつつ、信仰や歴史に触れられる新しい方法として、多くの人に注目されています。
こうした現代の取り組みによって、大山詣りの伝統や信仰の心は今も受け継がれています。江戸時代から続く大山への思いは、時代が変わっても多くの人に大切にされているのです。
大山詣りの帰り道も楽しみのひとつ
大山詣りの楽しさは、山を登ることや参拝するだけでは終わりません。帰り道の寄り道こそが、江戸っ子たちにとって最大の楽しみのひとつでした。特に人気だったのが、東海道五十三次の藤沢宿を経由して江の島へ立ち寄るコースです。
藤沢宿は、東海道の宿場町のひとつで、旅人が休憩したり、名物を楽しんだりできるにぎやかな場所でした。ここでは、地元の料理を味わったり、お土産を買ったりして、参拝の余韻をゆっくり楽しむのが粋な過ごし方とされていました。
さらに、藤沢宿を抜けた先にある江の島は、美しい海と景色が広がる人気スポット。海沿いを歩きながら、潮風にあたり、江戸の町とはまた違った自然を感じることができました。旅の疲れを癒しながら、最後まで遊び心を忘れないのが、江戸っ子の旅のスタイルだったのです。
具体的な寄り道の楽しみ方にはこんなものがあります。
・藤沢宿の茶屋でひと休みし、名物料理を味わう
・江の島で海の景色を眺め、磯遊びを楽しむ
・土産物屋を巡って旅の思い出を持ち帰る
・仲間や家族と旅の話をしながら帰路につく
まとめ
今回のブラタモリでは、こうした大山詣りの歴史や自然、そして江戸の人々の思いが丁寧に紹介されました。大山は、昔も今も変わらず多くの人々に愛され、訪れる人の心を引きつけています。
現代でも、自然や歴史を感じながら大山を訪れ、その後に江の島まで足を延ばすコースは人気があります。皆さんもぜひ一度、江戸っ子の気分で大山詣りに出かけてみてはいかがでしょうか。参拝だけでなく、帰り道までしっかり楽しめるのが、この旅の醍醐味です。
【参考ソース】
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/oyama_mairi/story/story02.html
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/oyama_mairi/heritage/osamedachi/
https://isehara-kanko.com/history/afurijinja/
https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/special/meguri/isehara/
https://www.afuri.or.jp/about/
https://www.atsugi-kankou.jp/site/yamanami-kikou/cyoubou-ooyamaafurijinjya-isehara.html
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

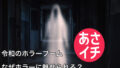
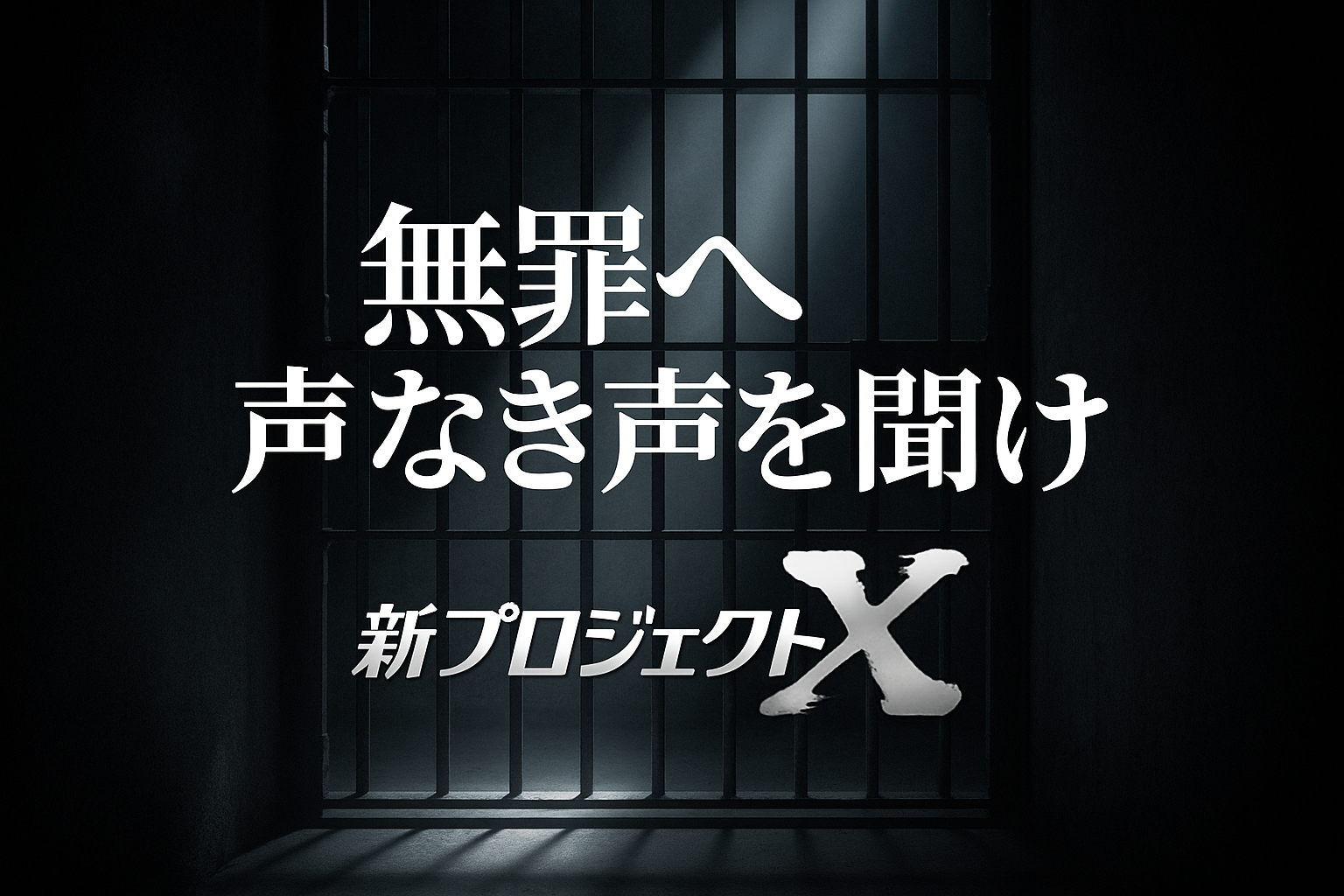
コメント