京都・二条城に秘められた徳川三代の思惑とは
京都の中心に立つ二条城。多くの人が「大政奉還の舞台」として知っていますが、番組ではその奥に潜む“徳川三代の思惑”を深くたどっていました。家康・秀忠・家光の三代が、天皇との距離をどう測り、政治と権威をどう操ろうとしたのか。その痕跡が建物や庭、堀の幅にまで残されていることが浮かび上がっていきます。歴史が静かに刻まれた石垣や庭園が、何百年も前の「本気の政治」を語り出す旅でした。
【NHKスペシャル「戦国サムライの城」第1集・織田信長“驚異の城郭革命”】藤戸石と黄金の瓦岐阜城、安土城破城の痕跡が語る“城郭革命”の真実|2025年9月14日放送
二条城の堀幅に宿る家康の“天皇への配慮”
旅のスタートは東大手門からでした。二条城を訪れたタモリさんが最初に注目したのは、意外にも“守りの弱さ”です。城の堀幅は14m。これだけを見ると、同じ徳川家康が建てた名古屋城(堀幅65m)と比べてもかなり小さく、戦いを意識した城とは思えません。
しかし、この設計こそが家康の計算でした。二条城のすぐそばには御所があり、天皇が暮らす極めて重要な場所がありました。そこで家康は、武士のリーダーとしての威厳は見せつつも、天皇に恐怖や圧迫感を与えないように堀幅を控えめにしたと考えられます。
見た目は静かで穏やかですが、その裏には「天皇との良好な関係を保ちながら政治の主導権を握る」という緻密な思考が込められていました。堀の14mという数字から、当時の権力バランスの微妙さがはっきりと伝わってきます。
神泉苑が語る“城の置き場所”の意味
続いてタモリさんが向かったのは神泉苑。794年に桓武天皇が造営した庭園で、京都の歴史そのものを宿した場所です。
家康が二条城を築こうとしたとき、この周辺にはすでに織田信長や豊臣秀吉が城を構えていました。政権を握った新しい武家のトップとして、どこに城を構えれば天皇との距離を保ちつつ、先人たちとの位置関係も損なわないか。その選択が二条城の場所でした。
京都の中心で多くの権威が重なり合う中、家康は「前に出すぎないが、存在を消さない」絶妙なラインを選びました。この地を訪れたことで、城の位置そのものが政治の一つの表現であったことが実感できます。
北側に残された石垣が示す秀忠・家光の狙い
城の北側へと足を進めると、石垣の積み方に違いが見えてきます。古い部分と新しい部分が混じり合うこの場所は、徳川秀忠と徳川家光が増改築した痕跡でした。
この時期に大きく整備されたものの一つが、現在は特別名勝に指定されている二の丸庭園です。この庭園は、美しさを楽しむためだけではなく、“天皇を迎えるため”の特別な空間でした。
秀忠の娘である徳川和子が後水尾天皇に嫁ぎ、徳川家と天皇家が親戚関係になったことで、両者の距離は大きく縮まります。家康の時代には慎重に保たれていた距離感が、秀忠・家光の代になると明確に「天皇家との近さ」を示す方向へ動いていくのです。石垣の積み方ひとつが、政権の方向性を静かに物語っていました。
二条城の行幸で実現した徳川の“見せ場”
当時、二条城で行われた行幸は、まさに政治の大舞台でした。秀忠と家光が天皇をもてなすために整えた二の丸御殿や二の丸庭園は、武家政権の格式を美しく演出する役割を担っていました。
行幸ののち、和子は男児を出産します。将来の天皇候補となる重要な存在でしたが、わずか幼い年に病気で亡くなります。番組では「もしこの男児が成長して天皇となっていたら、江戸幕府の終わりは違う形になっていたかもしれない」という歴史の分岐点に触れていました。
徳川家が天皇とどれほど深い関係を築こうとしていたか、その本気度が二条城の空間全体から伝わってきます。豪華な建物だけでなく、一つひとつの庭石や柱の配置にまで、政治の意図がしっかりと込められていました。
二条城に刻まれた三代のドラマが浮かび上がる
旅の終盤、タモリさんは二条城がただの城ではなく、歴史の“舞台装置”であることを理解していきます。堀幅の調整、城の位置選び、石垣の変化、庭園の整備。これらはすべて別々のものではなく、徳川三代が時代ごとに選択した政治の形が重なり合った結果でした。
家康の慎重さ、秀忠の外交戦略、家光の積極的な関係構築。その三つの流れが、今の二条城の姿となって残っています。歩けば歩くほど、石や木が当時の空気を思い出させてくれるような深い時間が流れていました。
まとめ
今回の「ブラタモリ」は、二条城を“政権の心臓部”として捉え直す旅でした。
家康は天皇への配慮を建築に込め、秀忠と家光は天皇との関係を強化するために増築を重ねました。二の丸御殿や二の丸庭園、石垣の違い、行幸の演出。どれもが政治の一手として使われていたことが鮮明に分かりました。
静かな城の内部に潜む“権力の鼓動”を感じられる内容で、歴史の奥にある思惑がより立体的に見えてくる旅でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

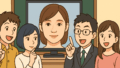
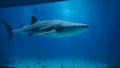
コメント