東京大学の“宝”を探るブラタモリ旅
NHK総合で2025年8月30日に放送された「ブラタモリ」では、東京大学本郷キャンパスを舞台に、タモリさんと佐藤茉那アナウンサーが「東大にしかない“宝”」を探し歩きました。番組では、歴史の舞台となった安田講堂、膨大な史料を守る史料編纂所、そして研究の成果が詰まった博物館をめぐり、東大の特別な魅力を紹介しました。この記事では放送内容をすべてまとめ、検索して訪れた方が「どんな宝があるのか?」という疑問にわかりやすく答えます。
安田講堂に刻まれた歴史

旅は、東京大学のシンボル的存在である安田講堂からスタートしました。この建物は、東大の正門を入ってまっすぐ進んだ真正面に位置しており、まさに大学を代表する存在です。外観の重厚さだけでなく、構造にも大きな特徴があります。実は講堂は崖の下に建てられており、入口部分は崖の上にあたるため、扉をくぐるとすでに建物の3階に直結しているという独特の造りになっています。普段見慣れている講堂とは異なる構造は、訪れる人に驚きを与えると同時に、建築技術の工夫を感じさせます。
また、この安田講堂は単なる建物ではありません。1960年代後半には、世間を揺るがす「東大安田講堂事件」がここで発生しました。学生たちが立てこもり、機動隊と衝突するという前例のない大事件となり、日本の学生運動を象徴する舞台となったのです。その際に生じた焼け焦げや破損の跡は、あえて完全には修復されず、今も講堂の一部として残されています。これらの傷跡は、過去に何が起きたのかを静かに語りかけ、訪れる人に歴史の重みを実感させてくれます。
つまり、安田講堂は単なる大講堂や大学施設ではなく、日本の学生運動の象徴であり、さらに東大の歩みそのものを物語る宝です。その場に立つと、建物自体が時代の証人であるかのように感じられ、歴史を受け止め、後世に伝える役割を果たしていることがよくわかります。
史料編纂所が守る日本の歴史
続いてタモリさんたちが足を運んだのは、東京大学史料編纂所です。ここは日本史研究の中心ともいえる場所で、歴史好きにとってまさに夢のような空間です。編纂所で取り組まれているのは「大日本史料」という膨大な歴史資料の編集・刊行作業。この史料は、古代から近代に至るまでの日本の出来事を体系的に記録しようという壮大なプロジェクトで、「日本書紀」の続きを作るという大きな目標のもとで始まりました。
その歴史は古く、なんと1901年から刊行がスタートし、現在までに429冊という驚くべき数が世に送り出されています。百年以上にわたる努力が積み重ねられてきたことを考えると、研究者たちの根気と情熱の深さが伝わってきます。
しかし、ここで扱う史料の多くは非常に古く貴重なため、すべてを原本のまま保存することはできません。そこで登場するのが「影写」という特別な技法です。これは、原本の筆跡や書きぶりをそっくりそのまま写し取る方法で、文字の形や筆の運び方まで忠実に再現されます。番組では、研究員の宮崎さんが実際に織田信長の影写を披露してくれました。その一枚は、まるで本人の直筆を目の前にしているかのような迫力と臨場感にあふれていました。
一文字一文字が丁寧に再現されたその姿は、単なる資料の複製を超えて、研究者の技と執念の結晶といえます。このような細やかな作業の積み重ねが、歴史を正しく未来に伝える力となっているのです。そして、この地道な努力こそが、東京大学にしかない知の宝として輝き続けています。
総合研究博物館に眠る宝の山
最後にタモリさんたちが訪れたのは、東京大学総合研究博物館です。ここは学術の“宝庫”とも呼べる場所で、教授や研究者が国内外で長年にわたって収集してきた標本や資料が400万点以上も所蔵されています。その膨大な数は一大学の博物館としては異例であり、まさに知の集積地といえるでしょう。
展示されているものの中には、70年ほど前から世界各地の砂漠のオアシスで採取され続けてきた「水のコレクション」もあります。一見するとただの瓶に入った水ですが、実際には非常に貴重な研究資料です。これは砂漠でどのように水を確保し、利用してきたのかを知るために集められたもので、治水技術や環境研究に欠かせない役割を果たしています。人類が厳しい自然の中で生き抜くために築いてきた知恵を読み解く手がかりともなり、未来の水資源研究にもつながる重要なコレクションです。
さらに、館内には地質学者ナウマンに関連する資料も保存されています。ナウマンは明治時代に日本の地質を調査し、「ナウマンゾウ」の名で知られる化石研究でも有名な人物です。その功績を示す資料は、日本の地質学の礎を築いた証でもあり、東大の研究の深さを実感させてくれます。加えて、動植物の標本や鉱物、考古学的遺物など、多岐にわたる自然史の宝が所狭しと並び、訪れる人を圧倒します。
こうした収集物は、ただ集められただけの“物”ではありません。研究者たちの好奇心が新たな価値を見出し、それを学問へと昇華させることで“宝”へと変わっていくのです。タモリさんも、膨大な展示を前に思わず「宝の山だ」と声を上げるほどの圧巻の光景で、学問の奥深さとロマンを存分に感じられる場となっていました。
東大にしかない“宝”とは?
今回の旅を通して明らかになったのは、東京大学の“宝”とは単に建物や標本といった物質的なものにとどまらない、ということです。それは「歴史を刻んだ場所」「知を受け継ぐ技」「好奇心から生まれる研究の成果」といった、目に見えるものと目に見えないものが重なり合い、深く息づいているという点にあります。
たとえば、安田講堂に残された傷跡は、半世紀以上前に起きた出来事を今に伝え、過去の重みを肌で感じさせてくれます。史料編纂所で進められる「大日本史料」の編纂作業は、日本の歴史を未来へ受け継ぐための技と努力の結晶です。そして、総合研究博物館に集められた膨大な標本や資料は、研究者たちの果てしない情熱が形となった成果であり、学問の新しい可能性を生み出しています。
これら一つひとつは単独でも大きな価値を持ちますが、互いに補い合うことでさらに輝きを増しています。歴史を伝える力、知を守り続ける力、そして未来を切り拓こうとする力。そのすべてが重なり合って、他にはない東大ならではの財産となっているのです。訪れる人にとっても、それは単なる展示や建物ではなく、「人と学問が積み重ねてきた時間そのもの」として心に残る“宝”だといえるでしょう。
まとめ
「ブラタモリ 東京大学の宝」では、安田講堂、史料編纂所、総合研究博物館という3つの舞台を通じて、東大にしかない“宝”を紹介しました。それは建築や標本といった具体的なものにとどまらず、歴史を受け止め、知を残し、未来へとつなぐ人々の姿勢そのものが宝だと感じられます。この記事を読んだ方も、東大を訪れる際には「ただの建物」や「ただの展示物」としてではなく、その背景にある物語や人々の努力を思い浮かべてみてはいかがでしょうか。そうすることで、東大の宝がより一層輝いて見えるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


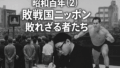
コメント