神楽坂ってなぜ大人の隠れ家なの?
東京にいながらちょっと特別な時間を過ごせる街、それが神楽坂です。おしゃれな路地裏にカフェや料亭が立ち並び、今では「大人の隠れ家」と呼ばれる人気エリア。でも、なぜこの街がそんな独特の雰囲気を持つようになったのでしょうか?「裏路地が多いから?」「芸者文化が残っているから?」と気になる人も多いはず。この記事では、2025年9月27日に放送された『ブラタモリ』の内容をもとに、歴史と街の構造をひも解きながら、神楽坂の魅力をわかりやすく紹介します。
NHK【ブラタモリ】京都・三十三間堂SP▼超拡大版!京の大仏と地盤改良が国宝を守った驚きの800年史|2025年9月20日放送★
江戸城とつながる坂の始まり

旅は飯田橋駅前から始まりました。駅を出てすぐに見えるのが、ゆるやかに伸びる神楽坂の坂道です。この坂道はただの街路ではなく、実は江戸時代に大きな役割を持っていました。神楽坂は江戸城の外堀に接していて、今でもその名残として牛込御門の石垣が残されています。石垣の大きな石は当時の職人が丹念に積み上げたもので、往時の迫力を今に伝えています。
坂道を歩くと、道の途中でアップダウンが目立ちます。これは江戸時代に将軍が通るためのルートとして整備されたからで、最短距離を優先した結果、あえて高低差を気にせずに道を通したといわれています。効率を重んじた江戸の街づくりの考え方が、今もそのまま形として残っているのです。
坂を上りきると現れるのが、神楽坂を象徴する寺院、毘沙門天・善國寺です。創建は16世紀後半とされ、江戸時代から庶民の厚い信仰を集めてきました。境内には毘沙門天の像が祀られており、商売繁盛や厄除けのご利益があるとされています。神楽坂の中心に位置することから、地元の人々だけでなく参拝客や観光客にとっても目印の存在になっています。
善國寺を囲む門前の通りは、江戸時代からにぎわいの中心でした。祭礼のときには人々が集まり、屋台や見世物が並んでいたと伝えられています。現代でも毎年夏に行われる「神楽坂まつり」では、境内を中心に盆踊りや縁日が開かれ、昔ながらの賑わいを感じることができます。
こうして、飯田橋駅から始まる神楽坂の坂道は、江戸の歴史を今に伝えると同時に、街のシンボルである毘沙門天・善國寺へと人々を導く道として息づいているのです。
徳川将軍が訪ねた大名屋敷

坂を登った高台には、かつて大名の下屋敷が構えられていました。所有していたのは、徳川幕府の重臣として名を馳せた酒井忠勝です。忠勝は徳川家康・徳川秀忠・徳川家光の三代に仕え、その誠実さと忠義で厚い信頼を得ていました。
特に徳川家光は忠勝に強い信頼を寄せており、記録によればこの神楽坂の屋敷を145回も訪れたとされています。将軍が頻繁に足を運んだという事実は、この地が単なる居住空間ではなく、政治や日常を離れた「心安らぐ場」として重要な役割を果たしていたことを示しています。
こうした背景から、神楽坂は早くから「将軍や大名が特別な時間を過ごすための場所」としての性格を帯びていました。この特別な歴史が、後に「大人の隠れ家の街」と呼ばれる土台となり、街の雰囲気を形づくっていったのです。
崖下に生まれた花街のルーツ

江戸時代後期になると、神楽坂の崖下に非公認の遊郭である『岡場所』が誕生しました。公には認められていなかったものの、多くの人々が足を運び、やがて街の独特な雰囲気を生み出していきました。
その流れは明治時代に入るとさらに加速します。当時の政府は「人目に付く派手な建物を建ててはならない」という禁令を出していましたが、崖下という立地は表通りから視線を遮ることができたため、花街を形成するには最適の場所でした。人々の目を避けつつ華やかな文化を育むことができたのです。
こうして神楽坂は、次第に芸者や料亭が軒を連ねる街へと変貌していきました。裏路地には料亭へとつながる小径がいくつも作られ、人目を気にせずに訪れることができる環境が整えられました。そこは単なる歓楽街ではなく、密談や接待、そして洗練された芸事が行われる“大人の社交場”としてにぎわいを見せるようになったのです。
裏路地が生んだ隠れ家文化

神楽坂の大きな魅力といえば、やはり迷路のように入り組んだ裏路地です。細い道が縦横に延び、歩くたびに新しい景色に出会える独特の街並みは、ほかのエリアにはない個性を放っています。
この裏路地の構造は、花街の発展とともに形づくられました。人目を避けて料亭や芸者のもとを訪れるため、あえて複雑に入り組んだ路地が新しく造られていったのです。そこには「隠れること」を前提にした街のデザインが反映されています。
料亭ではさらに細やかな配慮が見られました。中庭に大きな石を置いて視線を遮ることで、他の客と顔を合わせずに済むように工夫されていたのです。加えて、各部屋に専用のトイレを設置し、建物の中には複数の階段が設けられていました。こうした仕掛けにより、客同士が出会わずに行き来できる空間が保たれていたのです。
さらに街には、宮大工の技によって建てられた建物も残されています。釘を使わずに組み上げられたその構造は、現在では登録有形文化財に指定され、当時の高い技術と美意識を今に伝えています。これらの職人技は神楽坂の格を高めるとともに、街そのものを「大人の隠れ家」と呼ばれる存在へと押し上げていきました。
芸者文化の現在

番組には、神楽坂でおよそ60年近く芸者を続けてきた眞由美さんが登場しました。長い年月を芸の道に捧げてきた彼女は、「街は変わっていくけれど、神楽坂が好き」と穏やかに語ります。その言葉には、この街に根付いた文化と、人々を惹きつけてやまない魅力が凝縮されていました。
今も神楽坂では、芸者たちの稽古が日々行われています。三味線や舞、唄といった伝統芸能は受け継がれ、花街としての息遣いは途絶えることなく続いているのです。街を歩けば、石畳の路地裏にカフェやフレンチの名店が並び、現代的な華やかさと昔ながらの芸者文化の余韻が自然に共存しています。
おしゃれで新しいものと、古くからの伝統が同じ場所に息づくこと。それこそが神楽坂の最大の特徴であり、訪れる人が「大人の隠れ家」として惹かれる理由なのです。
まとめ:神楽坂が愛される理由
この記事のポイントは以下の3つです。
-
神楽坂は江戸城外堀と牛込御門の整備から始まった歴史ある街。
-
徳川将軍も訪れた大名屋敷や、崖下にできた花街が「隠れ家」としての基盤をつくった。
-
芸者や裏路地文化が今も残り、伝統と現代の街歩きが融合している。
神楽坂を歩くと、過去と現在が重なり合う不思議な感覚に包まれます。次に東京を訪れるときは、ぜひ表通りだけでなく裏路地も探検してみてください。「大人の隠れ家」の真髄が、きっと見えてきます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


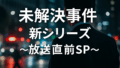
コメント