山岳リゾート・上高地 なぜここまで愛される場所になったのか
日本を代表する山岳リゾート・上高地。清らかな梓川と穂高連峰が織りなす絶景は、まるで絵の中に迷い込んだような美しさです。けれど、今のように多くの人が訪れる観光地になるまでには、意外な歴史と人々の努力がありました。2025年10月11日放送の『ブラタモリ』では、タモリさんが長野県上高地を歩き、その誕生の秘密を探りました。この記事では、放送の内容をもとに、上高地が「日本屈指の山岳リゾート」へと変貌を遂げた道のりをたどります。
【ブラタモリ】長野・上高地▼山岳リゾート・上高地の絶景はどう生まれた?梓川が透き通る秘密と堰止湖の成り立ち|2025年10月4日
江戸時代の上高地 人々が山に入った理由

タモリさんがまず訪れたのは、穂高神社の奥宮が鎮座する神秘の地・上高地。今でこそ静けさと透明な水に包まれた人気の観光地ですが、江戸時代の上高地はまったく異なる姿をしていました。当時、人々がこの地を訪れていたのは、観光ではなく、雨乞いの祈りや木材の伐採のため。山々に囲まれたこの谷は、豊かな森林資源をもつ“働く山”だったのです。
一年のうちに200人を超える杣(そま)と呼ばれる木こりたちが入り、斧や鋸を手に巨木を切り倒し、材木を下流の松本方面へと運び出していました。切り出した木材は家屋の建築や舟の材料、さらには松本城下の燃料としても使われ、当時の暮らしを支える大切な資源でした。川沿いには仮の小屋が建てられ、杣たちは寝泊まりしながら数週間にわたって作業を続けたと伝えられています。上高地は自然の恵みを与える場所であると同時に、人々にとって“生きるための仕事場”でもあったのです。
やがて時代は明治へと移り、上高地は新たな目で見られるようになります。自然の美しさが再発見されたきっかけをつくったのが、イギリス人宣教師で登山家のウォルター・ウェストンです。彼は日本各地の山を歩き、明治21年(1888年)に初めて上高地を訪れ、その壮大な景観に魅了されました。ウェストンは著書でこの地を紹介し、のちに「日本アルプス」という言葉を世界に広めました。この呼び名が、上高地を“日本のアルプスの玄関口”として知らしめるきっかけとなったのです。
ウェストンの登山を支えたのが、地元の猟師であり名ガイドとして知られる上條嘉門次(かみじょう・かもんじ)。彼は上高地・明神周辺を熟知しており、危険な沢や岩場を迷いなく案内しました。二人の友情は深く、嘉門次が営んでいた山小屋「嘉門次小屋」は今も残り、訪れる登山者たちに温かいおもてなしを続けています。
上高地が“信仰の山”から“憩いと探求の山”へと姿を変えていった背景には、このように地元の人々と外国人登山家の出会いがありました。自然と人が共に歩みを進めたこの時代が、のちの上高地を日本屈指の山岳リゾートへと導いた原点となったのです。
“風穴”がつないだ近代化への道
タモリさんが次に向かったのは、上高地から車でおよそ40分、長野県松本市の山あいにある稲核(いねこき)という集落。ここは古くから涼風が吹き出す「風穴(ふうけつ)」の地として知られています。風穴とは、岩の隙間から一年中冷たい空気が流れ出る天然の冷蔵庫のような場所。夏でも内部の温度は5℃前後に保たれ、氷を使わずにものを冷やすことができる貴重な自然の仕組みです。
明治時代、この風穴が大きな役割を果たしました。当時、日本の主力輸出品だったのが絹(シルク)。そのもととなる蚕(かいこ)の卵=蚕種(さんしゅ)は、一定の低温で保存しなければ孵化してしまいます。しかし冷蔵技術のない時代、夏場の保存は非常に難題でした。そこで注目されたのが、稲核の風穴です。ここでは地元の人々が石垣で風の通り道を整え、湿度を保ちながら蚕の卵を安全に貯蔵しました。この自然の冷気を活用した「蚕卵貯蔵業」は全国的に広まり、日本の絹産業を陰で支える重要な技術となったのです。
稲核で保存された蚕卵は、やがて富岡製糸場など各地の製糸工場に運ばれ、高品質な絹糸を生み出しました。明治から大正にかけて、日本は世界最大の生糸輸出国となり、近代化の象徴として繁栄していきます。その支えとなったのが、山の中の小さな風穴だったという事実は驚くべきことです。
やがて、風穴での貯蔵業が盛んになると、松本市から稲核までの輸送路を改良する必要が生まれました。明治37年(1904年)、この地域に新たな道路が整備され、物資や人の往来が活発になります。これが後の上高地へのアクセス向上につながり、観光や登山の発展の基礎を築きました。現在、上高地へ向かうルートの一部は、この時の道づくりに端を発しています。
つまり、上高地が“山岳リゾート”として知られるようになる最初の一歩は、実は絹産業と風穴の冷却技術から始まったということです。自然の力を利用し、人の知恵と努力で産業を発展させたこの土地の歴史は、上高地の美しい風景と同じくらい価値のある“人と自然の共作”といえるでしょう。
“釜トンネル”が開いた観光の玄関口

タモリさんが続いて訪れたのは、上高地の入口に位置する釜トンネル。今では観光バスや登山客が必ず通る「上高地の玄関口」として知られていますが、その誕生のきっかけは意外にも発電所の建設工事でした。
大正時代、上高地一帯の水源を利用して電力を供給するため、大正池発電所の建設計画が立ち上がります。その資材を運び入れるために掘られたのが、この釜トンネルでした。トンネルは岩盤をくり抜いて造られ、当時としては高度な土木技術を要する大工事。大正池の「大正」という名も、1915年(大正4年)に焼岳の噴火によってできた湖を記念してつけられたもので、自然と人の営みが交差する象徴的な場所といえます。
釜トンネルの横には、現在は使われていない旧釜トンネルも残されています。昭和の初めに完成したこの旧トンネルは、手掘りによる狭い通路で、当時の苦労を物語る貴重な遺構です。山肌に沿って延びるトンネルの中は暗く湿っており、歩くだけで当時の工夫と努力を感じ取ることができます。これらのトンネルができたことで、上高地への道のりは格段に安全で便利になり、人々が自然を楽しむために訪れるようになりました。
そして、昭和2年(1927年)、上高地の名を全国に広める出来事が起こります。大阪毎日新聞が主催した『日本八景』コンテストにおいて、上高地が渓谷部門の第1位に選ばれたのです。このコンテストは、日本全国の絶景を一般投票で選ぶ一大イベントで、当時の新聞紙上でも大きく報じられました。名だたる名勝を抑えて上高地が頂点に輝いたことは、多くの人に衝撃を与え、「日本にこんな美しい山の谷があったのか」と話題になりました。
この受賞をきっかけに、上高地は“自然美の象徴”として一躍有名になります。写真家や画家、登山家たちが次々と訪れ、穂高連峰を背景にした梓川や大正池の風景は、ポスターや観光絵はがきとして全国に広まりました。やがて上高地は、「誰もが一度は訪れたい場所」として憧れの地となり、現在の山岳リゾートとしての地位を確立していったのです。
帝国ホテルが示した“日本のもてなし”の原点

上高地がさらに脚光を浴びるようになったのは、昭和8年(1933年)のこと。日本を代表する山岳リゾートとしての象徴が誕生します。それが、今も多くの旅人に愛され続ける上高地帝国ホテルです。
このホテルの建設を発案したのは、当時の長野県知事・清水多嘉示(しみずたかし)。彼は、「外国人観光客を安心して迎え入れられる宿を上高地に」という強い思いから、帝国ホテル(東京)に協力を依頼しました。当時の上高地は、すでに『日本八景』の選出によって注目を集めていましたが、宿泊設備が整っておらず、外国からの登山家や学者たちを十分にもてなすことができなかったのです。そこで、日本の“おもてなし文化”を山岳地にも根づかせようと、この大規模なプロジェクトが始まりました。
設計を担当したのは、帝国ホテルの建築技師たち。木造の山小屋風建築をベースに、上高地の自然環境に溶け込むよう工夫が施されました。外観は赤い屋根と丸太の外壁が印象的で、周囲の森林と調和する優雅なデザイン。内装は、木のぬくもりを生かした落ち着いた空間で、当時のヨーロッパの山岳リゾートを思わせる雰囲気を漂わせていました。客室の窓からは、穂高連峰を一望でき、澄みきった梓川のせせらぎが静かに聞こえてきます。
ホテルの開業に合わせて、上高地までの道路も本格的に整備されました。これにより、松本市街から上高地まで馬車や自動車で訪れることが可能になり、アクセスは格段に改善されます。道路整備は観光の拡大だけでなく、地元住民にとっても物資の流通を支える大きな転機となりました。こうして、上高地は“自然と文明が共に息づく場所”としての姿を確立していきます。
上高地帝国ホテルはその後も時代に合わせて改修を重ねながら、創業当時の理念を守り続けています。春から秋にかけてのみ営業するこのホテルは、訪れる人々に「自然と調和した贅沢な時間」を提供し続けています。穂高の峰々を眺めながら味わう伝統のアップルパイやモーニングティーは、多くの旅行者の心に残る名物。世界中の登山家、写真家、文学者たちがこのホテルに宿泊し、上高地の美を作品や記録として残してきました。
今もなお、上高地帝国ホテルは“山岳リゾートの原点”としてその存在感を放ち続けています。自然と人の知恵が融合したその建物は、90年を経た今も変わらず、上高地の静寂と美しさをそっと見守りながら、多くの人々を温かく迎え入れています。
上高地の“自然と人”が生み出した奇跡
番組でタモリさんが歩いたのは、大正池や岳沢湿原(だけさわしつげん)といった、上高地を象徴する自然の舞台でした。大正池は、1915年(大正4年)に焼岳の噴火で梓川がせき止められて生まれた池で、今も噴火の痕跡を残しています。水面には枯れた木々の姿が静かに立ち並び、まるで時間が止まったかのような神秘的な風景をつくり出しています。晴れた日には、穂高連峰の峰々が鏡のように水面に映り込み、その幻想的な光景は訪れる人の心を奪います。
タモリさんはこの池のほとりを歩きながら、「自然がつくり、人が守った上高地の姿」を実感していました。上高地の地形は、何万年もの火山活動と水の流れが織りなした結果です。梓川が山の斜面から土砂を運び、その堆積が湿原をつくり出しました。現在の岳沢湿原はその代表例で、雪解け水がゆっくりと流れる静かな空間に、季節ごとの植物や野鳥が息づいています。湿原を歩く木道には、自然を壊さずに楽しむための工夫が詰まっています。
上高地が今のように美しい姿を保っているのは、自然の力だけではありません。地元の人々や研究者、そして環境省・上高地自然保護官事務所などの尽力によって、厳しい保全活動が行われています。昭和30年代には観光客の急増で環境破壊が問題となり、バスの乗り入れ制限や宿泊施設の管理が徹底されました。現在も、上高地は「特別名勝」および「特別天然記念物」に指定されており、日本有数の自然保護区として守られています。
上高地を訪れた人々が口にするのは、「空気の澄み方が違う」「歩くだけで心が落ち着く」といった感覚です。標高およそ1500メートルの冷涼な空気は、都市では味わえない透明感をもち、深呼吸するだけで体の芯まで清められるような気持ちにさせてくれます。タモリも、静かな笑顔で梓川の流れを見つめていました。水面を渡る風、遠くで鳴く鳥の声、そして山にこだまする足音――それらすべてが、長い年月をかけて築かれた「人と自然の共生」の証でした。
上高地は、ただの観光地ではなく、日本の自然と文化が調和して生きている場所。火山の力がつくり、川が形を整え、人が守り続けたこの風景には、自然に対する敬意と感謝が息づいています。タモリが見つめた穏やかな梓川の流れの中には、上高地が歩んできた数百年の物語が静かに流れていたのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・上高地はもともと木材の産地であり、信仰の場でもあった
・風穴による蚕卵保存と道路整備が観光開発の始まりとなった
・釜トンネルと帝国ホテルの登場で、上高地は山岳リゾートへと発展した
自然と文化、信仰と産業が交差する場所――それが上高地。タモリさんの旅は、単なる観光地紹介ではなく、日本人が自然とどう向き合ってきたかを静かに問いかける時間でもありました。
【ソース】
NHK『ブラタモリ 山岳リゾート上高地 なぜ人気観光地に?神秘の池&謎の風穴』(2025年10月11日放送)
https://www.nhk.jp/p/buratamori/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

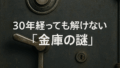
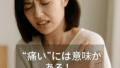
コメント