火山が生んだ信仰と絶景の物語〜タモリが歩く蔵王の秘密〜
「なぜ、昔の人は蔵王を目指したの?」
そんな疑問を抱いたことはありませんか?蔵王といえば、エメラルドグリーンに輝く御釜(おかま)やスキーの名所として知られていますが、実は江戸時代に“日本中の人々が憧れた聖なる山”でもありました。
今回の『ブラタモリ』(2025年10月25日放送)では、タモリさんが蔵王の山頂を訪ね、火山が生んだ信仰と自然の奇跡をめぐる旅に出ました。この記事では、番組で紹介された全エピソードをもとに、蔵王に秘められた歴史や文化、そして現代にもつながる魅力をわかりやすく解説します。
御釜が導いた「御山参り」ブームの始まり
旅の舞台は、宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰。古くから「火と氷の山」と呼ばれ、季節ごとにまったく異なる表情を見せます。その山頂に位置するのが、蔵王の象徴ともいえる御釜(おかま)です。
御釜はおよそ800年前、蔵王の噴火によって生まれた巨大な火口に雨水がたまってできた火口湖。水面は光の当たり方や季節によって色を変え、エメラルドグリーンから深いコバルトブルーまで、見る時間帯でまるで違う姿を見せます。この神秘的な色の変化から「五色沼」とも呼ばれ、訪れる人を魅了してきました。
1702年ごろに作成された仙台藩領絵図には、すでに御釜の姿が描かれており、当時からその存在が人々の関心を集めていたことがわかります。絵図には蔵王山周辺の地形や道、神社の位置までが細かく記されており、御釜が信仰や文化の中心にあったことを示しています。
江戸時代の人々にとって、御釜は単なる自然の湖ではなく、「天と地の境界」と信じられる聖なる場所でした。噴煙の立ち上る火口を“地獄”に見立て、その上に湛えられた水面を“天界”の象徴と考えたのです。御釜の水を口にすれば「穢れが祓われ、病が治る」とされ、実際に山頂まで登って水を汲む人も多くいました。
こうした信仰が広まり、やがて江戸中期には「御山参り」と呼ばれる蔵王信仰の登山が大ブームに。宮城県側の遠刈田温泉や山形県側の上ノ山温泉から登山道が整備され、庶民でも気軽に参加できる“祈りの旅”として定着していきました。蔵王御釜は、信仰と自然が一体となった特別な場所として、今も人々の心に深く刻まれています。
神と火山が共にある場所〜刈田嶺神社と蔵王大権現〜
タモリさんが次に訪れたのは、蔵王の山頂にそびえる蔵王刈田嶺神社 奥宮(ざおうかったねじんじゃ おくみや)。標高1,758メートルの刈田岳の頂にあり、晴れた日には御釜を見下ろす絶景の地です。現在の社殿は鉄筋コンクリート造りで、厳しい風雪や噴火の影響にも耐えられるように設計されていますが、その起源は江戸時代にまで遡ります。社殿の狛犬の台座には「安政四歳(1857年)」の刻印があり、長い歴史の証として今も残されています。
この神社を支えてきたのは、山形県側の出羽の人々と宮城県側の陸奥の人々。両側からの信仰が厚く、蔵王には当時すでに4つの登山口が整備されていました。宮城側からは遠刈田温泉を経て刈田岳を登るルート、山形側からは上ノ山温泉から熊野岳を目指すルートが人気でした。どちらの道を選んでも山頂で神に祈ることができる——そんな“開かれた聖地”であったことが、蔵王が多くの庶民に愛された理由のひとつです。
さらに、山形県側の熊野岳山頂にも神社があり、そこには熊野信仰と結びついた蔵王信仰の痕跡が見られます。蔵王という名の由来にもなった蔵王大権現(ざおうだいごんげん)は、修験道の中心的な存在で、もともとは奈良の金峯山寺(きんぷせんじ)で祀られてきた神仏です。山にこもり、厳しい修行を重ねて自然と一体となるという修験道の思想が、蔵王の地に息づいたのです。
蔵王大権現は、仏教の釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩が一体化した「権現」の姿で現れるとされ、怒りの表情で人々の煩悩を打ち砕き、正しい道へと導く存在とされています。この力強い信仰が東北にも広がり、蔵王は単なる登山の対象ではなく、「自然の力」と「信仰の力」が融合した特別な山として崇められるようになりました。
蔵王刈田嶺神社の境内から眺める御釜の姿は、まさにその象徴。火山が生んだ厳しくも美しい自然の中に、人々が神を見出し、祈りを捧げてきた歴史が静かに息づいています。
死と再生の象徴「賽の河原」を歩く
山頂を少し下った場所にある駒草平(こまくさだいら)では、タモリさんが荒涼とした大地をゆっくりと歩きました。風が強く、木々の少ないその光景は、まるで別世界のよう。火山活動によってできた岩肌が広がり、地表には草花がわずかに根を張るだけです。ここはかつて「あの世とこの世の境目」とされ、賽の河原(さいのかわら)と呼ばれていました。
江戸時代、蔵王を訪れる人々はこの地を通ることで、死後の世界を疑似体験しながら山頂を目指しました。賽の河原とは、子どもが亡くなった際にその魂が石を積むといわれる場所で、古くから「この世と彼岸のあわい」に位置づけられてきました。蔵王の駒草平もまさにその象徴であり、人々はここを越えることで一度“死”を経て、山頂の御釜の前で“生まれ変わる”と信じていたのです。
当時の登山は今のように観光ではなく、祈りそのもの。険しい山道を進み、岩場を登り、霧や風の中で一歩ずつ進むことが、心身を清める「修行」でした。御釜にたどり着いた瞬間、旅人は罪や穢れを洗い流されたような感覚を得たといいます。その体験は、現代でいう“心のリセット”に近いものでした。
駒草平の名の由来となったコマクサは、高山植物の中でも特に可憐な花として知られ、「高山の女王」と呼ばれています。厳しい環境の中でも美しく咲くその姿は、まるで試練を乗り越えた魂の象徴のよう。蔵王を訪れる人々は、その花を見て「苦しみのあとには必ず光がある」と感じたのかもしれません。
火山がつくり出したこの地形と、そこに宿る信仰の物語。駒草平は、自然と人の精神が交わる“再生の場所”として、今も多くの人々を静かに迎え入れています。
山と里をつなぐ「季節遷座」の儀式
最後にタモリさんが訪れたのは、蔵王山のふもとにある蔵王刈田嶺神社 里宮(ざおうかったねじんじゃ さとみや)です。緑豊かな森の中にたたずむこの神社は、山頂の奥宮とともに蔵王信仰を支えてきた重要な拠点。古くから「山の神を迎え、送り出す場所」として、地域の人々に親しまれてきました。
ここでは、長い年月にわたり「季節遷座(せつざんざ)」という伝統的な風習が行われています。春になると、冬のあいだ里宮に安置されていた御神体を担ぎ、行列が山頂の奥宮へと向かいます。道中では笛や太鼓が響き、白装束をまとった氏子たちが祈りを捧げながら山を登ります。そして秋、山に雪の気配が訪れるころには再び御神体を里宮へ戻す。この儀式は、自然とともに暮らす人々のリズムを象徴するものであり、信仰が季節の移ろいと密接に結びついていることを物語っています。
遷座の行列は、古くから地元の人々にとっての一大行事でした。参道には屋台が並び、子どもたちが神輿の後を追って駆ける姿も見られたといいます。里宮周辺の遠刈田温泉(とおがったおんせん)は、この遷座行事で多くの参拝者が訪れたことをきっかけに発展したとされ、今でも温泉街にはその名残が残っています。神事と温泉、そして旅が結びついた蔵王の文化は、まさに“信仰と暮らしが一体となった地域文化”といえます。
春に山へ神を送り、秋に再び里へ迎える——その繰り返しが、蔵王の自然と人々をゆるやかに結びつけてきました。蔵王刈田嶺神社 里宮と奥宮をつなぐこの伝統は、今も受け継がれ、訪れる人々に「自然とともに生きる」日本人の心を静かに伝えています。
こうして蔵王は、山岳信仰・火山・観光が三位一体となった“生きた文化遺産”として、現代にも脈々と息づいているのです。
まとめ:蔵王が今も人を惹きつける理由
この記事のポイントは以下の3つです。
・御釜の誕生が、江戸時代の「御山参り」ブームを生んだ
・蔵王大権現への信仰が、東北の人々を結びつけた
・死と再生の象徴「賽の河原」や「季節遷座」が文化として残った
蔵王は、単なる観光地ではなく、火山と人間の共生の象徴ともいえる場所です。御釜を見上げるとき、そこには800年前から続く祈りの記憶が確かに息づいています。
今度蔵王を訪れるときは、ただの絶景ではなく、“人と自然の信仰の物語”としてその景色を味わってみてください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


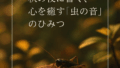
コメント