介護のリアルに迫る!現場から学ぶ“介護する・される”ためのヒント
「親の介護、これからどうすればいいの?」「介護の準備って、まだ早いと思っていた…」そんな不安や戸惑いを感じていませんか?
2025年10月20日放送のNHK総合『あさイチ』では、「介護のウラガワ」に密着。介護職の現場や、家族が知っておきたい実践的なヒントをたっぷり紹介しました。この記事では、番組で語られた“介護のリアル”をもとに、明日から役立つ情報をわかりやすく解説します。
介護の現場から見えるリアルな課題

番組ではまず、介護職の座談会が行われました。現場で働く介護スタッフが集まり、日々の業務や対応の工夫について率直に語り合いました。印象的だったのは、アルツハイマー型認知症の方への対応です。同じ話を何度も繰り返すことを、ただ「忘れている」と片づけるのではなく、短期記憶を確認し、進行具合を見極める大切なサインとして捉えるという話が紹介されました。これは、記憶がどのくらい保てているかを自然な会話の中で把握し、ケアに役立てる実践的な方法です。
また、介護の現場でよく注目されるのが、冷蔵庫の中身です。専門家によると、認知症が進行すると「同じ食品を何度も買ってしまう」「古いものを捨てられない」といった傾向が見られることが多いそうです。冷蔵庫を開けたとき、似たような惣菜や調味料が何個も並んでいたり、賞味期限が切れた食品がそのまま残っていたりする場合は、認知機能の変化を早めに気づくサインになるといいます。特に、夏場などは食中毒のリスクが高まるため、家族が一緒に確認することが重要です。
さらに、介護を受ける本人の前で不用意な発言をしないことも大切だと紹介されました。家族が疲れや不安を感じたとき、つい本人の前で「もう限界」などとこぼしてしまうことがありますが、それが本人の心に深い傷を残す場合があります。番組では、「気持ちのはけ口は本人ではなく、介護職やケアマネージャーに伝えることが大切」というメッセージが強調されていました。介護職はそのために存在しており、家族だけで抱え込まないようにすることが、より良いケアにつながるといいます。
スタジオでは、ジェーン・スーさんが自身の介護経験を語りました。「冷凍庫を開けたら、ものすごい数の保冷剤が入っていたんです」と話し、スタジオには共感の空気が広がりました。冷凍庫の中の保冷剤は、片付けられない心理状態の一例として多くの家庭でも見られる現象です。これに対し、黒沢かずこさんも「つい本人の前で傷つくようなことを言ってしまう」と率直に語り、自分の体験を重ね合わせていました。こうしたリアルな声が交わされることで、介護をする側・される側の両方に寄り添う番組となっていました。
“早めの備え”がカギとなるのが、要介護認定と住宅改修です。介護が必要になってから慌てて申請するのではなく、少しでも不安を感じた段階で動くことが大切だと番組では紹介されました。介護保険制度では、要介護認定の申請を行うことで、さまざまな支援が受けられるようになります。
特に注目されたのが、住宅改修費の支給制度です。介護保険を利用すると、段差の解消や手すりの取り付け、滑りにくい床材への変更、和式トイレを洋式トイレへ改修するなど、暮らしを安全に保つための改修が可能になります。費用は上限20万円まで給付される仕組みで、高齢の家族が安心して自宅で過ごすための強い味方です。
スタジオでは駒村多恵アナウンサーが、「電動ベッドや車いすなど、福祉用具のレンタルは早めに利用するのが安心につながる」とコメントしました。介護保険でレンタルできる福祉用具には、車いす・歩行器・スロープ・体位変換器・移動用リフトなどがあります。これらを上手に活用することで、介護する側・される側の双方の負担が軽減されます。
たとえば渋谷区では、介護度に応じて必要な用具を組み合わせてレンタルできる仕組みが整っています。利用を希望する場合は、地域包括支援センターやケアマネージャーに相談するのが基本です。こうした支援窓口では、申請方法や必要書類、費用負担の目安などを丁寧に教えてくれます。
また、住宅改修の際には、バリアフリー化に合わせて照明の明るさやドアの開閉方向を見直すケースも多いと紹介されました。ちょっとした環境の変化が転倒防止や介護負担の軽減につながるため、「早めに環境を整える」ことが、後々の安心につながると強調されていました。
ケアマネが見つからない!?深刻な人手不足

介護の現場では、ケアマネージャー(介護支援専門員)の不足が深刻化しています。介護保険を利用するには、ケアマネージャーが作成する「ケアプラン(介護サービス計画書)」が欠かせません。しかし現在、多くの地域で新規の受け入れが難しくなっています。番組で紹介された現場の声によると、「新規のケースは3年ほど受け入れできていない」という状況が実際に起きており、家族が相談してもすぐに担当者が見つからないケースが増えています。
行政機関や地域包括支援センターでは、特定のケアマネージャーを紹介することが制度上できません。そのため、相談に訪れた人には、登録事業所の一覧表を渡すだけという対応にとどまっています。結果として、家族が自分で事業所に連絡を取り、空き状況を確認しなければならないのが現実です。
番組では、こうした状況に対して「ツテを頼るのも大事」という現場の声が紹介されました。近所の介護経験者や地域の民生委員、病院の相談員などに情報を聞くことで、信頼できるケアマネージャーを見つけられることもあるそうです。もしケアマネが見つからない場合は、自費で介護サービスを利用したり、自治体や支援センターに相談しながら自分でケアプランを作成する方法もあります。介護保険制度では、本人や家族が「自己作成プラン」を提出すれば、一定条件のもとでサービスを受けることも可能です。
番組ではさらに、介護職全体の人手不足についても触れられました。今後、2026年には約240万人の介護職員が必要とされており、約25万人の人手不足が見込まれています。さらに2040年には約272万人の需要に対して57万人不足すると予測されています。高齢化が進む中で、介護職の確保は国レベルの課題となっており、現場の負担軽減や待遇改善が急務だとされています。
こうした現実を踏まえ、家族や地域が早めに相談・準備を始めることが、今後の介護を支える大切な第一歩になると強調されていました。
訪問介護ヘルパーの1日を密着取材

番組では、介護福祉士・千田愛香さんの訪問介護の1日に密着しました。朝から夕方までに4件の家庭を訪問し、排泄介助、口腔ケア、服薬準備、着替えの手伝い、デイサービスへの送り出し、ごみ捨てなどをおよそ30分ずつでこなしていきます。1件ごとの持ち時間は短いものの、その中で利用者の体調や気分を観察し、小さな変化を見逃さないことが重要だといいます。
現場では、身体のケアと同じくらい大切なのが会話です。千田さんは、利用者との何気ないやりとりを通じて、表情や声のトーン、話の内容からその日の体調や心の状態を確認していました。話しながらスマートフォンで記録をとり、事業所の責任者と情報を共有。こうしたリアルタイムのデジタル記録が、次の介護につながる重要な手がかりになっています。
また、番組では介護保険でできること・できないことについても紹介されました。
【頼めること】は、衣類のボタン付け、日常の掃除、簡単な調理など。生活に直結する支援が中心です。
一方、【頼めないこと】には、家具や家電の移動、床のワックスがけ、ペットの世話、留守番、嗜好品(お酒・タバコなど)の買い物、庭の草むしりなどが含まれます。介護保険では、日常生活に必要な範囲を超える作業は「対象外」となっており、必要な場合は介護保険外サービス(自費サービス)として対応している事業所もあります。
番組では、現場で深刻化しているカスタマーハラスメント(カスハラ)の問題にも触れました。調査によると、過去1年でケアマネージャーの37.7%がカスハラを経験。中でも、利用者本人から受けたケースが44.3%、家族やキーパーソンからのものが71.8%に上っています。介護職員に対して感情をぶつけたり、過度な要求をしたりするケースが少なくないといいます。
千田さんをはじめ介護職の多くは、「利用者の生活を支える“専門職”」という強い使命感を持って働いています。番組では、介護職を“お手伝い”ではなく対等なパートナーとして尊重する姿勢が求められると伝えていました。介護は誰もが関わる可能性のある分野であり、支える側と支えられる側が互いに理解し合うことの大切さを感じさせる内容でした。
特別養護老人ホームの今と最新技術

続いて番組では、千葉県旭市にある特別養護老人ホームを取材しました。取材先の施設は全室個室のユニット型で、入居者一人ひとりの生活リズムやプライバシーを尊重した造りになっています。各居室には見守りのためのインカムやセンサーが導入されており、職員が常に入居者の状態をリアルタイムで確認できる体制が整っていました。センサーは寝返りや呼吸の変化、起き上がりの動作まで感知でき、夜間の急変にも素早く対応できるようになっています。
以前は、朝の申し送りのために全職員が一度集まって情報共有を行っていましたが、現在はインカムの導入により、現場を離れずにその場で連絡を取り合えるようになりました。その結果、入居者に目を配る時間が増え、対応のスピードも向上しています。
また、食事管理の方法も進化しています。従来は紙の記録用紙に食事量や体調を手書きしていましたが、現在はタブレットでデータを入力・共有。これにより、職員全員がリアルタイムで食事状況や体調の変化を確認できるようになり、わずかな異変にも早く気づくことができるようになりました。たとえば、前日より食欲が落ちている、飲み込みが弱くなっているなど、細かな変化を記録から読み取ることができます。こうしたデジタル化による見守りが、安心と安全を両立させています。
入居を検討するタイミングについても、番組では明確に紹介されました。目安となるのは、認知症の進行によって外出中に道に迷うことが増えたとき、食事や排泄が自力で難しくなったとき、また痰の吸引や点滴など医療的なケアが必要になったときです。こうした状況になったら、家庭だけでの介護には限界があり、専門の施設での支援を検討する段階とされています。
特別養護老人ホームには大きく分けて「ユニット型」と「従来型」の2つのタイプがあります。ユニット型は個室が中心で家庭的な雰囲気を重視しており、入居者が落ち着いて過ごせるのが特徴です。一方、従来型は相部屋が多く、費用を抑えられる利点があります。費用は施設や介護度によって異なりますが、介護保険が適用されるため、自己負担はおおむね月10万円前後から20万円台の範囲になることが多いと紹介されました。
番組では、「費用や施設タイプの違いを理解し、早めに準備しておくことが大切」と強調。見学や相談を重ねながら、自分や家族に合った施設を選ぶことが安心につながると伝えられていました。
“マッチョ採用”が人手不足を救う!?
番組では、愛知県一宮市にある介護施設のユニークな取り組みが紹介されました。その名も「マッチョ採用」。筋トレやボディビルが好きな人を積極的に採用するという、全国的にも珍しい採用戦略です。
きっかけは、慢性的な介護人材不足でした。数年前までは年間の採用がわずか2人程度にとどまっていたこの施設が、発想を転換し「筋肉自慢の人材」をターゲットにした結果、現在では年間100人以上の採用に成功。体力に自信がある人たちが現場で活躍し、利用者からも「力強くて安心できる」「頼もしい」と高い評価を受けています。
この施設では、会社が新たにボディビル事業部を立ち上げました。職員が筋トレを続けやすいように、ジムの利用補助や大会参加支援など、筋トレに特化した福利厚生制度を整備。介護という仕事のイメージを「重労働」から「誇りと健康を保てる仕事」へと変えようとする挑戦が続いています。
現場の雰囲気も明るく、筋トレを通じて職員同士のコミュニケーションが活発になったことで、離職率も下がり、働きやすい環境づくりにもつながっているといいます。利用者との会話の中でも「今日も筋トレしたの?」と声をかけられることが増え、介護現場に新しい活力が生まれています。
番組では、福祉社会学の専門家である結城康博さんが登場し、「付加価値を作ることが人を集めるカギになる」と分析していました。介護職という枠を超えて、“自分の好きなことを生かせる職場”を作ることが、これからの人材確保のヒントになると語っていました。
世界一のセラピーロボットと最新介護テクノロジー
東京都世田谷区の特別養護老人ホームでは、最新のテクノロジーを活用した介護が注目を集めています。番組で紹介されたのは、入居者の心を癒やす存在として人気を集めている動物型セラピーロボット。見た目はアザラシの赤ちゃんのようで、ふわふわとした触り心地が特徴です。触り方や声のトーンに反応して、目を動かしたり鳴き声を出したりするなど、まるで本物の生き物のように寄り添ってくれます。その温かみのある反応が利用者の安心感につながり、介護現場でのコミュニケーションのきっかけにもなっているといいます。このロボットはギネス世界一のセラピーロボットとして認定された実績を持ち、国内外で高く評価されています。
同じ施設では、介護職員の腰痛を防ぐためのアシストスーツも導入されています。これは、装着者の動きを補助して腰への負担を軽減する装置で、重い体の移動や入浴介助などの際に力を分散させる仕組みです。介護職員の体を守ることが、結果的に質の高いケアの継続につながっていると紹介されました。
さらに、最新の介護用具展示会では、未来を感じさせるアイテムが次々と発表されていました。中でも話題になったのが、利用者が座ったままでメイクが完了する全自動メイクロボット。メイクを通じて「自分らしさ」を取り戻すことを目的としており、高齢者の心のケアにもつながると注目を集めています。
スタジオでは、ジェーン・スーさんが「自分が介護されるときは、ウェアラブル端末で全部管理してほしい」と語りました。健康状態やスケジュール、服薬の記録などを自動で管理できるようになれば、介護する側の負担も減り、より効率的で快適な介護が実現できるという考えです。番組では、こうしたデジタル技術の進化が介護の未来を大きく変えていく可能性を感じさせるシーンが数多く紹介されていました。
介護を支える“備え”の知恵
番組の終盤では、現場の介護職員から寄せられた「これだけはやっておくといい備え」として、日常の体調変化を記録する方法が紹介されました。特におすすめされたのが、「体調や変化を時系列で記録するノート」です。日々の食事量、睡眠、服薬、気分の変化などを簡単にメモしておくだけでも、病気や認知機能の変化を早期に察知できるといいます。体調の“波”を見える化することで、病院や介護職員に正確に伝えられるのが大きな利点です。
スタジオでは駒村多恵アナウンサーも、「私も親の健康状態をノートに記録している」と実践例を紹介しました。いつもと少し違う食欲の低下や歩行の乱れなど、小さな変化こそが大きなサインになると語り、視聴者にも記録の大切さを呼びかけていました。介護の現場でも、この“健康記録ノート”を共有することで、複数の介護スタッフが同じ情報を把握でき、より質の高いケアにつながるといいます。
また、親の経済状況や資産の所在を把握しておくことも、将来的な介護費用に備える上で欠かせないポイントとして取り上げられました。介護が始まってから慌てるのではなく、どのくらいの資金があるのか、どの口座に預貯金があるのか、保険や年金の受け取り先がどこかなどを、家族で共有しておくことが重要だと強調されました。これらを整理しておけば、介護サービスの選択や施設入居の手続きもスムーズに進められます。
番組では、「備えは“いつか”ではなく“いま”から」という言葉が印象的に伝えられ、介護を“支える準備”の大切さを改めて感じさせる内容となっていました。
いまオシ!LIVEでは“室内アワビ養殖”も紹介
『いまオシ!LIVE』のコーナーでは、千葉県いすみ市で行われている「室内アワビ養殖」の取り組みが紹介されました。自然の海に頼らず、室内水槽でアワビを育てるという試みは、環境変化に強く、安定した生産を可能にします。
地域に根ざしたこのプロジェクトには、“支える仕組みをつくる”という点で介護との共通点もあります。現場の人々が新しい技術と知恵を融合させて挑戦する姿は、介護の未来を考える上でも示唆に富んでいます。
みんな!ゴハンだよ『カリッもちっ!豆腐めんたいチヂミ』
料理コーナー『みんな!ゴハンだよ』では、料理研究家・ほりえさわこさんが『カリッもちっ!豆腐めんたいチヂミ』を紹介。豆腐のふんわり感と明太子のうまみが絶妙に合わさった一品で、外はカリッ、中はもちもちの食感が楽しめます。
介護食としても取り入れやすく、やわらかい食感と高たんぱくな豆腐は、栄養面でもおすすめ。家庭でも簡単に作れるレシピとして、幅広い世代に人気を集めそうです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・介護の備えは「早め」が鉄則。住宅改修・用具レンタルは地域支援センターへ相談を。
・ケアマネ不足など現場の課題は深刻。ツテや自治体を上手に頼る工夫を。
・最新技術やロボット導入で介護の未来は進化中。心のケアと体のケアの両立が鍵。
介護は“特別な誰かのため”だけではなく、いずれ自分にも関わるテーマです。家族の笑顔を守るために、今からできる一歩を踏み出しましょう。
出典:NHK総合『あさイチ』公式サイト(https://www.nhk.jp/p/asaichi/)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

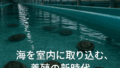

コメント