わたしの台所物語と睡眠ツーリズム・釜石のウニ・にらチャーハンも登場!
2025年5月28日放送のNHK『あさイチ』は、人生の軌跡を描く人気シリーズ「わたしの台所物語」の特集に加え、話題の「睡眠ツーリズム」、岩手・釜石の“うにしゃぶ”、スタミナ満点「にんにくにらチャーハン」のレシピ紹介など、暮らしと食、旅をテーマにした盛りだくさんの内容でした。出演は博多華丸・大吉さん、鈴木奈穂子アナウンサーに加え、ゲストは藤井隆さんと浅田美代子さん。すべてのコーナーが「今の暮らし」に寄り添った温かみのある構成となっていました。
福岡県・40代女性の台所——嫌いな料理に全力投球する日々
福岡県に暮らす2児の母・吉田由香さん(40代)の台所は、忙しい日々の中で「工夫」と「思い」が詰まった場所です。由香さんは建築士として働きながら、単身赴任中の夫を支え、家事と育児を両立させています。仕事から帰ってすぐに夕食づくりに取りかかるのが毎日の流れで、時間のない中でもワンプレート料理を約15分で完成させる工夫を欠かしません。
・調理時間を短縮するため、献立はあらかじめ考えておく
・一つの皿に主菜・副菜・ごはんをバランスよく盛りつけて洗い物も減らす
・夕食準備に迷いが出ないよう、材料は冷凍保存や下ごしらえ済みのものを活用
実は由香さん自身、料理が大の苦手。それでも手作りにこだわるのは、市販のお惣菜や冷凍食品を子どもに与えることに、どうしても罪悪感があるからです。「料理を作りたい」という気持ちではなく、「手間をかけることでしか自分の気持ちを伝えられない」と考えて、日々キッチンに立ち続けています。
・週末には夫が帰宅し、一緒に作り置きの準備を担当
・平日の台所は最小限の動きでまわせるよう、配置や段取りも工夫
・台所の一角には、母親がかつて使っていた「みそ溶き」が今も置かれている
このみそ溶きは、普段あまり料理をしてくれなかった母親の思い出の品でもあります。由香さんの母は、両親の離婚後に仕事に追われ、やがて家に帰らなくなってしまいました。その中で、由香さんは弟と2人、市販のお弁当で空腹をしのぐ日々を過ごしてきました。
・夕食が用意されているという「安心感」がなかった
・家族そろって食べる時間も少なく、寂しさが募っていた
・その経験から、「子どもたちにだけはちゃんと食卓を用意したい」と感じるようになった
結婚後、専業主婦になったこともありましたが、料理への苦手意識が強く、ストレスがたまる一方だったため、再び仕事を始めました。とはいえ、働くことで生活は一層多忙に。だからこそ、「苦手なことだからこそ、できる範囲で最善を尽くしたい」との思いが、今のスタイルにつながっています。
・冷蔵庫には常に常備菜が3〜4品ストックされている
・使いやすい調味料やカット済み野菜で、短時間調理を徹底
・レシピ本や動画を見るのではなく、「自分のやり方」で乗り越えている
料理が好きかどうかではなく、「料理を通して誰かを想う気持ち」こそが、台所に立つ原動力になっているのが、由香さんの物語の根底にあります。効率化された動線、苦手意識との付き合い方、そして家族への思い。そのすべてが、彼女の台所に詰まっています。仕事・子育て・家事を一手に担いながらも、自分らしく続ける日々の工夫こそが、誰かの共感を呼ぶ“等身大の暮らし”なのだと感じさせてくれる台所でした。
東京都・60代男性の台所——20年越しのオムレツと娘の記憶
東京都に暮らす大学講師・高原純一さん(60代)の台所には、20年という時間をかけて向き合ってきた父と娘の物語が詰まっています。今は再婚し、現在の妻とふたりで台所に立ち、夕食の支度を一緒に行いながら、鍋を火にかけて煮込む間に乾杯するという小さな楽しみを日課としています。しかし、そこに至るまでには、長い葛藤と記憶の積み重ねがありました。
・純一さんは、がんで妻を亡くし、当時9歳だった娘を男手一つで育てることになった
・仕事は長時間勤務が当たり前の時代で、講義・会議・研究・クライアント対応に追われる日々
・それでも娘の食事は毎日自分で用意し、食べさせてからまた仕事に向かう生活が続いた
電車の中で静かに過ごす数分間が唯一の休息だったと話すほど、日々は張りつめた時間の連続でした。そんな生活の中で、料理は「やらねばならない義務」であり、台所は苦しさや不安と向き合う場所でしかなかったといいます。
・自分の作る料理が娘にとって十分だったのか、自信が持てなかった
・他の家庭のように、手の込んだ料理や温かい団らんを提供できなかったことに、強い罪悪感を抱き続けていた
・「あのとき、もっと違うことができたのでは」と、20年が経っても思い返してしまう
しかし、娘が成長し、あるとき語った「あの頃はすごく楽しかった」という一言が、純一さんの心を大きく動かします。それは、父としての自分を見つめ直すきっかけになり、長く閉じ込めていた記憶がゆっくりとほどけていく瞬間でもありました。
・娘との思い出で特に印象深かったのは、週末に一緒にスーパーへ買い物に行ったこと
・家でよく作っていたのが、小林カツ代さんのレシピで作るオムレツ
・そのレシピ本はいまでも本棚に残っていて、最近になって再びそのオムレツを作れるようになった
オムレツはただの料理ではなく、父と娘をつなぐ象徴のような存在。その一皿には、時間を超えて積み重ねられた思いと、やっと向き合えるようになった気持ちが込められています。料理をすることが辛かった過去の自分と、楽しさを思い出として語ってくれた娘の存在が重なり、純一さんの台所は新しい意味を持ちはじめました。
・コンパクトなキッチンには、動線を考え抜いた工夫が詰まっている
・妻と一緒に調理するための段取りや器具の配置が、長年の経験から自然と整っている
・「食べることは生きること」という言葉が、そのまま日常の風景になっている
台所が苦痛だった日々から、今はふたりで立つ喜びの空間へと変わった純一さんの物語は、家族の形が変わっても、料理を通して絆は育まれるということを教えてくれます。時間をかけてしか得られない安心や、記憶が再び彩りを取り戻す瞬間が、台所の中に静かに息づいています。
石川県・珠洲市・80代女性の台所——被災からの再出発と手仕事の力
石川県珠洲市に暮らす圓堂メチ子さん(80代)の台所は、震災による喪失と再生の記録でもあります。2024年に発生した能登半島地震で、自宅がある山奥の集落が被災。これまで60年暮らしてきた思い出の家が大きな被害を受け、生活は一変しました。
・当初は台所に立つ気力さえも失い、料理をすることができなかった
・避難先の娘夫婦の家に身を寄せ、支えられる日々が続いた
・やがて希望していた仮設住宅への入居が実現し、2025年1月に新たな台所を持つことができた
この新しい台所ができたことで、メチ子さんの暮らしにも再び「動き」が戻り始めます。朝は近くの体育館に近隣の方々が集まり、井戸端会議を楽しむように。夜には親戚を招いての食事会を開くまでに元気を取り戻しました。人と食を通して再びつながりを持ち、笑顔の時間が戻ってきたのです。
・仮設住宅の庭先にはナス、里芋、じゃがいもを植え、少しずつ畑仕事を再開
・料理に使うための笹の葉を、自ら歩いて採りに行くようになった
・ひとりで始めた折り紙が仮設のブームとなり、地域との交流を生み出している
もともとメチ子さんは、畑で採れた山菜や野菜を使って人をもてなすのが得意でした。長年の夢だった「農家民泊」の看板は、被災した家が解体される際、唯一手元に残すことを選んだ大切な道具です。その看板には、自分の手でもう一度人をもてなしたいという強い思いが込められていました。
・家の解体は2025年2月に行われ、夢の場所は失われた
・しかし看板だけは今も手元に置かれ、再出発のシンボルとなっている
・仮設住宅の暮らしの中でも、生活のリズムや工夫を大切にしている
台所は、生活の再建そのものでもあります。エッセイストの大平一枝さんが語ったように、「台所には、その人の段取りやクセ、記憶が詰まっている」。メチ子さんの台所にも、手の動きで呼び起こされる記憶や、自分らしく生きる力がよみがえっているように感じられます。
手を動かし、土を耕し、料理を振る舞い、人とつながる——。それは被災という深い喪失を経たあとでも、年齢に関係なく再び始めることができる営みです。暮らしを整えること、自分のペースで誰かと関わること、それが生活を支える芯になっていくのだと、メチ子さんの台所は教えてくれます。
仮設の中で始まった第二の台所は、単なる生活の場を超えて、「生きていく力」を育む場所として静かに灯り続けています。
トレンドCatch!コレキテル「スリープツーリズム」特集——“眠るために旅する”新しい休息のかたち
今回の『あさイチ』では、「トレンドCatch!コレキテル」のコーナーで、注目のスリープツーリズム(睡眠ツーリズム)が取り上げられました。季節の変わり目で寝苦しくなる時期、睡眠に悩む人が増える中で、“眠ること”を目的とした旅行が静かに広がりを見せています。
東京都内では、すでにさまざまなホテルが睡眠に特化したサービスを展開しています。
・東京・浜松町のホテルでは、宿泊費のみで睡眠測定ができる
- 測定内容:心拍数、呼吸、いびき、寝返りなど
- データは専用のマットで自動的に収集
- 専門機関と提携して、自分の睡眠状態を「見える化」できるサービス
・東京・池袋のビジネスホテルでは、10種類以上の「眠るための仕掛け」が用意されている
- アロマや音響、照明の調整、遮光性の高いカーテンなど
- 寝る前のストレッチ動画や、リラクゼーションドリンクの提供もあり
- 忙しい都会人のために、短期間でもしっかりとした「質の高い睡眠」が得られる工夫がされている
こうした睡眠への意識の高まりは、ビジネス市場にも大きな影響を与えています。2021年に約1200億円だった睡眠関連市場は、2024年には1900億円にまで拡大。その中心にあるのが、このスリープツーリズムという新しいライフスタイルです。
特に注目されたのが、愛知県・幸田町にある旅館の快眠プランです。
・宿泊場所は、露天風呂付きの離れ
・入浴は2回に分けて行うスタイル
- 1回目:5~6分程度の軽めの入浴でリラックス
- 2回目:就寝前に15分ほど、軽く汗ばむ程度につかることで深部体温を下げ、眠気を促進
・部屋の照明や音、香りなども、深い眠りに誘う設計
この宿では、非日常の空間の中で「眠ること」そのものを旅の目的として提供しています。単なる観光や温泉旅行とは違い、休息を主目的とする新しいスタイルです。
番組内では、スリープツーリズムを研究する平野亜矢さんが登場。旅は本来「非日常」を味わうものだが、現代では日常が忙しすぎて、「休むこと」自体が特別な体験になっていると指摘しました。そのうえで、「しっかり眠る」という行為は、単なる体の回復ではなく、気合を入れて自分を整える行動の一つでもあると話されました。
睡眠の質を高めることで、心身ともにリセットされ、次の日の行動に前向きな変化が生まれる。スリープツーリズムは、これからの時代に必要な“本当の休息”を見直すためのきっかけになるかもしれません。旅先でぐっすり眠ることが、新たな「贅沢」や「ごほうび」になっていく、そんな流れが広がり始めています。
出演者情報
・【ゲスト】浅田美代子さん、藤井隆さん
・【講師】料理研究家のMakoさん
・【キャスター】博多華丸さん・博多大吉さん、鈴木奈穂子さん
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

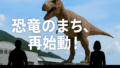

コメント