許せない!ネットのひぼう中傷 被害にあったとき何ができるのか
2025年4月14日放送のNHK『あさイチ』では、「許せない!ネットのひぼう中傷」と題して、ネット上で広がる誹謗中傷の実態と、それに巻き込まれた被害者の声、さらには対策や相談先について特集が組まれました。一般の人々も突然被害者となるリスクがあるいま、知っておくべき現実が詰まった40分間でした。本記事では番組で紹介された内容をもれなく整理し、被害を防ぐためにできることを詳しく紹介します。
堀ちえみさんが語った壮絶な誹謗中傷の実態
堀ちえみさんがネット上で誹謗中傷を受けるようになったのは、2019年にステージ4の舌がんを公表したのがきっかけでした。手術では舌の6割を切除するという大きな決断を乗り越え、長いリハビリを経て徐々に回復。再びテレビにも出演するようになりましたが、その復帰を歓迎する声と同時に、中傷の声が一段と激しくなっていきました。
・ブログのコメント欄には「病気はウソ」「同情を引きたいだけ」といった根拠のない言葉が並びました。
・匿名掲示板では、見た目や声の変化をあげつらう書き込みや、「家族も共犯だ」などといった家族に向けた攻撃まで広がり、堀さん自身が「限界だった」と語るほど精神的に追い詰められました。
・誹謗中傷の多くがネットニュースのコメント欄や掲示板で行われており、日常的に目に入る場所で繰り返される悪意は、心の回復を妨げる大きな障害になっていたのです。
堀さんは夫とともに、弁護士に相談しながら冷静に対応を進めました。
・まず行ったのが、中傷の証拠を1件ずつ丁寧に収集すること。SNSの投稿やコメントを保存し、投稿日時や内容を記録に残しました。
・弁護士を通じて、発信者情報開示請求という手続きを実施。これは裁判所を通じて、誰が投稿したのかを突き止めるための手続きです。
・驚いたのは、約1万6000件に及ぶ中傷の投稿の大半がわずか3人によるものだったという事実でした。
この3人について、堀さんたちはそれぞれ異なる対応を取りました。
・1人とは示談で和解。
・1人とは民事訴訟を継続中。
・そしてもう1人は、執拗にブログや掲示板へ中傷を書き込み続けていたため、警察に相談の上で逮捕に至ったのです。
堀さんは、被害を受けて苦しんでいる人に対して「たたかれている自分を責めないで」と語っています。自分が悪いからではなく、悪意を向けられているだけであると理解し、我慢せず証拠を残し、信頼できる人や専門機関に相談することの大切さを伝えていました。
この一連の対応は、誹謗中傷という見えにくい暴力にどう立ち向かうかの手本でもあります。被害を見過ごさず、証拠を残すことで動かせる現実があるということを、この事例が強く教えてくれます。
推し活がきっかけで誹謗中傷の被害に
番組では、40代の一般女性が経験した推し活による誹謗中傷被害が紹介されました。自分の好きなアイドルや俳優を応援する投稿をSNSに上げたことが発端となり、突然知らない人たちから人格を否定するようなコメントを受けるようになったのです。
・推しに関連する投稿に対し、「気持ち悪い」「目障り」「黙ってろ」などの言葉が繰り返され、投稿を消しても攻撃は止まらなかったといいます。
・一部のコメントは、本人の容姿や生活、家族までを対象にし、言われた本人が傷つくような表現が多く含まれていました。
・こうした誹謗中傷は、表に見える投稿だけでなくDM(ダイレクトメッセージ)でも届くようになり、精神的に追い詰められていったと番組で伝えられました。
また、ゲストとして出演していた中川翔子さんも、自身の経験をふまえた話をしていました。中川さんがSNSを始めたのは20年ほど前。まだネットリテラシーが浸透しておらず、いわば「無法地帯」だった時代でした。
・当時は中傷されても、それに反論したら「反論するほうが悪い」とされるような空気があり、何を言われても耐えるしかないような状況だったそうです。
・その中でも芸能人として発信を続けてきた中川さんの言葉は、現在ネットで悩む人にとっても共感と勇気を与えるものでした。
さらに、こっちのけんとさんは、自身が過去に双極性障害とうつ病を公表した際に受けた誹謗中傷について語りました。
・病気を正直に発信したにもかかわらず、「親の教育が悪い」「嘘をついている」「甘えているだけ」といった無理解で攻撃的なコメントが相次いだといいます。
・こうした書き込みは、一見すると何気ない一言でも、本人の心に深く突き刺さるダメージとなることが多いのです。
・特に、メンタルヘルスに課題を抱えている人にとって、ネット上の言葉の暴力は命に関わる重大な問題になりかねません。
このように、誰かを応援する気持ちや、自分をさらけ出す勇気が、時として誹謗中傷の標的になることがあるという現実が、番組では丁寧に取り上げられていました。応援や発信をする側も、受け取る側も、ネット上でのふるまいが現実の誰かの心に影響を与えているという意識を持つことが大切です。
誹謗中傷をする人の心理と特徴
番組の中では、ネット上で誹謗中傷をする人たちの心の奥にある心理や動機について、専門家の解説が紹介されました。言葉の暴力はなぜ起きるのか、誰がどんな気持ちでそれをしているのかを知ることは、対策を考える上でもとても大切です。
・まず山口真一准教授は、誹謗中傷の背景には「自分が正しいと思い込んでいる個人的な正義感」があると話しました。これは、相手の考えや行動が間違っていると信じ、正すことが自分の“使命”だと感じてしまう心理です。
・たとえば、ある投稿が気に入らないと、「これは世の中のために批判しないといけない」と考え、結果的に攻撃的な言葉を使ってしまうという行動に出る人がいます。
・この正義感は、本人にとっては“正当な行為”ですが、受け取る側には人格を否定されるような強い痛みを与えてしまうことがあります。
さらに清水陽平弁護士は、誹謗中傷をした人に通知書を送っても「自分は意見を言っただけで悪いことをしていない」と返されることが多いと説明していました。
・これは、ネット上のやりとりが顔が見えない空間で行われるため、相手を“人”として認識しにくくなることが原因とされています。
・リアルな場では言わないようなきつい言葉や罵倒も、相手の反応や感情が見えないことで、つい書いてしまうという現象が起きてしまいます。
・つまり、「見えない相手」にはどれだけ傷つけるかの想像力が働かず、歯止めが効かなくなるのです。
番組では、「批判」と「誹謗中傷」の違いについても詳しく説明がありました。
・批判とは、ある人の発言や行動に対して違う意見を述べたり、問題点を冷静に指摘することです。建設的であれば、社会にとっても有意義な意見のやりとりになります。
・一方で誹謗中傷は、相手の人格そのものを否定したり、見た目を侮辱したり、存在価値を否定するような内容を含むものです。そこには議論の余地がなく、ただ相手を傷つけることが目的となっています。
・たとえば「この発言には反対です」と言うのは批判ですが、「こんな人間は消えろ」「ブス」「気持ち悪い」といった言葉は誹謗中傷に該当します。
・投稿ボタンを押す前に“一呼吸おいて見直す”ことが非常に大切だと、スタジオで繰り返し強調されていました。
インターネットは便利で自由な場である反面、その自由には責任が伴うという意識が欠かせません。相手が見えないからこそ、誰かの気持ちを思いやる想像力が求められています。今の時代、すべての人が「発信者」であるからこそ、この心理的なメカニズムを理解し、自分も無意識のうちに加害者になっていないかを振り返ることが求められています。
加害者はごく少数?驚きの事実も判明
番組では、ネット誹謗中傷の背景にある加害者の数に関する意外な事実も明かされました。誹謗中傷が大量に見える場合でも、実際にはほんの一握りの人が何度も投稿しているだけというケースが少なくないのです。
・あるサイエンスライターが中傷被害を受けて訴訟に踏み切った事例では、被告が200以上ものアカウントを使い分けて、一人で執拗に攻撃を続けていたことが明らかになりました。見た目には多数の人が書いているように見えても、実は一人の加害者が複数の顔を使って攻撃していたという構造です。
・さらに、ネットユーザー全体を分析すると、誹謗中傷を実際に投稿しているのは約0.00025%の人たちにすぎないという研究結果も紹介されました。これはおよそ40万人に1人という数字で、極めて少数の人間が目立つ投稿を繰り返していることが分かります。
・こうした“見えない構造”が、SNSや掲示板の中で起きている炎上や中傷の印象を必要以上に大きく感じさせてしまう原因にもなっています。
・つまり、「ネットが荒れている」「多くの人から叩かれている」と思っていたとしても、実際には少数の人物の繰り返し投稿が大半を占めている可能性があるのです。
このような実態を知ることで、誹謗中傷の被害に遭ったときに「社会全体から責められている」と感じる必要はないという心の余白を持つことができます。現実には、加害者はごく少数。その一部の異常な行動が過剰に目立っているだけであるという事実は、被害者にとって大きな救いにもなります。
また、こうした少数の加害者を特定するには、証拠の保存と冷静な対応が何より重要です。匿名性の高いインターネット空間では、ひとつひとつの投稿の背後に誰がいるのかを見極めるために、発信者情報開示請求などの法的手段が必要になる場合があります。そうした対応を的確に進めることが、被害の解決につながる第一歩になります。
被害にあったらどうする?相談窓口と対応策
番組では、ネット上で誹謗中傷の被害に遭ったときに頼れる具体的な相談窓口と対応方法についても詳しく紹介されました。ひとりで抱え込まず、適切な機関や専門家に早めに相談することが重要です。
・まず紹介されたのが、セーファーインターネット協会(SIA)です。この団体は、被害者に代わってSNS運営会社やサイト管理者に投稿の削除依頼を行う活動を行っています。
・昨年度の実績では、送信した削除依頼のうち約半数が実際に削除に至ったとのことで、民間団体でありながら実効性のある対応をしてくれる存在として信頼されています。
・削除依頼は本人が出すこともできますが、専門知識をもった団体や弁護士に相談することで、より確実かつ速やかな対応が期待できるとされています。
さらに、誹謗中傷の内容がエスカレートして脅迫や個人情報の晒しなど命や安全に関わる危険を感じる場合は、次のような窓口にも相談が可能です。
・最寄りの警察署や、都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口では、犯罪性があると判断されれば捜査が行われることもあります。
・心が不安定になったり、精神的に追い詰められてしまった場合には、厚生労働省の「まもろうよこころ」といったメンタルヘルスの相談窓口が用意されています。
・さらに、損害賠償を求めたいと考えたときは、法テラスや弁護士に相談することで、法的手続きを取る選択肢もあります。
また、番組では発信者情報開示請求を行う際の注意点についても触れられました。
・多くの人がやりがちなミスが、誹謗中傷の投稿を「スクリーンショットだけで保存してしまう」ことです。
・しかし、裁判で証拠として扱う場合には、投稿画面をPDF形式などで保存し、URLや投稿日時、アカウント情報が明確にわかるようにする必要があると専門家は説明していました。
・証拠が不十分だと、開示請求が認められなかったり、手続きに時間がかかる可能性があります。
早期に相談し、正確な証拠をそろえて行動を起こすことが、被害の拡大を防ぐ第一歩です。誹謗中傷に悩んでいる人は、勇気を持って専門窓口にアクセスし、自分の心と権利を守るための行動を始めましょう。ネットの世界でも、「だれかに頼っていい」仕組みは確実に整ってきているのです。
放送を通して伝えたかったこと
誹謗中傷の加害者は必ずしも悪意を自覚していない場合が多く、また、被害者はひとりで抱え込んでしまう傾向があります。番組では、「たたかれている自分を責めないで」という堀ちえみさんの言葉が紹介され、視聴者からは「投稿を玄関に貼れるかを考えてから投稿すべき」という高校教師の教えを今も大切にしているというお便りも届きました。
誹謗中傷に立ち向かうには、まず知ることから始めることが大切です。被害を防ぐために、冷静な対応と正しい知識を持ち、自分や他人の尊厳を守る行動を心がけましょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

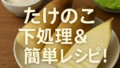
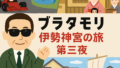
コメント