伊勢神宮への旅・第三夜|徳川御三家の巨大港と伊勢参り土産の誕生秘話!鈴鹿サーキットの意外な歴史にも注目
2025年4月19日放送の『ブラタモリ』は、シリーズ「伊勢神宮への旅」の第三夜。今回は三重県鈴鹿市が舞台となり、現代と江戸時代の風景が交差する興味深い旅が展開されました。旅のルートは、F1で有名な鈴鹿サーキットを出発点に、白子宿の巨大港の歴史的役割、そして江戸の人々を魅了した伊勢土産の職人技、さらには津の宿場で交わる信仰の道へと続きます。伊勢路の魅力を歴史・地理・文化の面からじっくりと掘り下げた構成で、知的好奇心を満たしてくれる放送となりました。
サーキットの中に残る“消せない池”と、米どころ鈴鹿の深い関係

旅のはじまりは、世界的に有名な鈴鹿サーキット。そのコース内にぽつんと残された小さな池が、今回の大きなポイントです。実はこの池、鈴鹿サーキットが建設される以前から存在していたもので、今でも周辺の農地へ水を供給するために現役で活用されているのです。
鈴鹿は古くから伊勢平野の豊かな水に恵まれた全国屈指の米どころ。江戸時代も例外ではなく、伊勢街道沿いの宿場では、収穫された良質なもち米を使って作られた「名物餅」が旅人たちに親しまれていました。白餅、草餅、あんこ餅などその種類は豊富で、それぞれの宿場に独自の味がありました。
また、鈴鹿といえばもう一つの名産が伊勢茶です。香り高くてまろやかな味わいが特徴で、餅と伊勢茶の組み合わせは旅の疲れを癒す定番セットとして愛されてきました。このように、サーキットの中の池という“現代の風景”が、実は江戸時代の食文化とつながっているという意外性は、まさにブラタモリらしい発見でした。
白子宿の巨大港は、徳川御三家・紀州藩の国家的プロジェクトだった

次に訪れたのは、伊勢路の宿場町として栄えた白子宿(しろこじゅく)。ここに江戸時代初期、徳川御三家のひとつ紀州藩が築いた巨大港「白子港」の痕跡が残されています。この港は単なる漁業用ではなく、藩の物資輸送と海上防衛の両面に対応した戦略拠点として設計されたものでした。
港の大きな特徴は、川の水を引き込んで造られた内港式の構造にあります。複数の小さな川とつながっており、小舟で荷物を運び、大きな船へ積み替えることで効率的な物流が可能になっていました。川と港をつなぐこの水路網は、まるで“江戸時代のインフラ整備”のようなスケールを持っていたことがわかります。
この白子港の存在により、紀州藩の領地である和歌山県と江戸を結ぶ重要な海上ルートが確保され、紀州徳川家の政治的影響力を伊勢湾全域に広げることができました。現在、港そのものは埋め立てや宅地化によってその姿を消していますが、地名や古地図、微妙な高低差などに往時の構造を垣間見ることができます。
伊勢型紙の技術が“冨久絵土産”を生んだ背景とは?

白子港の整備によってもたらされたもう一つの影響が、伊勢型紙の技術がこの地に流れ込んだことです。伊勢型紙とは、染色用の精密な型紙で、全国の着物文化を支えた重要な工芸技術。その技術が白子に伝わり、ここから「冨久絵(ふくえ)」という土産文化が誕生しました。
冨久絵は、型紙を活用して作られた縁起物の版画や細工物で、伊勢参りの記念品として爆発的な人気を博しました。冨久(ふく)には「幸福が久しく続くように」という願いが込められており、旅の無事や家族の健康を祈って持ち帰る人が多かったといいます。
細部まで丁寧に彫られた模様、鮮やかな色合い、そして手作りならではの温もり。江戸の人々はこうした品を大切にし、自宅の床の間や神棚に飾っていたそうです。現代でも一部の工房で復元や制作が行われており、土産の中に込められた「祈りの形」を伝え続けています。
津で交差する“道”が示す信仰の広がり

さらにタモリさん一行が訪れたのは、伊勢路の中継地・津市(つし)。この地は、東海道を経由する旅人と、京都・奈良方面から伊勢を目指す人々が合流するポイントとして栄えました。江戸と京の流れが交わるこの場所には、茶屋、旅籠、道標が数多く並び、参拝前の準備を整える場所として利用されてきました。
また、津には今も当時の名残を感じる場所が点在しています。石造りの道標や、神社に残された古地図、町家の造りなど、目立たないけれど確かに“旅の記憶”を今に伝える遺構が残っているのです。
このような町を訪れることで、単に“目的地”を目指す旅ではなく、“旅そのものに意味がある”という伊勢参りの精神が見えてきます。
まとめ
『ブラタモリ』伊勢神宮への旅・第三夜は、現在と過去の鈴鹿が交差する濃密な30分間でした。サーキットの池から始まり、白子港の歴史、型紙文化、伊勢土産の誕生、そして津で交差する信仰の道筋まで、一つの地域に複数の時代と文化が重層的に存在していることがよく伝わる回でした。
水・道・港・技術・祈り──それぞれの要素がつながり、伊勢路という一本の道が形づくられていたことを、タモリさんの視点であらためて確認することができました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

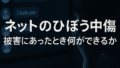
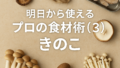
コメント