津城と松阪商人の繁栄に迫る!伊勢路が育んだ歴史と文化の秘密
NHK「ブラタモリ」伊勢神宮への旅シリーズもいよいよ第四夜に突入しました。今回の舞台は、三重県の津市と松阪市。伊勢参宮街道沿いに栄えたこれらの町には、歴史を動かした城、商人たち、そして世界に誇る食文化が根付いています。タモリさんたちは、津城を築いた藤堂高虎の戦略と、松阪商人たちが江戸を席巻した知恵、さらに松阪牛の秘密に迫ります。町並みや文化の奥深さを再発見できる、見応えたっぷりの旅となりました。
津城の築城に込めた藤堂高虎の狙いとは?

タモリさんが最初に訪れたのは、三重県津市にある津城。ここは、築城の名手として名を馳せた藤堂高虎によって江戸時代初期に大改修が施された城です。津は伊勢参宮街道沿いに位置する要衝であり、高虎はこの地に堅固な城を築くだけでなく、城下町の設計にも知恵を絞りました。
・津城の特徴は、輪郭式の構造で、防御力を高めるために城の中心部を高い石垣と堀で囲ったこと ・北側と東側には特に厚く高い石垣が積まれ、三重櫓を配して強固な防衛網を築き上げた ・城の東側には堀川を切り開き、物流の拠点としての機能も兼ね備えた都市づくりを行った
さらに高虎は、単なる軍事拠点にとどまらず、伊勢参宮街道を城下町に引き込む大胆な都市設計を行いました。これにより、伊勢参りの旅人たちが必ず津の町を通るようになり、宿場町としても大いに繁栄することになります。町の活気を高めるために、参拝前の立ち寄りスポットとして整備されたのが恵日山観音寺(津観音)です。
この観音寺には、阿弥陀如来像が本尊として祀られ、伊勢神宮の天照大御神の仮の姿とも信じられていました。参拝者たちは、伊勢に向かう道中で津観音にも手を合わせることが習慣となり、津の町は信仰の拠点としても一層賑わいを見せました。
現在、津城跡には復元された角櫓や立派な石垣が残されており、藤堂高虎の築城術の粋を感じることができます。堀川沿いには遊歩道も整備され、当時の城下町の雰囲気を楽しみながら歴史散策ができる人気スポットとなっています。
江戸を席巻した松阪商人の底知れぬ実力

津を後にしたタモリさん一行が向かったのは、伊勢路を南下した先にある松阪市です。ここは江戸時代、豪商たちが活躍し、日本経済を動かした重要な拠点でした。中でも有名なのが、三井グループの創業者である三井高利。彼を筆頭に、松阪の商人たちは江戸・日本橋を舞台に大きな商いを展開しました。
・松阪商人たちは「現金掛け値なし」という当時革新的な商法を導入し、信用第一を掲げた ・江戸日本橋には松阪出身の商人たちの店が並び、絹織物や呉服を扱う有力商人として台頭 ・出発前に寺子屋で読み書きや算盤を学ぶなど、実学重視の教育文化が根付いていた
松阪商人の強みは、単に商品を売ることではありませんでした。彼らは顧客の信用を第一に考え、値引き交渉をしないことで価格の透明性を確保しました。この姿勢が「三井越後屋」(のちの三越)を始め、多くの店に繁盛をもたらしたのです。
また、松阪商人たちは成功して得た財を、地元の教育や文化の振興に惜しみなく投資しました。町には寺子屋が多く設けられ、子どもたちに実践的な学びの場が提供されました。これにより、次の世代も優秀な人材が育ち、松阪は文化・経済の両面で日本有数の町へと成長していきました。
町を歩くと、当時の面影を残す商家や土蔵、資料館が今も数多く残り、豪商たちの暮らしぶりを肌で感じることができます。
伊勢路の旅人を支えた信仰と施しの文化
松阪の町で特に興味深かったのは、江戸時代のお伊勢参りの旅人たちの姿です。彼らは道中、柄杓(ひしゃく)を手に宿場を巡りました。この柄杓は、旅人が宿場の人々から水や食べ物などの施しを受けるための道具でした。
・旅人に施しを与えることは、宿場の人々にとっても神様への奉仕とされていた ・柄杓一本だけを持って旅を続ける「柄杓一本勝負」の旅人も多くいた ・中でも松阪は、豪商たちの厚意により特に多くの施しが期待できる宿場とされていた
施しの文化は、単なる善意ではなく、信仰心に根ざした行為でした。旅人を助けることは、自らも神の恩恵を受けることにつながると考えられていたのです。松阪の町は、この信仰と経済の両輪によって豊かさを築き上げていきました。
世界に誇る松阪牛誕生の背景

松阪といえば忘れてならないのが、松阪牛です。現在、日本を代表するブランド牛として知られる松阪牛ですが、その歴史には地元文化の積み重ねが大きく関わっています。
・ルーツは兵庫県但馬地方の但馬牛にあり、江戸時代は農耕用として利用 ・明治時代以降、食肉文化の普及とともに松阪地方で食用牛の飼育が本格化 ・松阪牛は、黒毛和種の未経産雌牛を特別に900日以上かけて育成する ・肥育には静かな環境と丁寧な世話が求められ、ビールやマッサージを施す農家もある
こうして手間暇かけて育てられた松阪牛は、きめ細やかな霜降り、甘くとろける脂、柔らかな食感を持ち、国内外のグルメたちから高く評価されています。
今回の旅でも、タモリさんはこの松阪牛に舌鼓を打ち、至福のひとときを味わう場面が紹介される予定です。単なるご当地グルメではなく、長い歴史と文化が生んだ奇跡の味として、松阪牛の魅力がたっぷり伝えられることでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

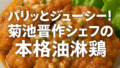
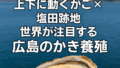
コメント