幻の骨〜日本人のルーツを探る
2025年6月3日(火)の夜22時からNHK総合で放送予定の『NHKスペシャル 幻の骨〜日本人のルーツを探る』では、日本人の祖先に迫る驚きの発見と、それに人生をかけた人々の歩みが描かれる予定です。今回の番組の中心となるのは、かつて「日本最古の人骨か」と注目されながらも、長らく行方不明となっていた旧石器時代の顎骨。この幻の骨が再発見されたことで、日本人の起源に関する新たな研究が動き出しています。
発見から半世紀を経て、ようやく見つかった幻の骨

およそ56年前のこと、鳥取県境港市の工事現場で、思いがけない発見がありました。現場の責任者で、化石の収集を趣味にしていた人物が、作業中に女性の下顎の骨のようなものを発見したのです。この骨は、専門家による調査で旧石器時代のものとされ、約4万年前の人骨である可能性が高いと判明しました。もし事実であれば、日本列島で人類が暮らしていた時期を大きくさかのぼらせる、教科書を書き換えるほどの大発見です。
この骨を鑑定したのは、当時早稲田大学で化石整理の仕事に携わっていた直良信夫(なおら・のぶお)という考古学者でした。正式な学問教育を受けず、独学で考古学を学んできた直良は、発見された骨を「夜見ヶ浜人(よみがはまじん)」と命名し、旧石器時代の女性の骨であると学会で発表しました。
ところが、当時の学会では「日本に旧石器時代は存在しない」という考えが主流で、直良の主張は受け入れられず、冷たくあしらわれてしまいました。その後、骨は早稲田大学から東京大学へと移されましたが、長い間、研究資料の山に紛れてしまい、行方がわからなくなってしまったのです。
この顎骨にまつわる具体的な経緯をまとめると、以下のようになります。
-
発見されたのは1969年(昭和44年)ごろ、境港市の工事現場
-
発見者は化石採集が趣味だった現場の責任者
-
骨の状態は保存が良く、鑑定可能なレベルだった
-
直良信夫が「夜見ヶ浜人」と命名し、旧石器時代の骨と発表
-
発表当時の考古学界では受け入れられず、注目されなかった
-
骨は早稲田大学から東京大学へ移される
-
1970年代後半には記録上からも姿を消し、実物は不明に
直良はその後も研究を続けましたが、彼の発見は長く学界で忘れられていました。この骨が再び注目されるようになるのは、それから数十年後のことになります。「幻の骨」と呼ばれるようになった背景には、骨の歴史的価値だけでなく、それをめぐる無視と埋もれた時間が深く関わっていたのです。
骨の行方を18年間追い続けた郷土史家の執念
行方不明となっていた「夜見ヶ浜人」の顎骨を18年ものあいだ追い続けた人物がいます。それが、鳥取県に住む郷土史家・根平雄一郎さんです。根平さんは、顎骨の存在を知った当初からその重要性に強い関心を抱き、独自に調査を始めました。研究者ではない一般人でありながら、彼は多くの文献を読み込み、当時の記録を一つ一つ確認していったのです。
特に力を入れたのが、関係する大学や研究機関への問い合わせと文献の洗い直しです。顎骨が最初に保管されていたとされる早稲田大学から、その後移送された東京大学に至るまで、記録の矛盾や手がかりを根気強く追い続けました。誰もが「もう失われたのでは」と諦めかけていた中で、根平さんだけが信じて調査を続けていたのです。
以下のような行動を通じて、根平さんは発見に至ります。
-
当時の発見者や研究者の証言を一つずつたどり直した
-
大学の研究室や資料庫の所在地を地道に調査
-
国会図書館や地元図書館の古い資料を照合
-
調査の途中経過をまとめた著書も自費出版し、関心を呼びかけた
そして2024年、東京大学のある倉庫の片隅で、段ボール箱の整理をしていた大学関係者が、中からラベルのない人骨の包みを発見。それが「夜見ヶ浜人」の顎骨だったのです。知らせを受けた根平さんは、長年探し続けたものがようやく見つかったことに胸がいっぱいになり、妻の美保子さんと抱き合ったと報じられています。
この発見は、考古学界に大きな衝撃を与えました。
-
直良信夫の鑑定が再び脚光を浴びるきっかけに
-
長く否定されてきた旧石器時代の日本人の存在を再検証できる材料となった
-
骨の分析が進めば、日本人のルーツに対する理解がさらに深まる可能性がある
一人の郷土史家の執念と信念が、学術の世界を動かし始めたのです。研究者ではなくとも、過去を掘り起こす努力が未来の歴史に影響を与えることを、この出来事は教えてくれます。
学会に背を向けられた在野の研究者・直良信夫の歩み
「夜見ヶ浜人」の骨を鑑定した直良信夫(なおら・のぶお)は、学会の中心にはいない在野の研究者でした。正規の教育を受けることなく、独学で考古学を学び続けた彼の研究人生は、常に既存の常識と向き合うものでした。1931年、直良が29歳のとき、兵庫県明石市の海岸で腰骨とみられる化石を発見します。彼はこの骨を「日本最古の人骨」と発表しました。
しかし当時の学会では、「日本列島に旧石器時代はなかった」とする見解が強く、直良の主張は受け入れられませんでした。彼の発表は嘲笑され、公式な学術の場では無視されることになります。発見された骨自体も、1945年の東京大空襲によって焼失し、痕跡だけが残る結果となりました。
それでも直良は諦めませんでした。
-
早稲田大学で化石整理の仕事に就き、地道に資料を扱い続けた
-
自らの発見を記録に残し、批判に屈することなく研究を継続
-
人骨の重要性と日本の先史時代の存在を、繰り返し訴え続けた
こうした直良の姿に感銘を受けたのが、作家の松本清張でした。1955年、清張は直良をモデルとした小説**『石の骨』**を発表します。この作品では、学会から無視されながらも真実を追い求める在野の人物が主人公として描かれ、学術界の権威主義や閉鎖性に対する静かな批判が込められていました。
清張と直良は、直接の交流もありました。直良が清張に送った手紙は、清張本人が大切に保管していたことが確認されており、二人の間に尊敬と共感の関係が築かれていたことがわかります。
直良の人生は、華やかな業績とは無縁でしたが、その信念は現代の研究者や歴史家にも影響を与え続けています。不遇の時代に信念を曲げず、日本の先史時代の存在を信じて行動した直良信夫の姿は、今になってようやく評価され始めているのです。
弟子がつなぐ想いと研究の灯火
再発見された「夜見ヶ浜人」の骨が持つ意味は、単なる考古学的価値だけではありません。それは、師から弟子へと受け継がれた信念と情熱の象徴でもあります。その思いを胸に、長年研究を続けてきたのが、考古学界の第一人者である春成秀爾(はるなり・しゅうじ)さんです。
春成さんが直良信夫と出会ったのは中学生のときでした。当時、ある博物館で直良が描いた化石のスケッチ画に強く心を動かされた春成少年は、その思いを手紙に綴って送りました。これがきっかけで二人は文通を始め、やがて交流を深めていきます。直良の誠実な姿勢と探究心に魅了された春成さんは、彼を「生涯の師」と仰ぐようになります。
その後、春成さんは考古学の道に進み、長年にわたって日本人の起源を探る研究に取り組んできました。今回再発見された顎骨についても、春成さんは特別な思いを寄せています。
-
骨を最初に鑑定したのが直良信夫だったこと
-
当時評価されなかった研究成果がようやく再び注目されていること
-
恩師の名誉と信念がようやく正当に評価されようとしていること
今回の番組では、春成さんがこの骨にどれほど深い想いを寄せてきたか、そして直良信夫という研究者の背中を追い続けた春成さんの人生にも焦点が当てられる予定です。再発見された骨は、春成さんにとって、恩師の存在を現代に伝える「証」でもあり、学問の世界において受け継がれてきた精神を具現化するものでした。
地道な努力と信念が次の世代へ受け継がれる様子は、歴史の重みとともに、未来への希望を感じさせます。研究はただのデータや資料ではなく、人と人のつながりの中で育まれていくのだと改めて実感させられる場面です。
現代の科学で解き明かす、骨の謎
長い年月を経て再発見された「夜見ヶ浜人」の顎骨は、現在の最先端技術によって、少しずつその謎が明らかにされつつあります。研究の中心を担うのは、東京大学総合研究博物館の海部陽介教授です。海部教授は骨の内部をCTスキャンで詳細に調べ、顎の内部にわずかに残っていた空洞から砂が詰まっていることを確認しました。
この砂が意味するものは極めて重要です。そこで、地質学に精通した瀬戸浩二教授が分析に加わりました。砂の粒の性質や堆積の特徴を調べた結果、この骨が境港の土ではなく、別の土地の地層に埋まっていた可能性が高いと指摘されました。つまり、発見場所とされてきた地点が実際とは異なるかもしれないという、根本的な再検討が必要になるのです。
また、人類学的観点からの比較も進められています。
-
夜見ヶ浜周辺で見つかった縄文人の骨と夜見ヶ浜人の骨を比較
-
骨の構造や大きさ、磨耗具合などを詳細に観察
-
夜見ヶ浜人が他の縄文人とは異なる特徴をもっていると専門家は分析
このことから、夜見ヶ浜人は縄文人とは異なる時代、あるいは異なる系統に属する可能性があるとされ、旧石器時代のヒトとしての独自性が注目されています。
さらに、年代を正確に測定するための作業も始まっています。東京大学の米田穣教授が、骨の一部を削り、炭素年代測定などの化学分析を実施。2年以内には具体的な年代が明らかになる予定です。
-
骨の炭素成分から出土年代を推定
-
他の旧石器時代の人骨との年代比較
-
骨の表面の劣化具合や成分も併せて解析
このように、化石発見当時には不可能だった高度な分析手法が今では実現可能となり、直良信夫が見出した発見の価値を現代の科学が追いかける形で証明しようとしているのです。
このプロジェクトは、単なる歴史の再検証にとどまらず、日本列島に人類がいつ、どこから渡ってきたのかという根本的な問いに迫る重要な研究となっています。過去の埋もれた真実が、科学の力によって少しずつ姿を現そうとしている今、その成果が注目されています。
まとめ
今回の番組では、旧石器時代の人骨の再発見という考古学的意義だけでなく、学界の常識に抗い続けた在野の研究者の執念、それを受け継ぐ弟子たち、そして真実を求めて18年かけて骨を探した郷土史家の努力が、一本の骨を軸に丁寧に描かれていました。分析が進めば、日本人のルーツに新たな光が当たるかもしれません。今後の研究結果の発表が待たれます。
この番組を見て思ったこと
見終わった後もしばらく心がざわつくような、深い余韻が残る番組でした。たった一本の顎骨が、これほどまでに多くの人の人生や情熱を動かしてきたのかと思うと、その存在の重さに圧倒されます。半世紀以上も行方不明だった「夜見ヶ浜人」の骨が見つかるまでの過程は、発見そのもの以上に、人が真実を信じ続ける力の物語でした。
郷土史家・根平雄一郎さんの18年間の地道な調査は、まさに執念という言葉がぴったりでした。専門家でもない一人の市民が、記録の矛盾を一つずつ紐解き、関係者に連絡を取り続け、ついには幻の骨を現実の手元に引き寄せる。その姿勢に、学問の世界を動かすのは必ずしも肩書きや立場ではなく、信じる心と諦めない行動なのだと感じました。
そして、在野の研究者・直良信夫の存在も忘れられません。学会に受け入れられず、嘲笑や無視に耐えながらも、日本の先史時代の存在を訴え続けた半生。その信念が弟子や作家、そして現代の研究者にまで受け継がれていることが、この番組から伝わってきました。
現代の科学で骨を詳細に分析し、発見地の真偽や時代的背景を再検討していく場面は、歴史が「生きた問い」へと変わっていく瞬間のようでした。砂粒や骨の劣化状態、炭素年代測定――ひとつひとつの結果が、何千年も前の人間の暮らしに少しずつ光を当てていく。
この番組は、考古学の発見を紹介するだけでなく、それに人生を捧げた人々の物語を丹念に描き、視聴者に「歴史は人がつくるもの」という実感を与えてくれました。これからこの骨がどんな新しい事実を語り出すのか、続報を心から待ちたいと思います。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


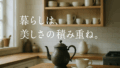
コメント