冬から春へ 命が躍動する神奈川・城ヶ島の海
神奈川県三浦半島の南端に位置する城ヶ島(じょうがしま)は、東京から約60kmという近さにありながら、豊かな自然と多様な海洋生物が共存する特別な場所です。東に東京湾、西に相模湾、南には黒潮の分流という3つの潮流がぶつかり合う海域に浮かぶこの島では、なんと500種以上の魚が生息しています。『さわやか自然百景』では、冬から春へと向かう季節の中で、小さな命がたくましく育つ様子や魚たちの繁殖の営みが紹介されます。
魚たちの楽園・城ヶ島の海とは

城ヶ島の周囲の海は、東京湾の栄養豊富な内湾水と、相模湾の深く冷たい海水、そして黒潮の温かい外洋水が入り混じる、まさに潮の交差点です。異なる海の性質がぶつかり合うことで、海中にはさまざまな環境が生まれ、それぞれに適応した魚たちが暮らしています。
-
小さな甲殻類やプランクトンが豊富なため、それを食べる小魚が多く集まります。
-
小魚を狙う大型の回遊魚も周囲を巡るため、食物連鎖が複雑に構築されています。
-
地形も変化に富み、砂地・岩礁・藻場・潮だまりなど、魚たちのすみかが豊富にあります。
このような条件により、相模湾と東京湾の魚種を合わせて500種以上が確認されているという、全国的にも非常に珍しい海域となっています。
2月 極寒の海で命をつなぐ魚たち

水温が最も低くなる2月。この冷たい海の中でも、命をつなぐ準備が静かに始まっています。特に注目されるのが、城ヶ島の岩場や砂地にひっそりと暮らす2種の魚です。
-
コケギンポは、岩のくぼみや空き缶などを巣穴として利用する魚です。冬の産卵期になると、メスが産んだ卵をオスが一週間以上も守り続けます。外敵から卵を守るだけでなく、ヒレで水流を送り、酸素を届けるという丁寧な子育てを行います。このようにして、厳しい冬を乗り越える次世代の命が育まれます。
-
サビハゼは、砂地にある小さな岩の下に巣穴を作ります。メスが産んだ卵を、こちらもオスが単独で守る習性があります。オスは、巣穴からほとんど出ずに卵を守り、孵化までじっと耐えます。周囲の敵から守ると同時に、こちらも水流を送って酸素を確保する姿が見られます。
いずれの魚も、寒さに負けず子育てに励む姿がとても健気で力強く、城ヶ島の海の生命力を象徴する存在です。
3月 海藻の森で命が育まれる春

春の兆しが見え始める3月。城ヶ島の浅瀬では、ワカメやカジメといった大型の海藻が一気に成長を始め、海の中に「緑の森」が広がります。この海藻の森は、たくさんの命を育てる場所として大きな役割を果たします。
-
体の小さな幼魚たちは、外敵から身を守るために海藻の陰に隠れて過ごします。
-
メバルやアイナメなどの稚魚が、プランクトンや小型のエビを食べながらゆっくりと成長します。
-
海藻自体にも小さな生き物が付き、彼らもまた食物連鎖の一部として重要な存在になります。
このような海藻の森は「海の保育園」とも呼ばれ、多くの生き物の命を育む場として機能しています。
しかし、近年では地球温暖化や磯焼けの影響で、こうした海藻の森が各地で減少しています。城ヶ島でも保全活動や海藻の植え付けが行われており、地域ぐるみで豊かな海を守る努力が続けられています。
島の魅力と自然の共演
城ヶ島の魅力は、海中の生き物たちだけではありません。陸地の自然もまた、訪れる人々の心を癒やしてくれます。
-
城ヶ島公園は、島の東側に広がる広大な公園で、富士山や伊豆大島まで一望できる絶景スポットです。冬には約10万株の水仙が咲き誇り、香りに包まれた穏やかな時間が流れます。
-
馬の背洞門は、波によって削られたアーチ状の奇岩で、自然の彫刻ともいえる景観です。写真映えする絶景としても人気です。
-
城ヶ島灯台・安房埼灯台は、島の東西にそれぞれ建ち、航海の安全を見守っています。どちらも「恋する灯台」として知られ、ロマンチックな雰囲気に包まれています。
-
水中観光船「にじいろさかな号」では、宮川湾の海中を観察でき、実際に多様な魚や海藻の様子を見ることができます。
命あふれる城ヶ島の魅力を伝える15分
番組『さわやか自然百景』では、15分という短い時間の中で、冬から春にかけて移り変わる城ヶ島の海の表情や、そこで懸命に生きる生き物たちの姿が丁寧に描かれる予定です。海の中の静かな営みに目を向けることで、普段は見えない自然の奥深さに触れることができます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

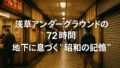
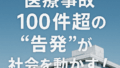
コメント