情熱の連鎖が生んだ音楽革命〜初音ミク 誕生秘話〜
2007年に発売された歌声合成ソフト「初音ミク」。それは、音楽制作をプロだけのものから誰でも参加できる表現手段へと広げた、まさに音楽の革命でした。今回の『新プロジェクトX』では、その誕生の裏にあった小さな会社とわずかな人数の技術者たちの挑戦、そして無名のクリエイターたちの情熱が描かれました。機械の声では感動できないという“常識”を覆したその軌跡を、番組の内容に沿って詳しく振り返ります。
札幌の片隅から始まった静かな挑戦
1990年代の音楽業界は、CDセールスの最盛期であり、小室哲哉さんのプロデュース楽曲がチャートを席巻する華やかな時代でした。そんな中、北海道・札幌にわずか3人の社員で立ち上がった会社がありました。それが「クリプトン・フューチャー・メディア株式会社」です。
創業者の伊藤博之さんは、子どものころから音楽に夢中で、学生時代から自宅でコンピューターを使って曲作りに励んでいました。大学職員として働きながら、自ら作った効果音やBGMをCDに収録し、海外に文通で販売するという活動から、ビジネスが始まります。
やがて「着メロ」市場の拡大にともなって事業は拡大。社員も20人規模に成長し、本格的に音楽制作支援ソフトの会社として動き始めていきます。そんな中、運命の出会いが訪れます。ある打ち合わせの席で、伊藤さんは取引先の担当者から「ちょっと聞いてみて」と音源を渡されます。流れてきたのは、コンピューターが人間のように歌う声でした。
たった4人の技術者が挑んだ「歌うソフト」
この音声合成技術を開発していたのは、静岡にある総合楽器メーカー「ヤマハ」の研究部門です。歌声合成のチームはたった4人。中心人物は剣持秀紀さんと藤井茂樹さんでした。
研究が始まったのは2000年頃。課題は、「歌詞が聞き取りにくい」ということでした。剣持さんは言葉を分解し、音をパーツ化して接続する方法にたどり着きます。
・2文字の言葉を5つの要素に分けて繋ぐことで、より自然な発音に
・人間の声の中にある「息」を残すことで、抑揚や表情のある歌声が可能に
・数えきれないほどのサンプルを録音・分析し、アルゴリズムの改良を続ける
開発は2年におよび、ようやくコンピューターに1曲を滑らかに歌わせることに成功しました。しかし、社内では「人間のほうが早くて上手い」と言われ、製品化は却下されます。それでも伊藤さんはこの技術に可能性を感じ、販売を引き受けることを決断します。
自由に楽しめる“キャラクターのある声”へ
伊藤さんは、「歌うソフト」というだけでは人に興味を持ってもらえないと考えました。そこで重要になるのが“キャラクター”。ソフトに親しみやすさを持たせ、誰でも創作したくなる存在にすることが狙いでした。
そのアイデアに反応したのが、入社2年目の佐々木渉さん。彼は音に対して深いこだわりを持っており、「自分の知らない音に出会えるかもしれない」と開発に加わりました。
・300人以上の声優候補の中から、透明感と強さを兼ね備えた藤田咲さんを選出
・“未来から来た少女”という設定で、アンドロイドのようなキャラデザインを採用
・キャラクター名は「初めての音」「未来の音」を合わせて“初音ミク”と命名
2007年4月に音声収録が行われ、半年の開発期間を経て製品が完成。同年8月に発売された「初音ミク」は、1か月で1万5000本を超える大ヒットとなりました。
作品がつなぐ世界と情熱の連鎖
発売直後、動画投稿サイトには初音ミクを使った楽曲が続々と投稿されます。とくに話題になったのが「メルト」という楽曲でした。これを機に、無名だった作曲家たちが高品質な楽曲を発表し始めます。
・大学生だったDECO*27さんは、初音ミクとの出会いがきっかけで自作曲の投稿を始め、プロ作家に
・米津玄師さん(当時の名義:ハチ)も投稿サイトで楽曲を公開し、独特な世界観で注目を集めメジャーデビュー
・Ayaseさん(YOASOBI)も初音ミクを使って楽曲制作を始め、のちに大ヒット曲「夜に駆ける」を生み出す
当初、企業やレコード会社から「初音ミクの肖像権を譲ってほしい」というオファーが殺到しましたが、伊藤さんはそれを拒否。「みんなで自由に使える道具であってほしい」という思いから、一定のルールのもと無料で使用できることを公式に宣言しました。
初音ミクがつないだ未来と文化
2011年には、アメリカ・ロサンゼルスで初音ミクのソロライブが開催されます。3D映像と音楽が融合したステージには、世界中からファンが集まりました。さらに、初音ミクの楽曲を“人間が歌う”という新しい文化も生まれ、Adoさんのような次世代アーティストが登場します。
・Adoさんは「ボカロがなかったら自分はいない」と公言
・当初は難しすぎると言われた高音や速いテンポも、ボカロを聴きながら真似て歌えるように
・ボカロはもはや1つのジャンルとして定着し、文化として社会に根付く存在へ
そして今、初音ミクは発売から18年を迎え、他社製ボカロも登場し続けています。誰もが音楽を作り、発信できる時代をつくった“情熱の連鎖”は、これからも続いていきます。
※放送の内容と異なる場合があります。ご了承ください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

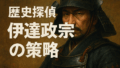
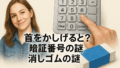
コメント