密着!ジャングルスクール オランウータン いのちの学校
2024年11月17日にNHK総合で放送された『ダーウィンが来た!』では、「密着!ジャングルスクール オランウータン いのちの学校」と題して、インドネシア・カリマンタン島の熱帯雨林にある特別な施設「ジャングルスクール」の取り組みが紹介されました。この施設では、親を失ったオランウータンの孤児たちが野生への復帰を目指して暮らしています。番組ではその日々の学びや苦悩、命のつながりに迫る様子が描かれました。
ジャングルスクールとは?森で生きる力を学ぶ場所

舞台はインドネシア・カリマンタン島にある「ニャルメンテン・レスキュー&リハビリテーションセンター」。ここでは、親を失ったオランウータンの孤児たちが野生に戻るための訓練を受けながら暮らしています。これまでに500匹以上の個体が野生復帰に成功しており、その成果と信頼性の高さがうかがえます。
生徒となるオランウータンたちは、アブラヤシ農園の拡大や密猟によって親を失った孤児たちです。人間が母親の代わりとなり、食べ方から寝方までを丁寧に教えます。
・オランウータンは、一生の大半を木の上で暮らす動物です。枝から枝へと移動しながら食べ物を探し、安全な寝床を作ります。
・食事の中心は森の果実や葉、昆虫など。「何を食べてよいのか」も人が一から教える必要があります。
・毎晩、新しいベッドを葉っぱで作って眠るという習性も身につけなければなりません。これは捕食者から身を守るための大切な知恵です。
・敵の存在にも気づかせます。ジャングルにはヘビなどの天敵も潜んでおり、危険を察知して逃げる感覚も育てます。
ジャングルスクールでの生活はまさに「生きる練習」です。先生役の人たちは、まるで母親のようにそばについて教え、見守り、時には一緒に木に登って行動を示します。
また、孤児たちは他のオランウータンと接することで、社会性やコミュニケーションの力も学んでいきます。これは将来、森で他の個体と出会ったときに必要となる能力です。
このようにジャングルスクールは、単に保護するための場所ではありません。「もう一度、森で自分の力で生きる」ための準備を整える学校なのです。一つ一つの行動が、やがて自立の一歩につながっていきます。
森を奪われた“森の人”たち

オランウータンは「森の人」という意味の名前を持つほど、森林と深く結びついた生き物です。ですが、近年はその森が急速に失われつつあります。最大の原因は人間による森林伐採と土地開発です。とくにアブラヤシの栽培を目的としたプランテーション開発が進むことで、熱帯雨林が次々と切り開かれていきました。
・アブラヤシのプランテーションは、パーム油を大量に生産するためのもので、食品・化粧品・洗剤など多くの製品に使われています。
・これにより、オランウータンの生息地は分断・縮小し、安全に暮らせる場所を奪われてしまいました。
・さらに、森が減ることで食べ物も少なくなり、人里に降りてきた親子が人間に襲われるケースも発生しています。
オランウータンが孤児になるもう一つの理由が違法な密猟です。赤ちゃんオランウータンは可愛らしい姿からペットとして高値で取引されます。
・しかし赤ちゃんを捕まえるには、必ずそばにいる母親を殺す必要があります。その結果、命を奪われた母親のそばで取り残される赤ちゃんがあとを絶ちません。
・輸送中の赤ちゃんの多くも命を落とし、わずかに生き延びた個体が保護施設に引き取られることになります。
こうして保護された孤児たちは、何も知らない状態で人間のもとに運ばれてきます。森の中でどうやって生きていけばいいのか、まったくわからない状態です。
ジャングルスクールは、そうした人間の都合によって命を翻弄されたオランウータンたちに、再び森で暮らす力を教えるための場所です。
・人間の手によって森を失い、家族を失った彼らが、再び自然の中で生きるために必要なことを、ひとつひとつ丁寧に学んでいきます。
・食べ物の探し方、木登り、寝床の作り方、そして仲間との関わり方――それらすべてが、生きる力となっていくのです。
このようにジャングルスクールの存在は、ただの保護ではなく、責任を持って命と向き合う「再生」の場でもあります。人間に奪われた森と命を、人間が少しずつ取り戻していく。その姿勢が、未来につながる希望を育てているのです。
生徒たちの成長と新たな命

番組では、11歳のメスのオランウータン「ディラ」の物語が丁寧に追われました。ディラは11歳で妊娠しており、これは野生のオランウータンではかなり早い段階での妊娠にあたります。自然界では通常、15歳前後で初めて出産を迎えることが多いため、ディラのケースは例外的といえます。
出産自体は無事に終わりましたが、問題はそのあとに起きました。ディラは生まれた子どもを育てようとしなかったのです。その理由は、彼女の過去にありました。
・ディラは5歳までペットとして人間に飼われていた経験があります。
・その間、オランウータンの子どもにとって最も大切な時期を、本来の母親と過ごすことができませんでした。
・オランウータンの育児は約7年にわたり、母親から生きる術を学ぶのが基本です。ディラはその期間に、母親から子育てを学ぶ機会を持たなかったのです。
このように、たとえ命をつなぐことができても、育て方がわからなければ次の命を守ることができないという現実があります。これは、人間の都合によって自然から引き離されたオランウータンが背負う大きな代償です。
・ジャングルスクールでは、このような状況にも対応できるよう、子育ての知識を補うプログラムも用意されています。
・スタッフが近くで見守りながら、必要であれば子どもの世話を代行し、その様子をディラ自身にも見せていきます。
・また、他の母親オランウータンの行動を観察できるようにし、「見て学ぶ」機会も意識的に与えているのです。
ディラのケースは、オランウータンにとっての「育てる力」と「親の存在の大きさ」を示す象徴的な出来事でした。人に翻弄された命が新しい命を迎えたとき、そこには育て方すら失われた現実があるということを、私たちにも深く考えさせられるエピソードです。
最後の試練と旅立ちの日

ジャングルスクールでの学びを終えたオランウータンたちにとって、野生復帰への最終試験が用意されています。その舞台は、川に囲まれた孤立した島。ここには人の手は加えられておらず、すべて自力で生活することが求められます。
・この島では、木から木へと移動する能力が試されます。枝をつかみ、自分の力だけで移動範囲を広げていく姿は、まさに野生で生きる準備そのものです。
・食料もすべて自分で探さなければなりません。水中に生える植物を見つけて食べる様子も確認され、自然の中で食べ物を選ぶ力が育っているかが大切なポイントとなります。
・仲間との距離感や関わり方も重要で、他のオランウータンと協調して行動できるかどうかも評価されます。
ディラとその子どもも、この試練に挑みました。自分の意思で木に登り、果物を探し、時には水辺でじっと様子をうかがうような姿が見られました。この経験を経て、ふたりは施設からおよそ400km離れた国立公園へと旅立つことになります。
・旅立ちはヘリコプターなどを使って慎重に行われます。ストレスを与えないよう、静かな環境が整えられ、運搬中も専門スタッフが付き添います。
・移送先となる国立公園は、自然が豊かで他のオランウータンたちも暮らしている場所。新たな生活のスタート地点として選ばれた、安全な場所です。
ジャングルスクールで人に育てられたディラたちが、今度は人の手を離れ、自然の中へと自分たちの足で帰っていく姿は、非常に感動的です。過去に人間によって命を翻弄された彼女たちが、同じ人の支えによって未来へ進む姿は、まさに希望の物語です。
この旅立ちは終わりではなく、新しい森での暮らしの始まりです。一度は失われかけた“森の人”の未来が、もう一度息を吹き返す瞬間とも言えるでしょう。私たちにできるのは、その姿を見守り、支え続けていくことなのです。
命の学校で学ぶこと
この番組を通して、「命の学校」であるジャングルスクールがどれほど重要な役割を果たしているのかを改めて感じました。オランウータンたちは、ただ助けられるだけではなく、もう一度“森の人”として生きていくための力を、自らの意思で手に入れていくのです。
番組の最後には、孤児だった生徒たちが今日も森へ帰るために学び続ける姿が描かれ、静かにエンディングを迎えました。
この感動的なドキュメンタリーをきっかけに、私たちも自然と動物たちとの関わり方について、もう一度考えてみる機会になるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


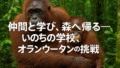
コメント