シマフクロウレスキュー密着3年の結末とは?野生復帰と種の保存の最前線
2025年4月13日(日)のNHK『ダーウィンが来た!』では、絶滅危惧種「シマフクロウ」の野生復帰と種の保存に関する壮大な取り組みが放送されました。釧路湿原野生生物保護センターを舞台に、親を失った1羽のフクロウ「ハル」が自然に帰るまでの3年間にわたる密着ドキュメントです。北海道でしか見られないシマフクロウの命をつなぐために、全国の専門家や施設が一丸となって取り組む姿が描かれました。
密着!野生復帰プロジェクトの始まり

シマフクロウは北海道にしかいない、とても珍しいフクロウです。その生息地はごくわずかで、日本全体でもわずか200羽ほどしか確認されていません。環境省が厳しく保護しており、生息地の詳細も一般には公表されていません。今回の番組では、特別な許可を得て、その貴重なシマフクロウの保護活動に密着することができました。
釧路湿原野生生物保護センターは、こうした希少動物を保護し、治療やリハビリを行う拠点となっています。中でも注目されたのが、2021年11月に登場したオスのシマフクロウ「ハル」です。ハルは生まれてすぐに親を失い、人の手で育てられてきましたが、本来であればすでに独り立ちして野生で生きているはずの年齢でした。そのため、センターではハルを自然の中に帰す「野生復帰」の訓練が始まったのです。
-
最初のステップは、浅い池に生きた魚を放すところから。ハルは池に入り、魚の動きをじっと見つめていました。ここで魚を追う感覚を身につけます。
-
次に、より狭い容器で魚を泳がせ、狩りのタイミングを覚えさせる練習へと進みました。狭い空間で魚の動きを追うことで、ハルの集中力が高まっていきます。
-
そして、最終段階では、「待ち伏せして魚を獲る」技術を習得することに成功します。これは野生で生きていくために欠かせない力で、シマフクロウ特有の狩猟スタイルです。
こうした段階的な訓練を通じて、ハルはただ餌をもらうだけではなく、自らの力で生きる術を学んでいきました。人の手が加わっているとはいえ、その方法はできるだけ野生に近づけるように細心の注意が払われています。たとえば、人の姿を見せないようにするために監視カメラを使いながらの訓練が行われており、ハルが人間に依存しないようにする配慮が徹底されています。
このプロジェクトは、ひとつの命をただ守るだけでなく、自然の中で生きる本来の力を取り戻すことを目指すものです。人間ができる限り関与を最小限にしながら、その命がもう一度森の中で羽ばたけるように支えていく。それがこの「野生復帰プロジェクト」の根幹です。
ハルの物語は、今もなお進行中です。彼がどこまで自然に近づけるか、その一歩一歩を支えている人々の姿が、このプロジェクトの重みと希望を物語っていました。
命を守るためのレスキューと連携

番組では、交通事故によって保護された1羽のシマフクロウ「ナツ」のケースが取り上げられました。ナツは夏のある日、北海道の道路脇でぐったりと倒れているところを発見されました。調査の結果、頭部に強い衝撃を受けており、さらに翼も骨折していました。さらに、片目には後遺症が残り、瞳孔の大きさが左右で異なる状態になってしまったのです。
-
ナツが事故に遭った原因は、道路に出てきたカエルを食べていたところに車のヘッドライトが当たり、目がくらんで動けなくなったためとされています。夜行性であるシマフクロウにとって、突然の強い光は大きな脅威となります。
こうした事故が繰り返されないよう、釧路湿原野生生物保護センターでは道路沿いに溝を掘るなどの工夫を加えた対策を進めています。この溝は、車が通る際の振動や音を伝えることで、動物たちが近づかないように注意を促す仕組みになっています。
-
野生復帰が難しい場合には、次の選択肢として動物園での保護飼育が行われます。現在、釧路市動物園には20羽近いシマフクロウが保護されており、傷ついた個体たちが安心して暮らせる環境が整えられています。
この動物園は、世界で初めてシマフクロウの飼育下での繁殖に成功した施設としても知られており、種の保存という面でも大きな役割を果たしています。
-
シマフクロウは非常に繊細な性格で、広いゲージや静かな環境が必要とされるため、一つの施設で多くの個体を収容するのは難しいとされています。そのため、全国の動物園が協力し、分散飼育という形でシマフクロウの保護を支えているのです。
保護センターと動物園が連携することで、野生に戻ることができない個体に対しても、命をつなぐチャンスが確保されていることがわかります。また、動物園での飼育は、将来的な繁殖を通じて新しい命を育む役割も担っており、シマフクロウという貴重な種を未来に伝えるための重要な拠点となっています。
ナツのように事故に遭ったフクロウが、保護されたあとも適切なケアを受け、安全な場所で生きていくことができる背景には、多くの人の連携と工夫があることを、この番組は丁寧に伝えていました。
ハルの訓練、そして新たな役割へ

野生での暮らしを目指して訓練を続けてきたシマフクロウのハルは、ついに深さ40cmほどの池でも魚をとらえる力を身につけました。これまで浅瀬での狩りを中心に練習していたハルですが、難易度の高い条件でも結果を出せるようになったことで、保護センターでは「野生でも生きていける能力が備わった」と判断されました。
-
狩りの動きには変化があり、魚が集まりやすい浅瀬を探し出して待ち伏せするという、自然の中で必要な“知恵”を見せるようになりました。
-
獲物を仕留めるまでの間、ハルは一切音を立てずにじっとその場に身をひそめる姿が観察され、野生本来の静かな集中力も確認されています。
こうした成長の結果、ハルには次の役割として「繁殖」への参加が託されることになりました。ハルは自然の親から生まれ、遺伝的にも非常に貴重な血統を持っているだけでなく、事故経験もないため健康状態も良好で、将来的な子孫の育成にも大きな期待が寄せられています。
-
2024年2月、ハルは釧路市動物園へと移送され、繁殖プログラムに参加することになりました。ここでの新たなパートナーとして用意されたのが、メスのシマフクロウ「ミドリ」です。
-
初めての対面では、ミドリがハルに近づく場面がありましたが、ハルはすぐにその場から飛び立って距離を取るなど、慎重な反応を見せていました。
-
それでも時間が経つにつれてお互いの存在に慣れ、10月には動物園スタッフも「ペアとして認められる関係に進展した」と確認。将来、ヒナが誕生する可能性も現実的になってきました。
一方で、番組はもう1羽のシマフクロウ「ナツ」の近況にも触れています。ナツは事故で片目を失い、翼の傷も完全には癒えていないものの、1年半にわたるリハビリを経て、魚を捕る動作を習得するまでに回復しました。
-
餌場となる池では、ナツが獲物を見つけ、水面すれすれに飛び込む姿が確認されました。
-
翼のバランスを取りにくい様子も見られましたが、自然に近い動作を試みるナツの姿には、生命力の強さが感じられました。
ハルとナツ、どちらも異なる状況からスタートしたものの、それぞれの場所で生きる力を育み、新しい一歩を踏み出していることが伝わってきます。自然界に戻るという道だけでなく、種の保存や教育的役割など、多様な選択肢の中で命がつながれていることが、今回の放送では丁寧に描かれていました。
命をつなぐ人々の挑戦
この番組を通して伝わったのは、「1羽でも多くの命を救いたい」という真剣な思いでした。単に保護するだけでなく、自然に戻すという難しい挑戦に対し、環境省・獣医師・動物園が連携し、粘り強く取り組む姿が描かれています。
シマフクロウの未来は、人と自然がどう向き合うかにかかっています。希少な命を未来へと繋ぐため、私たちにできることを考えさせてくれる内容でした。
放送を見逃した方も、NHKプラスなどでぜひご覧ください。今後のハルやナツの様子にも注目が集まりそうです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

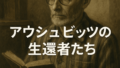
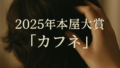
コメント