首里城の漆職人・小豆島のしょうゆ蔵・ドクターイエロー|3月13日放送
14年間にわたり、働く人々のランチを通じて人生や仕事の裏側を伝えてきた「サラメシ」が、ついに最終回を迎えます。今回の放送では、3つの特別な現場に密着し、それぞれの職人たちの仕事と昼ごはんに迫ります。取り上げられるのは、沖縄の首里城再建に携わる漆職人、香川県・小豆島の老舗しょうゆ蔵の5代目、そして1月末に引退したドクターイエローT4編成の検測員たちです。どの現場も、日本の伝統や技術を守る大切な仕事。彼らの仕事ぶりと食事の様子から、職人のこだわりや想いが伝わってくるでしょう。
首里城再建に挑む漆職人たちの技術と努力

2019年に焼失した首里城を再建するため、多くの漆職人が日々作業に取り組んでいます。首里城の美しい朱色や豪華な装飾を復元するには、単に漆を塗るだけではなく、緻密な技術と経験が必要です。漆を使う作業は、見た目の美しさだけでなく、長期間耐久性を保つための工夫も求められます。
漆を塗る作業は、何度も重ね塗りを行うことで独特の艶や深みが生まれます。一度に厚く塗るのではなく、薄く均等に塗り重ねることが重要です。この工程を何度も繰り返すことで、首里城特有の色合いと質感を再現していきます。
-
漆の調合が決め手
漆の色は、顔料の種類や配合比率によって微妙に変わります。首里城の朱色を正確に再現するためには、過去の資料をもとに最適な漆の配合を見つけることが必要です。さらに、顔料の粒子の大きさや混ぜる順番も、仕上がりに影響を与えるため、熟練の職人が細かく調整しながら作業を進めます。 -
環境管理が仕上がりを左右する
漆は乾燥する過程で固まるのではなく、湿気を含むことで硬化します。そのため、適切な湿度や温度を保つことが不可欠です。作業場では、加湿器を使って湿度を一定に保ち、漆が適切に硬化するように管理されています。もし湿度が低すぎると、漆がうまく固まらず、仕上がりが悪くなるため、職人たちは天候や室内環境をこまめにチェックしています。 -
若手職人の育成が再建のカギ
漆塗りの技術は、習得するのに時間がかかるため、若手職人の育成が非常に重要です。今回の首里城再建プロジェクトでは、多くの若手が参加し、ベテラン職人の指導を受けながら技術を学んでいます。例えば、筆の持ち方一つとっても、漆をムラなく塗るためのコツがあり、こうした技術を身につけるには何年もの経験が必要になります。 -
地元の素材を活かした漆づくり
首里城の復元には、地元の素材を活かした漆を使用することも重要視されています。沖縄県産の漆は全国的に見ても希少であり、これを活用することで地域の伝統工芸の復興にもつながると期待されています。地元の漆生産者と協力し、再建に必要な漆を確保する取り組みも進められています。
漆職人たちは、こうした細かい工程や管理を徹底することで、首里城の美しさを蘇らせるために奮闘しています。ただ作業を進めるだけでなく、次世代に伝統技術を継承することも、この再建プロジェクトの大きな目的の一つです。首里城の復元が進むことで、沖縄の漆文化が再認識され、未来に受け継がれる工芸の価値が改めて見直されることが期待されています。
首里城再建に励む漆職人・森田哲也さんの昼休み
首里城の再建に携わる漆職人・森田哲也さん。彼は職長として30人以上の職人をまとめ、首里城の赤い漆塗装を担当しています。首里城の象徴ともいえる赤色は、「弁柄」と呼ばれる天然の塗料を使用した特別な漆で、扱いが非常に難しいものです。漆を塗る工程は場所によって異なりますが、最大で30もの工程を経て仕上げられることもあります。
そんな森田さんにも、昼休みのひとときが訪れます。午後12時、現場隣にある休憩所には、漆職人だけでなく鳶職などの関係者も集まり、それぞれの弁当を広げます。森田さんの昼ごはんは、妻が手作りした弁当。おかずやご飯がぎっしり詰まった愛情たっぷりの弁当は、再建工事に励む彼の活力となっています。
- 奥様は木工家で、箸や器などの制作を手掛けている
- 首里城の塗り替え工事を通じて出会い、結婚
- お弁当には沖縄の食材を活かした料理が詰められていることも
仕事で使う道具にも奥様の手作りのものがあり、彼にとってはかけがえのない存在となっています。
2006年の大規模塗り替え工事の際、森田さんはまだ職人になりたてで、漆塗りの技術を首里城で学びました。2019年の焼失時は、状況が理解できず、しばらくは実感が湧かなかったそうです。それでも、今は再建に向けて漆塗りの技術を駆使し、首里城を甦らせるべく尽力しています。
漆塗りは、温度や湿度の影響を受けやすく、繊細な調整が必要な作業。「乾燥が早すぎると塗りムラができ、遅すぎると光沢が出ない」という難しさがあるため、職人の経験と技術が問われます。森田さんは、長年培った技を駆使しながら、後輩職人たちにも技術を伝えています。
首里城再建の現場では、様々な職人たちが携わっています。漆職人、木工職人、鳶職など、多くの人の力が合わさることで、首里城が少しずつ形を取り戻していきます。昼休みには、そんな職人たちが集まり、仕事の話をしたり、雑談を交えながら束の間の休息を取る大切な時間になっています。
一つ一つの工程を丁寧に進めながら、完成に向けて歩みを止めることなく取り組む漆職人たち。その背中には、首里城再建への強い想いが込められています。
150年以上続く小豆島のしょうゆ蔵の伝統と挑戦

小豆島には、400年以上続く醤油造りの文化があります。その中でも、「ヤマロク醤油」は150年以上の歴史を持つ老舗のしょうゆ蔵です。昔ながらの木桶仕込みを続けており、深いコクと香りを持つしょうゆを生み出しています。
木桶仕込みのしょうゆ造りは、現代ではとても貴重になっています。多くの醤油メーカーがステンレスタンクを使用するのに対し、ヤマロク醤油では杉で作られた木桶を使用し、じっくり時間をかけて発酵・熟成させます。木桶の内側には何十年、時には100年以上かけて育った乳酸菌や酵母菌が住み着いており、しょうゆに複雑な旨味を与えます。
-
木桶は職人の手作り
木桶は、ただの容器ではなく、しょうゆの味を決める重要な要素です。しかし、木桶を作る職人は全国に数人しかいないほど減ってしまいました。そのため、ヤマロク醤油の5代目は、木桶の修理や新しい木桶を作る技術を学びながら、「木桶職人復活プロジェクト」を立ち上げました。全国の職人たちと協力し、少しずつ新しい木桶を作り、未来にこの技術を伝える活動を進めています。 -
発酵には自然の力が必要
しょうゆを発酵させるには、適度な温度と湿度が欠かせません。小豆島の気候は醤油造りに適しており、寒すぎず、暑すぎず、穏やかな環境が発酵を助けます。さらに、木桶は空気を通すため、発酵が自然に進み、まろやかで深い味わいが生まれるのです。 -
発酵期間は2年から3年
一般的なしょうゆは半年から1年ほどで完成しますが、ヤマロク醤油の木桶仕込みは2年以上の熟成期間をかけます。発酵がゆっくり進むことで、角の取れた丸みのある味わいになり、特に刺身や卵かけご飯に合う濃厚な風味が生まれます。 -
見学できる伝統の醤油蔵
ヤマロク醤油では、しょうゆ蔵の見学が可能です。木桶が並ぶ蔵の中では、長年使われてきた桶の表面にびっしりと付いた菌の層を見ることができます。この菌の働きが、ヤマロク醤油の独特な風味を生み出しています。見学の際には、発酵を妨げる可能性があるため、前日に納豆を食べることを控えるようにお願いされています。 -
醤油を活かした絶品ランチ
併設の「ヤマロク茶屋」では、しょうゆを使った料理やスイーツを楽しめます。特に人気なのが、「しょうゆアイス」。甘じょっぱい味わいがクセになり、観光客にも評判です。さらに、週末限定の「黒豆入りしょうゆプリン」は、木桶仕込みのしょうゆならではの香ばしさとコクが楽しめる一品です。
職人たちのランチもまた、地元の食材をふんだんに使い、しょうゆの味を最大限に引き出す工夫がされています。特に、炊きたてのご飯にたらした「鶴醤(つるびしお)」は絶品。しょうゆを知り尽くした職人が、自らの作った醤油で食事を楽しむのは、まさに贅沢なひとときです。
ヤマロク醤油の挑戦は、伝統を守るだけでなく、新しい木桶を作り、未来へ技術を受け継ぐことにもあります。小豆島の醤油文化が、これからも続いていくように、職人たちは日々努力を重ねています。
山本さんの昼ごはんを支える「サラメシ」
ヤマロク醤油の5代目・山本康夫さんは、市場にわずか1%しか出回らない木桶仕込みのしょうゆを作るため、日々忙しく働いています。特に冬のこの時期は仕込みの最盛期で、朝5時30分から準備体操をし、重労働に備えます。醤油麹を運び、桶に投入する作業、発酵を終えたもろみをゆっくりと搾る作業など、体力を使う仕事が続くため、休憩時間の食事はとても大切な時間です。
そんな山本さんと従業員の食事の場となっているのが、蔵のそばにある一軒家の休憩所。2年前に空き家を購入し、従業員の休憩場所として活用することにしました。醤油作りは屋外作業も多く、夏は暑く、冬は寒さが厳しいため、落ち着いて食事ができる場所が必要だったのです。
- 購入した空き家を休憩所に改装
- 仕事の合間にゆっくり食事ができる環境を整備
- 忙しい作業の合間でも、ほっと一息つける大切な空間
山本さん自身の昼ごはんは、朝ご飯の残り物。朝、子どもたちのために作った食事の残りをそのまま食べることが多いそうです。
- 朝食は家族が食べるためにしっかり用意
- 子どもたちが食べ終わった後の残りをそのまま昼食に
- 無駄なく食べることで、食材を大切にする気持ちも
木桶しょうゆ作りは時間と手間がかかる伝統製法。木桶職人の減少という課題にも直面する中、自ら木桶を作ることを決意し、技術を学びながら新たな挑戦を続けています。そんな中でも、家族との時間を大切にし、毎日の食事をしっかり摂ることが、山本さんの活力になっています。
従業員とともに食事をとることで、仕事の合間のリラックスした時間にもなり、醤油作りに欠かせないチームワークを育む場にもなっています。何気ない日常の食事が、伝統を守り続ける職人たちのエネルギーを支えているのです。
引退を迎えたドクターイエローT4編成と検測員の最後の仕事

新幹線の線路や架線の状態をチェックするために走っていた「ドクターイエロー」T4編成が、2025年1月に引退しました。2001年から約24年間にわたり、新幹線の安全を支えてきた特別な車両です。走行するだけでなく、架線や軌道のわずかな異常を発見し、早期の修理を促す役割を果たしてきました。特にT4編成は、JR東海が運用する唯一のドクターイエローであり、東海道新幹線の安全運行を陰で支えてきた存在でした。
この車両には、「検測員」と呼ばれる専門技術者が乗務し、運行中にさまざまなデータを収集・解析していました。検測は非常に高度な技術を要する作業で、走行中にリアルタイムで異常を発見し、即座に記録する能力が求められます。
-
検測員の仕事内容
走行中に専用の測定機器を使い、架線の高さや電圧、軌道のゆがみなどを詳細に調べます。特に架線の位置がわずかにずれているだけでも、新幹線の走行に影響を与えるため、1ミリ単位の誤差を検出するほどの高い精度が求められます。もし異常が見つかれば、すぐに記録し、そのデータをもとにメンテナンス計画を立てることが重要な仕事です。 -
走ることで安全を守る特別な車両
ドクターイエローは「新幹線のお医者さん」と呼ばれるほど、重要な役割を担ってきました。一般の乗客を乗せず、運行ダイヤに合わせて走りながら検測を行い、新幹線の安全を見守っていました。T4編成は、約10日に1回のペースで走行し、東海道・山陽新幹線のすべての線路をくまなく検査していました。 -
引退前の最後の検測
T4編成の最後の検測には、長年この車両に乗り続けたベテラン検測員たちが乗務しました。彼らにとって、ドクターイエローは単なる車両ではなく、共に日本の鉄道を支えてきた「相棒」とも言える存在でした。最後の走行中も、いつも通り真剣にデータを測定し、少しの異常も見逃さないよう慎重に作業を続けました。 -
鉄道ファンの注目を集めた引退
ドクターイエローは、その珍しさと黄色いボディから「見ると幸せになれる」と言われ、多くの鉄道ファンに愛されてきました。そのため、T4編成の最後の走行では、多くの人が沿線に集まり、カメラを構えてその勇姿を見送りました。最後の検測を終えた後、車庫へ戻るT4編成を見守る検測員たちの姿には、長年の感謝と誇りが込められていました。 -
これからの検測技術の進化
T4編成の引退後、JR東海ではN700S営業車に検測装置を搭載することで、今後も新幹線の安全運行を支える計画を進めています。技術の進歩によって、営業運転をしながら検測が可能になることで、さらに効率的に安全確認ができるようになります。しかし、これまでドクターイエローが果たしてきた役割や、検測員たちの誇りある仕事は、鉄道史において重要なものとして語り継がれるでしょう。
T4編成の引退は一つの時代の終わりを意味しますが、検測員たちはこれからも新たな技術を活用しながら、新幹線の安全を守り続けます。ドクターイエローの黄色い車体はもう見られなくなりますが、その精神は変わることなく未来へと受け継がれていくのです。
引退直前のドクターイエロー検測員・田中さんの最後のサラメシ
ドクターイエローの検測員として長年活躍してきた田中さん。新幹線の安全を支える大切な役割を果たしてきましたが、ついに引退の日を迎えました。その最後の乗務で食べたランチが、おにぎり弁当でした。
測定作業中は、新幹線が通常の営業列車とほぼ同じ速度で走行しているため、モニターを常に監視しながら異常がないかを確認しなければなりません。そのため、食事をとる時間も限られており、乗務前の10時30分に早めの昼食をとるのが日常でした。
- 普段はコンビニのおにぎりを簡単に食べるだけ
- この日は引退を前に、ちょっと奮発して「おにぎり弁当」
- 短時間で食べられるおにぎりは、乗務員にとって理想的な昼食
測定が始まると、モニターを見続けるため、ゆっくり食事をする余裕はありません。安全運行を守るため、食事の時間もシンプルで効率的に過ごしていました。
普段、乗務がない日は社員食堂の定食や自作の弁当を食べることもあったそうですが、ドクターイエローに乗務する日は、手軽に食べられるものが基本でした。
そして、最後の仕事を終えて新大阪駅に到着。**長年支えてきたドクターイエローの業務を無事に終えました。その日の夜は、同僚たちとともに「お疲れ様会」**を開き、これまでの思い出を語り合いながら食事を楽しみました。
- 長年の感謝を込めた「お疲れ様会」
- 普段はなかなかゆっくり食べられなかったため、この日は特別な食事を
- 鉄道に関わる仕事を続けられたことへの満足感と寂しさも
ドクターイエローの引退とともに、田中さんの検測員としての役目も終わりましたが、長年支えてきた新幹線の安全は、これからも受け継がれていきます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


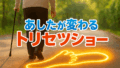
コメント