菊池晋作シェフ直伝!香ばし油淋鶏とベチャ防止の春野菜炒めテク
2025年4月21日(月)放送のNHK『きょうの料理』では、調理師専門学校の講師でもある菊池晋作さんが登場。「シェフのON&OFFごはん」というテーマのもと、家庭でもプロの味を再現できる2品を紹介します。番組で取り上げられたのは、カリッと香ばしい仕上がりが魅力の「油淋鶏(ユーリンチー)」と、春野菜とえびを組み合わせた「えびと春野菜の中華炒め」です。
どちらの料理も、手に入りやすい食材とシンプルな手順で、失敗しがちなポイントをしっかりカバーしてくれるレシピになっており、炒め物が水っぽくなる、揚げ物がベチャつくといった悩みを解消するヒントがたっぷり詰まっています。
番組で紹介される2品の材料と作り方を、それぞれ丁寧に解説していきます。
油淋鶏(ユーリンチー)の魅力と特徴

中華料理の定番ともいえる油淋鶏は、揚げたての鶏もも肉に、しょうがやたまねぎの香味たっぷりの甘酸っぱいたれをかける料理です。揚げたてのパリッとした食感と、たれのさっぱりした味わいが特徴で、家庭料理としても人気です。
材料(2人分)
【主な材料】
・鶏もも肉:1枚(約250g)
・しょうゆ・酒:各大さじ1(下味用)
・片栗粉:適量
・揚げ油:深さ2cm程度
・サニーレタス:適宜
【たれ(作りやすい分量)】
・たまねぎ:1/4個(約50g)※7mm角に切る
・しょうが(みじん切り):1かけ分
・しょうゆ・砂糖・酢・水:各大さじ2
・顆粒チキンスープの素(中華風):小さじ1
・ごま油・オリーブ油:各小さじ1
・オイスターソース:小さじ1/2
・こしょう:少々
※たれは清潔な保存容器に入れて冷蔵庫で約3日間保存可能です。唐揚げや白身魚のフライ、冷奴やサラダにも活用できます。
作り方
【1】たれを作ります。たまねぎは7mm角に切り、しょうがのみじん切りとともにボウルに入れます。残りのたれの材料もすべて加えて、よく混ぜてなじませます。時間に余裕があれば、使う前に少し置いておくと辛みが和らぎ、よりまろやかになります。
【2】鶏肉は皮を下にして置き、包丁のあごの部分で筋全体を細かくたたいて切り込みを入れます。火の通りを均一にし、縮みを防ぐための大切な下処理です。しょうゆと酒をまぶして、10分ほど置いて下味をしっかりしみこませます。
【3】バットに片栗粉を広げて、鶏肉全体にたっぷりまぶします。衣が厚すぎないように、余分な粉はしっかりとはたき落とすのがポイントです。
【4】深めのフライパンに油を2cmの深さまで注ぎ、中火にかけます。油が約120℃に温まったら、鶏肉を皮を下にしてそっと入れます。1分後に色づいてきたら上下を返し、その後も5〜6回ほど繰り返し返しながら、7〜8分かけて揚げます。途中、鶏肉を油の中で軽く動かすことで、均一に火が通り、カリッと仕上がります。
【5】油の音がパチパチと激しくなり、大きな泡が立ち始めたら揚げ上がりの合図です。網に取り出して油を切り、食べやすく切って器に盛ります。サニーレタスを添えて、上からたれをたっぷりとかければ完成です。
えびと春野菜の中華炒め

えびと春野菜の中華炒めは、炒め物特有の“水っぽさ”を解消するテクニックが光る一品。あらかじめ調味料をからめておくことで、火にかけたときに水分が出すぎず、シャキッとした仕上がりが実現します。
材料(2人分)
・えび(無頭・殻付き):10匹(約200g)
・ゆでたけのこ:1/2本(50g)
・ブロッコリー:1/4個(35g)
・スナップえんどう:6本(30g)
・にんじん:1/4本(25g)※薄い半月切りまたはいちょう切り
・グリーンアスパラガス:1本(20g)※根元の皮をむいて斜め切り
・ねぎ(白い部分):1/3本(20g)※小口切り
・にんにく・しょうが:各1かけ分(薄切り)
【A(調味料)】
・酒(あれば紹興酒)・ごま油:各大さじ1
・顆粒チキンスープの素(中華風):小さじ1
・しょうゆ:小さじ1/3
・オイスターソース・塩:各小さじ1/4
・砂糖:1つまみ
・こしょう:少々
作り方
【1】野菜は食べやすい大きさに切りそろえます。ブロッコリーは小房に、たけのこは4mmの縦切り、アスパラは斜め切りにします。スナップえんどうは筋を取り、にんじんは薄切りにします。
【2】えびは殻をむいて背ワタを取り除き、下処理を済ませます。
【3】ボウルにカットした野菜、えび、にんにく、しょうが、ねぎを入れ、混ぜておいたAの調味料を回しかけ、火にかける前によくなじませます。
【4】フライパンに③を広げ、強めの中火で加熱します。最初は触らずに表面に焼き色をつけるようにし、色が変わってきたら全体をザックリ混ぜて炒めます。
【5】炒めながら水分を飛ばすようにし、3〜4分加熱します。仕上げに具材に軽く焼き色がつき、汁気がほぼなくなったら火を止めて完成です。
まとめ
どちらの料理も、ちょっとした下ごしらえや手順の違いが、仕上がりの大きな差を生むポイントになっています。家庭でも実践しやすいコツが紹介されているので、放送を見ながらその技をしっかり学び、料理の腕をワンランクアップさせるチャンスです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

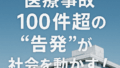

コメント