家族の食卓を救った“白い希望” クリームシチュー誕生に込められた「子どもたちを守りたい」という想い
寒い季節になると、食卓に並ぶ定番メニュー『クリームシチュー』。湯気とともに立ちのぼるやさしい香り、具材を包み込むとろりとした白いソース――誰もがほっとするこの料理には、実は“命をつなぐ物語”が隠されています。
2025年10月24日放送の『チコちゃんに叱られる!』では、「クリームシチューはなんでできた?」という素朴な疑問から始まり、戦後の日本を支えた一人の新聞記者の行動と、食文化の誕生にまつわる深い人間ドラマが紹介されました。この記事では、番組の内容をもとに、クリームシチューがどのように生まれ、なぜ“日本人の心に残る味”になったのかを詳しく紐解きます。
一人の日本人が動かした“命のリレー”
チコちゃんの答えは「アメリカにいた一人の日本人が日本の子どもたちを救いたいと思ったから」。
その人物こそ、戦前からアメリカで新聞記者として活動していた浅野七之助さんです。彼は日本の敗戦を遠い地から見つめながら、祖国の厳しい現状を報じ続けていました。1945年の終戦後、日本はまさに「飢えの国」と化していました。食料の生産は落ち込み、農地は荒廃し、兵士の帰還や都市の焼け跡が重なり、国民の多くが栄養失調に苦しむ時代。特に、育ち盛りの子どもたちが最も深刻な被害を受けていたのです。
浅野さんは、新聞の紙面で“日本の飢餓”を訴えました。アメリカに住む日本人や現地の市民、宗教団体に向けて「母国の子どもたちが命を落としている。どうか手を差し伸べてほしい」と呼びかけたのです。
この呼びかけが火種となり、在米日本人の間で支援の輪が広がりました。寄付金が集まり、米国の教育団体や教会も次第に協力を申し出るようになります。こうして始まったのが『日本戦災難民救済運動』でした。
半年後、ついに日本への第一便が出発します。その量はなんと約9万5千キロの食料。小麦粉、砂糖、豆類、衣料、そして――『脱脂粉乳』。これらは“ララ物資(LARA物資)”と呼ばれ、のちに日本政府やアメリカ政府をも巻き込む国際的な支援プロジェクトへと発展していきました。
“まずい粉ミルク”をおいしく変えた母たちの工夫
ララ物資の中でも、当時特に印象的だったのが『脱脂粉乳』です。アメリカでは戦時中の栄養補給食品として広く使われていましたが、独特の香りと味が日本人の口には合わず、子どもたちからは「においが苦手」「飲みたくない」と不評でした。
しかし、戦後の給食ではこの粉ミルクを使わざるを得ません。栄養価は抜群でも、まずくては意味がない。現場の調理員や家庭の母たちは、子どもたちに少しでもおいしく食べさせようと知恵を絞りました。
牛乳の代わりに使い、野菜を煮込んでとろみをつけ、バターや小麦粉を混ぜ合わせてスープにした――これこそが、今の『クリームシチュー』の原型となった料理でした。
食文化研究家の畑中三応子さんによれば、当時の白いシチューは「おいしくない脱脂粉乳を、子どもたちが笑顔で飲めるように工夫した“愛情の料理”」だったそうです。
つまり、クリームシチューは“食べるための工夫”からではなく、“子どもを救うための工夫”から生まれた料理だったのです。
ララ物資が残した“支援の文化”
ララ物資は6年間にわたって続きました。学校や施設に送られた粉ミルクや缶詰、衣料は、戦後の人々の命を支えただけでなく、日本に「食で人を助ける」という文化を根づかせました。
それまでの日本には“支援の食文化”という概念はほとんどありませんでしたが、ララ物資の経験は後の給食制度や社会福祉の基盤となり、クリームシチューのような“やさしい食事”が家庭料理として広まっていくきっかけにもなりました。
また、脱脂粉乳の改良は国内の食品メーカーにも影響を与え、やがて“ホワイトソース文化”が生まれます。1960年代にはハウス食品やグリコなどが「クリームシチュールウ」を開発し、粉末をお湯に溶かすだけで誰でも作れるようになりました。これによって、シチューは“特別な料理”から“家庭の定番”へと変化していきます。
白いシチューが伝える“ぬくもりの記憶”
クリームシチューが日本人にとって特別なのは、味だけでなく“背景にある物語”が温かいから。
戦後の苦しみを乗り越えようとした大人たちの知恵、遠い国から助けの手を差し伸べた人々の優しさ、そして何より“子どもたちの笑顔を守りたい”という共通の願い。それらがひと皿の中に溶け込んでいるのです。
今、私たちが寒い夜に食べるシチューの温かさは、ただの温度ではなく「想いのぬくもり」。
浅野七之助さんの小さな行動が、やがて多くの人を動かし、数えきれない命をつなげたように、ひとりの思いやりが世界を変えることを、この料理は静かに教えてくれます。
現代に受け継がれる“支え合う食卓”
現代では、クリームシチューは季節を問わず愛される定番メニュー。スーパーの棚に並ぶルウやレトルトスープ、学校給食の献立にも欠かせない存在になりました。
栄養バランスがよく、子どもから高齢者まで食べやすいこともあり、災害時の非常食としても注目されています。粉ミルクのように保存がきく材料を活かして、被災地で提供される温かいスープ――それは、まさにララ物資が伝えた「食で支える」という理念の現代版といえるでしょう。
この記事のまとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・クリームシチューは、戦後の食糧難の中で“子どもを救いたい”という願いから生まれた料理。
・発端はアメリカの記者浅野七之助が立ち上げた「日本戦災難民救済運動」。これがララ物資となり、脱脂粉乳が“白いシチュー”の原点となった。
・今日のクリームシチューは、支援と希望の象徴。やさしい味の裏には「人を思う力」が息づいている。
食卓に湯気が立ちのぼるたびに、どこか懐かしい気持ちになる――。
その“懐かしさ”の中には、過去に誰かが守り抜いた命と、今を生きる私たちへの温かいバトンがあるのです。
次にシチューを食べるとき、少しだけ目を閉じてみてください。その白い一皿の奥に、きっと“やさしさの記憶”が静かに広がっています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

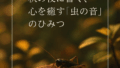
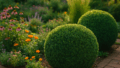
コメント