なぜハンコは赤いのか?知られざる日本文化の秘密
私たちが日常生活で使う『ハンコ』。宅配便の受け取りや契約書の署名の代わりなど、押すたびに赤い印影が残りますよね。けれど、よく考えてみると「なぜ赤色なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?黒や青ではなく、赤が主流になったのには、歴史や文化、そして実用的な理由が深く関わっているのです。この記事では、その背景をわかりやすく掘り下げていきます。
赤は“永遠”を意味する色だった
ハンコに赤色が使われる背景には辰砂(しんしゃ)という特別な鉱物の存在があります。辰砂は硫化水銀から成る鉱石で、古代から強烈な赤色を放つことで知られていました。その色は血のように鮮やかで、さらに土に混じっても色あせることがなく、時間が経っても消えにくい特性を持っていました。この性質から、人々は辰砂を「永遠を象徴する鉱物」と考え、命の循環や再生の力を表すものとして扱ってきたのです。
赤は古来より命の象徴とされ、人の血や生命力と結びつけられてきました。祭祀や葬送の場でも辰砂が用いられ、死者の周りに撒かれることで「永遠に続く存在」となると信じられていました。そのため、辰砂は単なる顔料以上の意味を持ち、人々の精神文化や信仰と深く関わっていたのです。
大阪芸術大学の久米博士も、こうした辰砂の特性と信仰がハンコに赤色を使う背景となったことを指摘しています。古代人にとって赤は特別な色であり、権威や正当性を示すために欠かせない存在でした。のちに中国の皇帝や日本の権力者たちが朱印として用いたのも、この「永遠」と「生命力」を象徴する辰砂の赤に特別な力が宿ると信じられていたからなのです。
中国での歴史と日本への伝来
中国の歴史書である北斉書には、官僚の陸法和が皇帝に宛てた文書へ朱印を押したという記録が残されています。このことから、すでに当時の中国では赤い印章が単なる装飾ではなく、公的な証明として正式に用いられていたことが分かります。朱印を押すという行為は、皇帝からの命令や許可を裏付ける強力な権威の証であり、赤色そのものが力と永続性を象徴するものとして信じられていました。
やがてこの文化は7世紀頃に日本へと伝わりました。奈良時代や平安時代には、朝廷が発行する土地の支給や税に関する公文書に赤い印が押されるようになり、朱印は国家の公式な証明手段として広く根付いていきました。当時の正倉院文書などにも朱印が確認でき、すでに制度として確立していたことがうかがえます。
さらに時代が進み、戦国時代に入ると、朱印は武将たちの権威を示す重要な手段となりました。武田信玄や織田信長など名だたる戦国大名は、自らの命令や約束を朱印状という形で発行し、家臣や領民に対して権力を示しました。朱印は単に赤色で押す印ではなく、「この印が押されている以上は絶対である」という強い意味を持っていたのです。こうして朱印は、中国から伝わった文化が日本独自の歴史と融合し、権威の象徴として長い間受け継がれていきました。
江戸から明治へ、商人や庶民にも広がる
江戸時代になると、朱印は武士だけでなく町人や商人の間にも広がり、日常生活や経済活動の中で欠かせない存在となりました。当時の社会では商取引や契約の証明に印判が多用されるようになり、庶民にとっても印鑑を持つことが当たり前になっていきました。これにより、朱印は権威の象徴というだけでなく、実用的な「信用の証」としての役割を果たすようになったのです。
しかし、古代から使われていた辰砂(しんしゃ)は非常に高価で希少な鉱物であり、一般庶民が手にすることは難しいものでした。そこで代用品として登場したのが酸化鉄を原料とした朱肉です。酸化鉄は安価で入手しやすく、しかも赤色が鮮明で長く残るという利点があったため、商人や庶民の間で一気に普及しました。この酸化鉄の朱肉は、印影が時間を経ても残りやすく、実用性に優れていたため、現代の朱肉にもその技術が受け継がれています。
そして時代は明治へ移り、明治4年(1871年)には新たに印鑑登録制度が導入されました。これは政府が近代的な行政制度を整備する一環として始まったもので、全国民が印鑑を公的に登録し、法的効力を持つ証明として活用できるようになったのです。この制度により、朱印は全国規模での統一的な文化となり、「契約や公文書には赤い印鑑を押す」という習慣が完全に定着しました。
こうして江戸から明治にかけての変化を経て、現代にまで続く「ハンコは赤」という常識が形づくられました。赤い印影は単なる慣習ではなく、長い歴史の中で育まれ、信頼と権威の象徴として受け継がれてきたものなのです。
現代の朱肉と赤色の理由
現在の朱肉には、古代から用いられてきた辰砂(しんしゃ)ではなく、酸化鉄を主成分とする顔料が使われています。酸化鉄による赤色は非常に安定しており、長い年月が経っても変色や退色が少ないため、押された印影が鮮明に残り続けます。この特性が、公的な契約書や役所での手続きなど、長期間保存される文書に適している大きな理由となっています。
意外なことに、日本の法律で「朱肉は必ず赤でなければならない」と定められているわけではありません。理論的には黒や青でも使用は可能です。しかし実際には、赤色が最も視認性が高く、ほかの文字や署名と明確に区別できるため、自然と赤色が主流となっていきました。特に複写式の書類や薄い和紙などでは、赤の印影がはっきりと残ることが重視されてきたのです。
このように、赤い印鑑は単なる慣習ではなく、長い歴史的背景と実用性の積み重ねによって選ばれ続けてきた色です。古代の辰砂から始まった「永遠を残す赤」という象徴性と、近代以降の酸化鉄による耐久性と鮮明さ。この二つが結びついた結果として、現代の「ハンコは赤」という常識が形成され、今も私たちの生活に息づいているのです。
まとめ:ハンコの赤色が持つ意味
この記事で紹介したポイントを整理します。
-
ハンコの赤は辰砂に由来し、「永遠」を意味する特別な色だった
-
中国の北斉書に朱印の記録があり、日本には7世紀頃に伝わった
-
江戸時代には庶民にも広がり、明治4年の印鑑登録制度で全国に普及した
-
現代の朱肉は酸化鉄を使用し、長持ちする実用的な赤が主流になっている
つまり「ハンコ=赤」という常識は、信仰・歴史・実用性の3つが結びついた結果なのです。次に朱肉に印を押すとき、そこに込められた“永遠”の意味を思い出してみてはいかがでしょうか。
出典:
NHK総合「チコちゃんに叱られる!」2025年10月3日放送
NHK公式サイト
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

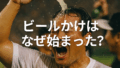
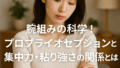
コメント