早口ことばのルーツは“のど薬”!?あの名台詞『外郎売』に隠された物語
「生麦生米生卵」や「赤巻紙青巻紙黄巻紙」など、一度は挑戦したことのある“早口ことば”。噛まずに言えると気持ちいいけれど、そもそもどうしてこんな言葉遊びが生まれたのでしょうか?実はそのルーツ、まさかの“のど薬”にあったのです。
2025年10月10日放送の『チコちゃんに叱られる!』では、渋谷凪咲と澤部佑が挑戦しながら、清泉女子大学の今野真二教授がその歴史を楽しく解説。笑いと驚きが交錯した生放送回となりました。この記事では、早口ことばがどのようにして生まれ、人々に広まっていったのか――そして、あの歌舞伎演目『外郎売(ういろううり)』との深い関係を紹介します。
江戸の名優・市川團十郎がのど薬で救われた日
番組のチコちゃんからの質問は、「なぜ早口ことばを言うようになった?」というもの。
渋谷凪咲の答え「早くしゃべる人の方が賢そうに見えるから」という可愛らしい発想に、スタジオは笑い声に包まれました。しかし、チコちゃんの「ボーっと生きてんじゃねーよ!」のひと叱りとともに発表された正解は――「市川團十郎がのどの薬で救われたから」。この答えに、出演者たちは一斉に「まさか!」と驚きの表情を見せました。
この逸話の主人公は、江戸時代に活躍した歌舞伎役者、二代目・市川團十郎(1688〜1758年)。荒事を得意とする勇壮な演技で人気を博し、江戸歌舞伎の黄金期を築いた人物です。
しかしその華やかな舞台裏では、激しい演技と声の酷使から、常に“のどの不調”と闘っていたといわれています。そんな彼を救ったのが、「外郎(ういろう)」と呼ばれる漢方薬。
この“ういろう”は、今の名古屋名物「ういろう(外郎)」とはまったく別物で、もともとは鎌倉の外郎家(ういろうけ)が中国から伝えた薬です。
生薬を調合した万能薬で、のどの痛み、咳、痰、声枯れなどに効能があるとして当時の役者たちの間で重宝されていました。
團十郎もその恩恵を受けた一人。声が回復した感謝を舞台で表現しようと考え、薬の効能を華やかに紹介する口上を演じることにしたのです。
これが後に歌舞伎十八番のひとつとして知られる名作『外郎売』の誕生につながりました。
『外郎売』が生んだ“滑舌の芸術”
『外郎売』の口上は、まさに早口ことばの原型です。
薬を売り歩く商人が、商品の効能を滔々と語る――そのセリフは5分以上にも及び、息継ぎのタイミングすら難しいほどの長台詞。
「拙者親方と申すは、お立ち会いの中にご存知のお方もございましょうが…」という冒頭から始まり、テンポよく、流れるように続く文句は、当時の観客を圧倒したといいます。
今野真二教授によると、『古事記』や『日本書紀』にも音の響きを楽しむ“言葉遊び”の記述がすでに見られます。
ただし、それが一般庶民に広がったのは江戸時代に入ってから。歌舞伎が庶民の娯楽として定着し、舞台のセリフや口上が人々の話題になる時代に突入していたのです。
そこに現れたのが團十郎の『外郎売』。
滑らかで力強い発声、美しいリズム、テンポの良い言葉運び――そのすべてが観客の心をつかみました。
やがて、町人たちはその口上を真似して遊び、次第に“誰が噛まずに言えるか”という競い合いが始まります。これこそが、現在の「早口ことば」の直接的なルーツとされているのです。
チコちゃんも笑った!生放送での“滑舌チャレンジ”
今回の放送では、そんな歴史を紹介するだけでなく、スタジオでも“生チャレンジ”が行われました。
澤部佑と渋谷凪咲が実際に『外郎売』の一節を暗唱しようとするも、途中で噛んでしまい大爆笑。
生放送という緊張感の中で挑戦する2人の姿に、観客も思わず微笑んでしまう温かい空気が流れました。
岡村隆史も「これはムリやな!」と笑いながらコメント。
生放送ならではの“噛みながらも前に進む”人間味あふれるチャレンジは、まさに『外郎売』の精神そのもの。
笑いの中にも、声を使う芸へのリスペクトが感じられるシーンとなりました。
早口ことばが受け継がれてきた理由
『外郎売』の影響は、江戸の娯楽を超えて現代にも続いています。
今ではアナウンサーや声優、俳優、ナレーターを目指す人たちにとって、『外郎売』の暗唱は発声練習の定番。
呼吸、滑舌、間の取り方、声の響き――そのすべてを鍛える教材として高く評価されています。
実際に、国立国会図書館や東京都立中央図書館には、『外郎売』の写本や口上資料が保管され、歌舞伎座では定期的に若手役者が練習演目として挑戦しています。
また、現代のアナウンサー養成校やボイストレーニング教室でも、『外郎売』の一節を取り入れる授業が行われています。
早口ことばが単なる遊びではなく、“声の芸術”として今も息づいている証拠です。
この記事のポイント
・早口ことばの起源は、歌舞伎の演目『外郎売』にあった
・二代目・市川團十郎が、のど薬「外郎(ういろう)」に救われたことがきっかけ
・江戸庶民が團十郎の口上を真似したことで、早口ことばが広まった
・今でもアナウンサーや声優の発声練習で『外郎売』が使われている
・チコちゃんの生放送では、渋谷凪咲と澤部佑の“滑舌チャレンジ”が大爆笑を呼んだ
まとめ
早口ことばは、単なる“遊び”ではなく、声を通じて文化が受け継がれてきた証。
清泉女子大学の今野真二教授が語ったように、その背景には、江戸の舞台文化、薬の効能への感謝、そして人々のユーモアが息づいています。
のど薬が芸を生み、芸が文化を広め、文化が現代の教育にも生き続ける――それが「早口ことば」という日本独自の言葉の美学です。
次に友達と早口ことばで盛り上がるときは、ほんの少し『外郎売』の舞台を思い出してみてください。
笑いながら、江戸の粋を感じるはずです。
(ソース:NHK総合『チコちゃんに叱られる!』2025年10月10日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

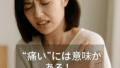
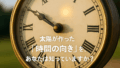
コメント