電車の車掌さん、なぜあのしゃべり方?その理由を知ったらもっと好きになる!
「車掌さんのアナウンスって、なんであんな独特な声なの?」と思ったことはありませんか?
駅でよく耳にするあの鼻にかかった声。ちょっとマネしてみたくなるけれど、どうして全国どの電車でもあの話し方が共通しているのか、不思議ですよね。
「もしかして決まりがあるの?」「あれは演出?」と感じた方も多いはず。
実はあの話し方には、乗客の安全を守るための科学的な理由が隠されているんです。
この記事では、2025年11月8日放送の『チコちゃんに叱られる!』で紹介された内容をもとに、
・なぜ車掌さんはあの話し方をするのか
・どんな歴史から生まれたのか
・現役の車掌さんたちがどんな思いでアナウンスしているのか
を、わかりやすく紹介していきます。
読めば、いつもの電車のアナウンスが少し違って聞こえるかもしれません。
NHK【鉄オタ選手権 西武鉄道の陣・第二戦!】特急レッドアロー号が激レアルートへ!小田急車両の西武移籍が意味する“鉄道の未来”とは|2025年10月13日
騒音の中でも聞き取れる声――その正体は「鼻腔共鳴」
まず結論からいうと、車掌さんがあのように話す理由は、「騒音を避けるため」です。
解説してくれたのは、長年車内放送システムを支えてきた車内放送装置メーカーの山本さん。
電車は走行中、モーター音や車輪とレールの摩擦音、風切り音などが常に響いています。特にトンネルや高架線では音が反響し、車内の騒音レベルは会話が聞こえにくいほどの大きさになります。
そのため普通に話しても声がかき消され、乗客には届きません。
そんな中で生まれたのが、鼻にかかったような「鼻腔共鳴」という発声法。
鼻の奥や口腔内に声を響かせることで、高音域の音を多く含む声が出やすくなり、低音の騒音に埋もれにくくなるのです。
たとえば人の耳は3000Hz前後の高音を最も敏感にキャッチします。電車の騒音は200〜1000Hzほどが多いため、その上の帯域を使う声のほうが通りやすい。
つまり、車掌さんの「鼻声」は、物理的に“聞こえやすくするための設計された声”なのです。
1951年の事故がきっかけ 車内放送の歴史
この発声法が定着する背景には、1951年に発生した列車火災事故があります。
当時はまだマイク設備が整っておらず、非常時に車掌の声が乗客に届かず、避難誘導が遅れたという痛ましい出来事でした。
この教訓から、「車掌の声を全員に確実に届ける仕組みを」と、鉄道各社で車内放送装置の整備が始まります。
1960年代になると技術が進歩し、スピーカーを通して均一に聞こえる車内放送が実現。
停車駅の案内や安全確認もマイクで行われるようになりました。
ただ、どれだけ機械が発達しても、電車の騒音そのものは避けられません。
そこで「どうすれば騒音の中でも伝わるか?」を研究した結果、自然と鼻に響かせる話し方が広まりました。
山本さんによると、当時は正式な研修マニュアルが存在せず、ベテラン車掌の声を聞いて真似することで受け継がれていったそうです。
こうしていつの間にか、日本全国どの鉄道会社でも共通する“あの声”が定着したのです。
誰が最初に始めた?全国52社に聞いても謎のまま
番組では、全国52の鉄道会社を取材。
結果は驚くべきもので、「誰が最初に始めたのかは不明」という答えでした。
どの会社も「特別に指導していない」「自然とそうなっている」と回答。
それでも共通していたのは、「お客様に聞き取りやすく伝えることを第一に考えている」という姿勢でした。
この言葉の背景には、鉄道員たちの使命感があります。
どんなに混雑しても、どんなに走行音が響いても、情報を正確に伝えるのが車掌の責任。
その思いが、無意識のうちに全国の鉄道で同じリズムと音色を生んでいったのです。
現場を支える鉄道たち 地域ごとの特色も紹介
今回番組に登場したのは、ひたちなか海浜鉄道(茨城県)、愛知環状鉄道(愛知県)、そして富士山麓電気鉄道(山梨県)。
どの鉄道も地元の人々の足として親しまれています。
たとえば、富士山麓電気鉄道では観光列車の運行も多く、アナウンスの声には「旅の雰囲気を壊さない温かみ」を意識しているそうです。
一方、愛知環状鉄道では朝夕の混雑時にもはっきり聞こえるよう、発音を短く区切るトレーニングを行っているとのこと。
地域の特性や乗客層に合わせて、話し方を少しずつ調整しているのも面白いところです。
お笑いと鉄道愛の融合 中川家・礼二さんの登場
さらに番組には、鉄道ファンとして知られる中川家の礼二さんも登場。
全国の車掌ボイスを完璧に再現する“車掌モノマネ”でおなじみですが、礼二さんも「やっぱり鼻に響かせると伝わりやすい」と語っていました。
礼二さんは地方路線ごとのアクセントの違いまで分析しており、関東と関西では抑揚の付け方が微妙に違うことも紹介。
このあたりの細かい解説は、鉄道ファンにはたまらないシーンでした。
声の文化としての“車掌ボイス”
鉄道のアナウンスは、もはや「音の文化」といってもいい存在です。
聞き取りやすさ、安心感、旅情――そのすべてが融合して、ひとつの“音風景”を作り出しています。
科学と感性の間で磨かれてきたこの声は、鉄道が積み重ねてきた信頼と安心の象徴。
マニュアルではなく、人の経験と心で受け継がれてきた「日本の音」なのです。
たとえAI放送や自動アナウンスが主流になっても、この独特の声には人の温かみがあります。
機械の正確さと人の感性が共存する“車掌ボイス”は、これからも日本の鉄道文化を支えていくことでしょう。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・車掌さんの独特なしゃべり方は、騒音を避けるために生まれた科学的発声法である
・1951年の列車火災事故をきっかけに、車内放送装置が全国に導入され、鼻腔共鳴の声が広まった
・全国の車掌が共通して「お客様に伝わる声」を追求した結果、自然に同じ話し方が根付いた
あの独特なトーンの裏には、70年以上にわたる安全への努力と工夫が詰まっています。
次に電車に乗ったとき、アナウンスの声をじっと聞いてみてください。
その一言一言に込められた“伝える技術”と“人の想い”が、きっと聞こえてくるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

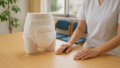

コメント