なぜ将棋の駒には「戦い」に関係のない漢字が使われているの?仏教と歴史に隠された深い理由
2025年6月13日放送のNHK「チコちゃんに叱られる!」では、「なぜ将棋の駒に“戦い”と関係ない漢字が使われているのか?」というテーマが取り上げられました。将棋は戦いのゲームなのに、「桂」や「香」といった漢字が使われているのはなぜなのか。番組では日本の将棋の起源から、駒の文字に込められた意味、そして仏教との深い関係まで幅広く紹介されました。今まであまり気にしていなかった駒の文字に、意外にも日本人の精神文化や宗教観が影響していたことがわかり、知的好奇心がくすぐられる内容となっていました。
NHK【チコちゃんに叱られる!】驚くことを“目が点になる”と言うようになったのはなぜ?|2025年6月13日放送
NHK【チコちゃんに叱られる!】なぜエレベーター待ちはイライラする?|2025年6月13日放送
将棋の起源はインドの戦いのゲーム「チャトランガ」

まず将棋のルーツとして紹介されたのが、インドで生まれた「チャトランガ」という古代のボードゲームです。これは戦いを模した遊びで、象や兵、馬といった軍の要素を持つ駒を使い、敵の王を先に倒したほうが勝ちというルールでした。このチャトランガは戦争好きな王様のために作られたという伝説もあり、現在の将棋やチェス、その他の戦略ボードゲームのもとになったとされています。
チャトランガはその後、アジア各地やヨーロッパへと広まり、それぞれの文化に合わせて進化していきました。中国では象棋、ヨーロッパではチェスとして発展し、日本では独自の将棋へと形を変えていったのです。
平安時代に日本独自の将棋が生まれる

日本で将棋が定着したのは平安時代のことで、当時は現在の将棋とは違い、飛車や角行がまだ存在しない6種類の駒で行われていました。また、今では「王将」と「玉将」が両方使われていますが、当時は王将のみが使われていたといいます。
興味深いのは、多くの将棋に関する古文書や駒が、お寺で発見されているという点です。これにより、当時の将棋は僧侶や貴族など、仏教と深い関わりのある人々が主に楽しんでいたと考えられています。
仏教では争いや暴力を避けることが重んじられています。そのため、戦いのゲームである将棋に対しても、なるべく戦いのイメージを薄めようとする工夫が必要とされました。その一つが、駒に使う漢字を変えることだったのです。
「桂」や「香」は戦いを隠すための宝物の文字だった

番組では、大阪商業大学の古作登さんがこの疑問に答えていました。それによると、将棋に使われている「桂」や「香」などの文字は、仏教において“宝物”を意味する漢字だといいます。たとえば「桂」は霊木、「香」は仏前に供える香木を指し、どちらも神聖で価値あるものを意味しています。
つまり、将棋という戦いのゲームであっても、駒の名前を戦いから遠ざけることで仏教の教えに反しないように配慮したのです。このようにして、見た目には戦いの匂いを感じさせない駒が作られたと考えられています。
また、将棋のルーツであるチャトランガやチェスでは、駒の名前に兵士や戦車、騎士といった軍事用語が多く使われています。しかし、日本の将棋はこの点で大きく異なり、文化的・宗教的背景に応じた独自の進化を遂げたというわけです。
将棋は時代とともに駒が増え進化していった
将棋が単なる遊びから戦略的なゲームへと進化する過程で、より多くの駒の種類が加えられていきました。その始まりが「平安大将棋」で、駒の数は13種類。このときに生まれたのが「飛龍」という駒で、現在の角行に近く、盤の斜め方向に大きく動ける特徴を持っていました。
鎌倉時代になると、さらに「大将棋」というルールが誕生し、駒の種類は一気に29種類に増加。このときに現在も使われている飛車と角行が仲間入りしました。
さらにスケールが大きくなったのが「大局将棋」で、なんと駒の種類が200種類以上にもなります。中には「獅子」という駒のように、一回の手番で2回動ける能力を持つものも登場しました。対局にかかる時間も非常に長く、普通に対戦して3日間かかったといわれています。
このような複雑な将棋が進化する中で、もっとコンパクトに、しかも戦略性のあるゲームを目指した結果、現在の8種類の駒で構成される将棋が生まれました。そしてここで大きな役割を果たしたのが、取った駒を自分の駒として使える「持ち駒」のルールです。このルールのおかげで、少ない駒でも深い読み合いができるようになり、現代の将棋の形が完成したのです。
駒の文字にも込められた日本人の美意識
今回の放送では、将棋の表面的な遊びとしての楽しさだけでなく、駒の名前に隠された精神性や文化的な背景まで深く掘り下げられていました。戦いのゲームを楽しみながらも、その中に争いを感じさせない工夫を込めるという、日本らしい配慮と工夫が光ります。
仏教の価値観と結びつけることで、将棋がただの遊びではなく、教養ある人々の知的な娯楽として位置づけられたことも納得できます。文化や宗教と密接に関係しながら、現代まで続いてきた将棋というゲームは、日本人の精神性や歴史を象徴する存在であると改めて感じられた放送でした。
何気なく見ている将棋の駒に、ここまで深い意味があったとは思わなかった人も多いかもしれません。これから将棋を観るとき、駒の一つひとつの文字に込められた意味や背景を思い出してみると、また違った楽しみ方ができるようになるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


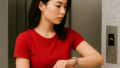
コメント