年を重ねても前向きに生きるヒント “老いへの抵抗”を和らげる方法とは
誰でも年齢を重ねるにつれて、体の変化やできないことが増えていくもの。頭では分かっていても、「まだ若いつもり」「人の世話になりたくない」と感じる瞬間、ありますよね。この記事では、2025年11月12日放送のNHK『クローズアップ現代』で紹介された「老い上手」「介護上手」の秘けつを通して、老いと上手に向き合うための実践的なヒントを紹介します。
名古屋市のユニークな取り組みや専門家の言葉、介護現場での温かい工夫まで、心が軽くなる内容が詰まっています。
NHK 【あさイチ】密着!介護の仕事 介護する時・される時に役立つヒントいっぱい ケアマネが見つからない現実と備えのコツ|2025年10月20日
“老いへの抵抗”が生まれる理由とは
番組はまず、名古屋市のある女性のケースから始まりました。彼女はサービス付き高齢者住宅に暮らしていますが、排せつが間に合わなくなることが増え、スタッフからおむつの使用をすすめられていました。
しかし、その女性は「おむつなんて病人が使うもの」と強く拒否し、スタッフの前で一度着けたおむつも後で脱いでしまうほどの抵抗を示しました。結果的にズボンが濡れてしまい、部屋に閉じこもってしまう日々が続きます。
なぜここまで「老い」を受け入れられないのか。
権藤恭之さんは、老年心理学の観点からこう語りました。
「長年、家族を支えてきた“親世代の誇り”がある人ほど、支えられる立場になることを受け入れにくいのです。自分が“支える側”から“支えられる側”へと変わることは、まるで“自分の人生が終わりに近づいている”と宣告されたような衝撃を与えるんです。」
つまり、老いを拒む気持ちは決してわがままではなく、人間の自然な感情の一つ。尊厳を保ちたいという思いの裏返しなのです。
名古屋市の取り組み “排せつの悩み”を一人にしない
このテーマを支える現場の一つが、名古屋市が6年前に設置した「排せつ専門コールセンター」。全国でも珍しいこの取り組みでは、看護師や介護福祉士が電話で無料相談を受け付けています。
「恥ずかしくて誰にも言えなかった」という高齢者の声を受け止め、使う人の生活スタイルに合ったケア方法や道具の選び方を提案。年々利用者は増え、2024年には過去最多の約1500件に達しました。
中には県外から電話をかけてくる人も多く、社会全体に“排せつ”をオープンに語れる環境がまだ整っていない現状も浮き彫りになりました。
この取り組みを支えるのが、ユニ・チャームなど民間企業との連携です。最新のおむつや排せつ支援用具の開発が進み、「できないことを補う」だけでなく、「安心して外出できる」「旅行を楽しめる」といった前向きな支援が広がりつつあります。
“老い上手”を支える言葉の魔法
一方、番組が取材した大阪府の訪問介護事業所では、全国に1000店舗を展開する企業がスタッフ研修を行っていました。
テーマは「声かけの工夫」。
介護の現場では、何気ない一言が利用者の気持ちを左右します。
「トイレに行きましょう」ではなく、「ちょっと体を動かしましょうか」「気分転換に立ちましょうか」と伝えるだけで、受け取る印象は大きく変わります。
排せつ=恥ずかしいというイメージを持つ人にとって、優しい言葉選びは心のバリアを取り除く鍵。
浦田克美さんは語りました。
「排せつケアは単に清潔を保つだけでなく、その人の“尊厳”を守るケアです。だからこそ、声かけの一言がとても大切なんです。」
こうした工夫の積み重ねが、利用者の“老いへの抵抗”をやわらげ、介護を「一緒に生きる時間」へと変えていくのです。
“生活全体”を見つめるケアの力
さらに番組では、京都府で20年以上にわたり排せつ用具のアドバイスを行ってきた女性専門家の活動も紹介されました。
彼女のアプローチは非常にユニークで、排せつだけでなく「どんな布団で寝ているか」「寝る姿勢」「趣味や職業」「性格」など、一見関係なさそうな話題まで丁寧に聞き取ります。
その理由は、「生活の中に解決の糸口があるから」。
たとえば、寝具が柔らかすぎて起き上がりにくいことが原因でトイレが間に合わない場合、マットレスを変えるだけで解決することもあるのです。
彼女は全国を回り、研修や講演で「排せつは“生きる力”の一部」と伝え続けています。人に言いづらい悩みだからこそ、専門家が“耳を傾ける姿勢”を持つことの大切さを訴えました。
権藤教授が語る “幸福な老い方”のヒント
スタジオでは、博報堂の調査と大阪大学の研究データをもとに、老いを受け入れながら幸せに生きるためのポイントが紹介されました。
-
『ポジティブワードに変換する』
「介護される」ではなく「支え合う」、「助けてもらう」ではなく「チームで生きる」と考えるだけで、心が軽くなります。 -
『自分らしい選択肢を探す』
おむつに抵抗がある人も、自分の好みに合ったデザインや素材を選べば抵抗感が減る。自分の意志を大切にすることが「老い上手」への第一歩。 -
『道具を知って活用する』
最近は薄くて快適な吸収シートや、衣服のように履けるパンツ型おむつなども登場しています。最新技術を知ることで、老いの不安を減らせます。
権藤恭之さんの調査によれば、身体機能が低下しても「幸福感が高い」と答えた人は全体の23%。彼らに共通していたのは、「自分を責めず、人に頼る勇気を持っていた」ことだそうです。
“老いを語れる社会”へ 勇気ある一歩
番組のラストでは、兵庫県尼崎市のホテルで働く60代男性のエピソードが紹介されました。
彼は仕事中に排せつの不安を抱え、おむつを使うようになりましたが、同僚に言い出せず、処理を一人で抱えていたといいます。
しかし思い切って同僚に打ち明けたところ、ホテル側は全ての男性トイレにおむつ専用のごみ箱を設置。社員が自然に受け入れる雰囲気が生まれました。
「隠す」から「共有する」へ。
その一歩が、老いを恐れない社会への道を開いています。
まとめ
この記事のポイントを整理します。
・老いへの抵抗は「支える側から支えられる側になる」心理的変化から生まれる
・介護の現場では“声かけ”や“言葉選び”が尊厳を守る重要な鍵
・排せつや介護を「恥ずかしいこと」ではなく「生きる工夫」として受け止める視点が必要
誰もがいつか老いに向き合う日が来ます。そのとき大切なのは、年齢ではなく「どう生きたいか」。
“老いを受け入れる”とは、“自分を否定しない”ことでもあります。
心と体をいたわりながら、自分らしい生き方を選ぶ——それこそが真の「老い上手」なのかもしれません。
次回の『クローズアップ現代』も、人の心に寄り添うテーマで新しい視点を届けてくれることでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

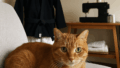

コメント