クローズアップ現代 “史上最強”日本サッカー 進む国際化の先に
2025年9月9日放送のNHK「クローズアップ現代」では、“史上最強”とも呼ばれる日本サッカーの現在地を特集しました。日本代表が過去最高の力を持つと言われる一方で、国内リーグや育成の仕組み、移籍市場の課題など、多面的なテーマが取り上げられました。番組では選手・代理人・クラブ・専門家の視点を交えながら、日本サッカーが国際化の波にどう対応しているのかを深く掘り下げています。
急増する日本人選手の海外移籍
かつては中田英寿、本田圭佑、中村俊輔といった限られたスター選手だけが海外に挑戦していました。しかし今では、ヨーロッパの舞台でプレーする日本人選手は100人以上にのぼります。驚くべきことに、その6割以上は日本代表経験のない選手たちです。つまり「代表に選ばれてから海外」という流れではなく、若手の段階で直接ヨーロッパへ渡るルートが一般化してきているのです。
ベルギーの名門アントワープへ移籍した25歳の綱島悠斗選手もその一例。東京ヴェルディでプロデビューしてからわずか2年、オファーから出発までたった4日間というスピードで海外挑戦を実現しました。
代理人の存在と変化する移籍の常識
こうした背景には、代理人の存在も大きく関わっています。番組に登場した田邊伸明氏は、2001年に稲本潤一選手をアーセナルに送り込んだベテラン。かつてはクラブの住所を調べ、選手のビデオを240本も送って返事を待つという“手探り”のやり方でした。しかし今やネットワークは世界中に広がり、彼がサポートする選手は120人以上。ヨーロッパ各国のクラブから、トップ選手はもちろん無名の若手にまで問い合わせが舞い込むようになっています。
スカウト技術の進化と日本人選手の強み
海外移籍が加速しているもう一つの理由が、スカウト技術の進化です。世界1400クラブが導入するシステムでは、69万人の選手データを条件検索し、プレー映像を瞬時に確認できます。これにより、かつてのように日本から映像を送る手間は不要になり、国境を越えて評価されるチャンスが増えました。
加えて、日本人選手の「規律」「献身性」「戦術理解力」が世界で高く評価されています。ドイツのSCフライブルクが掲げる「全員攻撃・全員守備」のサッカーには、日本人選手の特性が不可欠だとされています。
Jリーグを経ずに直接海外へ
番組では福田師王選手の例も紹介。高校時代に得点王となった彼にはJリーグ10クラブからオファーがありましたが、最終的に選んだのはドイツのクラブでした。その理由は、ヨーロッパのクラブが持つセカンドチームの存在です。若手が試合経験を積む場が整っており、成長のチャンスが広がるため、Jリーグを経由せず海外へ直行するケースが増えているのです。
地方クラブの挑戦と国際化
一方で、国内クラブも国際化を意識した取り組みを始めています。今シーズンJ1に初昇格したファジアーノ岡山は、地域密着を基本方針に掲げ、スタジアムでは「津山ホルモンうどん」や「千屋牛串焼き」といった地元グルメを提供。廃校を活用した人工芝グラウンドの整備など、地域に根差したクラブづくりを進めています。
しかし、クラブ収入の柱である広告料は頭打ち。そこで注目したのがオーストリアでのキャンプです。ここには毎年100以上のクラブが集まり、練習試合を通じてネットワークを築けるだけでなく、将来的には選手移籍の交渉や移籍金収入にもつながると期待されています。
移籍金の格差と改革の必要性
今、日本サッカーにとって大きな課題となっているのが移籍金の低さです。2025年夏の平均移籍金を比べると、ベルギーは約2億7000万円、オランダは約2億4000万円。それに対して日本はわずか4000万円。選手を育てても、十分な収益につながりにくいのが現状です。
これを改善するため、Jリーグでは欧州と同じ秋春制シーズンへの移行や、年俸上限の引き上げ、さらにはU21リーグの新設など、国際基準に近づける改革が議論されています。夏の酷暑を避けられる点でもメリットがあり、選手のコンディションや競争力向上につながると期待されています。
専門家が語る日本サッカーの未来
スタジオでは元日本代表の戸田和幸氏が「日本サッカーのレベルは確実に上がり、規律正しさが評価されている」と指摘。Jリーグチェアマンの野々村芳和氏も「日本人選手の価値は世界市場で高まっている。ビジネス構造も30年前とは大きく変わっている」と語りました。
Jリーグは1993年にわずか10クラブでスタートしましたが、今では60クラブに拡大。地域に根ざしつつ、国際市場での存在感をどう高めていくかが問われています。
2026年ワールドカップに向けて
2026年にはアメリカ・カナダ・メキシコでFIFAワールドカップが開催されます。番組の最後では「日本代表×アメリカ代表」の強化試合にも触れられ、日本が“史上最強”と呼ばれるチームとして世界に挑む準備が着々と進んでいることが伝えられました。
これまで以上に多様なルートで成長する選手たち、国際化を意識するクラブ経営、改革を進めるリーグ運営。そのすべてが重なり合って、日本サッカーは今、新たなステージへと向かっています。
出典:NHK「クローズアップ現代」2025年9月9日放送
番組公式ページ
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

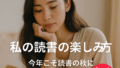
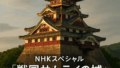
コメント