ChatGPT:
NHK【2025新春特番】日本最強の城スペシャル|冬に訪れるべき絶景城8選|松本城・犬山城・湯築城などを徹底解説【1月2日放送】
小牧山城 石垣に隠された秘密
1563年、29歳の織田信長が初めて築いたのが小牧山城です。尾張の中心に位置するこの城は、信長にとって自らの力を誇示するための重要な舞台となりました。
発掘調査の結果、この城からは信長時代の石垣が大量に出土しました。当時、城といえば山を削って土塁や堀をめぐらす「土の城」が一般的で、石を用いた築城はきわめて珍しいものでした。石垣は主に京都の寺院などで用いられていたため、地方の城に導入するのは革新的な試みだったのです。
ただし、小牧山城の石垣は後世のものと比べると高さは低く、防御力も十分ではありませんでした。それでも、石を積み上げる作業には膨大な手間と時間がかかり、土や木を使うよりもはるかに労力が必要でした。この挑戦こそ、信長の新しい城造りの姿勢を象徴しています。
さらに、最新の3Dスキャン調査によって、石垣が実際よりも高く見えるように設計されていたことがわかりました。実際の防御効果よりも「見せ方」に重点を置いた工夫で、城を見上げた敵には圧倒的な存在感を与えたのです。
この様子は、当時の記録である『信長公記』にも残されています。そこには、敵方が小牧山城を目にして「これでは勝ち目がない」と感じ、戦わずに退いたと記されています。つまり、小牧山城は単なる防御拠点ではなく、敵を心理的に打ち負かす「見せる城」の始まりだったのです。
岐阜城 黄金の瓦に秘めた経済ビジョン
美濃攻略を果たした後、織田信長が築いたのが岐阜城です。金華山の頂にそびえるこの城は、信長の天下取りの拠点となりました。
発掘調査によって、この岐阜城からは大量の瓦が出土しました。その中には、なんと金箔が施された瓦の痕跡が確認されています。城に黄金の瓦を用いるという発想は、単なる防御施設としての城を超え、権威と繁栄を示す象徴的なデザインでした。
特に、黄金の瓦は長良川沿いを行き交う人々の目に触れるものでした。川を利用して物資や人が集まる岐阜の城下町において、輝く瓦は「この地が信長の支配する繁栄の都である」という強烈なメッセージを放っていたのです。
また、信長はここで楽市令を掲げ、全国から商人を呼び寄せました。自由で活発な商業都市を築くという彼のビジョンが、城そのもののデザインに反映されていたといえます。城をただの軍事拠点ではなく、経済の中心・都市のシンボルとして用いた点に、信長の先進性が表れています。
当時日本を訪れていた宣教師ルイス・フロイスも、信長が見せる城の力とその影響力に強く注目し、記録に残しています。岐阜城は、まさに信長の政治力と経済戦略を体現した城だったのです。
旧二条城 天主に託した野望
1568年、織田信長は将軍候補として足利義昭を奉じて上洛し、その拠点として築かれたのが旧二条城です。この城は、信長が天下人としての地位を確立するための舞台であり、従来の城とは一線を画す存在でした。
近年の発掘や調査によって、城の堀跡や構造が確認され、ここに日本初の「天主」が存在していた可能性が高まっています。これまで「天守」といえば安土城が最初と考えられてきましたが、旧二条城こそがその原点であったかもしれないのです。
建設にはおよそ2万人もの人々が従事しました。その中で特に注目されるのが、「天下の名石」藤戸石を都に運び込むという演出です。信長はただ石を運ばせるのではなく、大勢の家臣たちに囃し立てさせ、人々に見せつけながら作業を進めました。これは、城造りそのものを「権威を示す舞台」として利用した、まさに大胆なパフォーマンスでした。
そして信長は、天主を室町通りのど真ん中という都の中心にそびえ立たせました。京の人々が日常の中でその姿を仰ぎ見ざるを得ない場所に築くことで、自らが天下人であることを視覚的に誇示したのです。旧二条城は、信長の戦略性と演出力が結実した、革新的な城造りの象徴だったといえます。
安土城“天下無双”の実像
1576年、織田信長は天下統一の総仕上げとして、比叡山を望む地に安土城の築城を開始しました。工事は昼夜を問わず進められ、その壮大な建設は山も谷も動くかのようだと記録に残されています。そして1581年、ついに完成を迎えました。
ここで使われた瓦は従来の和様瓦だけでなく、焼き方を工夫して赤や黒を発色させた“唐様”の瓦もあったと考えられています。当時の日本では一般的に黒一色のいぶし瓦が用いられていたため、この色彩豊かな瓦は極めて異例でした。その姿は、まるで中国の紫禁城を思わせ、信長が新時代の到来を強烈にアピールしたことを示しています。
この壮麗な城を実際に目にした宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノは、「ヨーロッパの最も壮大な城に並ぶ」と高く評価しました。さらに、信長は安土城の姿を屏風に描かせ、海外へと示したとも伝えられています。城そのものを外交のツールとして用いた点に、信長の先進性が表れています。
しかし1582年の本能寺の変で信長が倒れた直後、安土城の天守は忽然と姿を消しました。近年の発掘調査では、天守を支えていた石垣に破城の痕跡が確認されています。これは単なる焼失ではなく、あえて城を破壊する行為が行われた可能性を示しています。その背景には、後継者である羽柴秀吉が、信長の象徴を消し去るために命じたのではないか、という説も浮かび上がっています。
安土城は短命にして幻の名城となりましたが、その革新性と壮麗さは、今もなお「天下無双の城」として語り継がれています。
信長の夢を継ぐ城たち
織田信長が本能寺の変で倒れた後も、その革新的な城造りの思想は日本各地に受け継がれていきました。
近年の研究で注目されたのが、犬山城の建材調査です。使用されていた木材を年代測定したところ、1585年に伐採されたものであることが判明しました。これは、安土城が焼失してわずか3年後のことです。犬山城は規模こそ小さかったものの、外観や構造が安土城に酷似しており、信長が目指した「新しい城」の意匠を引き継いでいたことがわかります。
さらに、その流れは豊臣秀吉が築いた大阪城、そして徳川家康の江戸城へと発展していきました。石垣・瓦・天守を備えた「近世城郭」のスタイルは、信長の発想を源流として全国へと広がり、日本の城の姿を大きく変えていったのです。
信長が打ち立てた「見せる城」の思想は、単なる軍事拠点を超え、権威を誇示し、都市のシンボルとして人々を惹きつける存在となりました。その夢は後世の大名たちにも影響を与え、今も日本の歴史や文化の中で生き続けています。
まとめ
今回の放送で紹介された信長の城造りから見えてきたポイントは以下の通りです。
-
小牧山城で石垣を導入し「見せる力」で敵を威圧
-
岐阜城で黄金の瓦を用い、商業都市を築く経済ビジョンを体現
-
旧二条城で初の天主を建て、天下人の権威を視覚化
-
安土城で色彩豊かな瓦を用い、新時代を告げる象徴を完成
-
信長の思想は犬山城、大阪城、江戸城へと継承され、日本各地に近世城郭文化を広めた
織田信長が生み出した“城郭革命”は、単なる戦の拠点を超え、人々を驚かせ惹きつけるシンボルでした。この記事を読んだあなたも、次に城を訪れるとき「この城にはどんな信長の影響があるのだろう」と想像してみると、新たな発見があるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

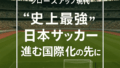
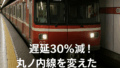
コメント