未完のバトン 第3回“均等法の母”に続く長い列
2025年5月30日放送の『NHKスペシャル』では、「未完のバトン 第3回“均等法の母”に続く長い列」と題して、男女雇用機会均等法を生んだ赤松良子さんの軌跡と、その志を引き継ぐ人々の姿が描かれました。今回は、生前の赤松さんが遺した日記や証言、そして現在も続く平等への取り組みを丁寧に紹介した内容となっています。
“均等法の母”赤松良子さんの遺志
旧労働省で婦人少年局長を務めた赤松良子さんは、男女差別をなくすために生涯をかけて取り組んだ人物です。1982年に局長に就任した当時、まだ多くの職場では男女の差別が当たり前のように存在していました。採用時に男性のみを募集する企業が多数を占め、結婚や出産を理由に女性が退職を迫られる例も少なくなかった時代です。そうした中で赤松さんは、法制度による改革を目指して本格的に動き始めました。
1985年、ついに男女雇用機会均等法が成立します。この法律は、日本で初めて雇用の場における性別による差別を禁じた画期的な法律で、以下のような内容が含まれました。
-
採用や昇進、配置転換において男女を平等に扱うことを「努力義務」とする
-
退職や定年などの扱いにおいて、男女差別を明確に禁止
-
雇用主に対して女性の就労機会を広げるよう求める仕組み
とはいえ、努力義務にとどまった点や、差別の実態に対して即効性が薄かったことも事実です。赤松さん自身もこの法律を「理想とは異なる妥協の産物」と受け止めていました。本来目指していたのは、差別の完全な撤廃と平等の実現でしたが、社会の反発や制度の壁に直面し、全てを盛り込むことはできなかったのです。
それでも赤松さんは、この法律が「第一歩」になることを信じていました。制度の上では小さな一歩かもしれませんが、以下のような成果を生み出しました。
-
女性の就職活動において選択肢が広がりはじめた
-
結婚や出産を理由に辞めさせられる事例が徐々に減少
-
社会全体に「男女平等」という意識が根づきはじめた
さらに赤松さんは、その後も制度の充実を求めて活動を続けました。育児休業法の制定や非正規雇用で働く女性の処遇改善にも深く関わり、「一人ひとりが安心して働ける社会」をめざしました。また、女性の政治参加にも強い関心を持ち、地方議会や国会における女性議員の割合向上を求め続けました。
このように赤松良子さんの遺志は、法律の条文だけにとどまらず、社会の意識改革や働き方の未来に向けた道しるべとして今も多くの人々に影響を与えています。彼女の残した「未完のバトン」は、今を生きる私たちの手にしっかりと引き継がれているのです。
働く女性たちのいま
芝信用金庫では、2008年から女性の総合職採用を本格的にスタートさせました。それまで男性が中心だった職場に、女性たちが加わり、今では副支店長や係長といった役職に就く女性社員が増えています。その一人、荻野副支店長は、日々の業務に加え、部下との面談も丁寧に行い、チーム全体の成長を支えています。
荻野さんのように子育てと仕事を両立している女性が活躍できる環境づくりのため、芝信用金庫ではさまざまな工夫が導入されています。たとえば、以下のような取り組みが実施されています。
-
毎週水曜日を「早帰りデー」として設定し、定時退社を推奨
-
長期休暇や連続休暇の取得を積極的に勧め、リフレッシュの機会を確保
-
育児や介護などのライフイベントに応じた柔軟な働き方を整備
さらに注目すべきなのは、男性社員の育児休暇取得率が95%に達していることです。これは全国的に見ても非常に高い数字で、性別を問わず「子育ては家庭全体の役割」という意識が職場に根づいていることを表しています。
実際に、杉本係長のように育児休暇から復帰後に昇進したケースもあり、「育休=キャリアのブレーキ」という固定観念を崩すモデルケースとしても注目されています。
こうした取り組みは、職場全体の働きやすさを高めるだけでなく、女性も男性も共に成長し続けられる組織風土を育んでいます。芝信用金庫のように、制度と意識の両面から支える職場が増えることで、赤松良子さんが目指した真の男女平等社会が少しずつ形になってきているのです。
法改正と市民の声
1991年に育児休業法が制定され、働く人が子どもを育てるために一時的に仕事を離れられる制度が整いました。しかし、法律ができたにもかかわらず、長い間、男性の育児休暇取得率は低いままでした。多くの職場では「育児は女性の役目」とされ、男性が休むことに対する理解が進まなかったのです。
そうした中で、自らの経験をもとに行動を起こしたのが天野妙さんです。彼女は第一子出産後に、職場から一般職へ降格されるという現実に直面しました。赤松良子さんと出会ったことで、「このままではいけない」と強く思い、子育て支援と職場環境の改善に向けた取り組みを始めます。
-
2017年、「みらい子育て全国ネットワーク」を設立
-
当事者の声を集めて、制度への反映を目指す活動を展開
-
働く親たちが安心して子育てできる環境づくりを支援
さらに、2019年の参議院予算委員会の公聴会では、天野さんが自らの言葉で男性の育休取得の義務化を提案しました。この提案は多くの共感を呼び、国会内でも「育児は男女ともに担うべき」という考えが少しずつ広がっていきます。
そして、2022年には育児・介護休業法が改正されました。この改正により、以下のような変化が生まれました。
-
出生時育児休業制度(いわゆる「産後パパ育休」)の導入
-
育休の分割取得が可能になり、柔軟な働き方が実現
-
企業に対して、社員への制度周知や取得環境の整備を義務付け
こうした法改正の背景には、一人ひとりの声や経験が社会に届いたことがあります。特に天野さんのように、困難を乗り越えて制度を動かそうとする人の存在は、政策を変える大きな力となっています。
今、育児は「家庭の問題」から「社会全体の課題」へと認識が変わりつつあり、法律と市民の動きが連動して社会を変える原動力になっています。これはまさに、赤松良子さんが願った「誰もが働きながら暮らせる社会」へと近づくための、大きな一歩といえます。
非正規雇用の女性たち
赤松良子さんは、男女平等の実現において正規雇用だけでなく、非正規雇用で働く女性たちの課題にも深く向き合ってきました。1985年に労働者派遣法が成立したことで、企業は必要なときにだけ人材を雇うことが可能となり、その結果、非正規雇用は年々増加していきました。中でも大きな問題となっているのが、その非正規雇用の約7割が女性であるという現状です。
非正規で働く女性たちは、以下のような厳しい状況に直面しています。
-
雇用が不安定で、突然の雇止めや契約打ち切りのリスクが高い
-
昇進やスキルアップの機会が限られ、将来のキャリア形成が困難
-
同じ仕事内容でも、正規雇用と比べて賃金や待遇に大きな差がある
番組では、名古屋で実際に起きた保育士の大量雇止めの事例が紹介されました。現場で長年働いてきた保育士たちが、ある日突然契約を打ち切られ、困惑と怒りの声をあげたのです。これを受け、建交労保育パート支部や公務非正規女性全国ネットワークが立ち上がり、実態の改善を求める活動を展開しました。
そうした集会の場には、2014年に赤松良子ユース賞を受賞した社会学者の瀬山紀子さんも参加。瀬山さんは、現場で働く女性たちの声を丁寧に聞き取りながら、非正規雇用という働き方の構造的な問題点を明らかにする研究を続けています。
このように、赤松さんが取り組んだ問題は今も続いていますが、それに対して声をあげる人々の輪は確実に広がっています。制度と現場、そして研究が結びつくことで、非正規の立場にいる人たちの環境を少しでも良くしようという努力が進んでいるのです。
赤松さんの理念は、「誰もが安心して働ける社会をつくる」ことにありました。そしてその思いは、今なお多くの現場で引き継がれています。
次の世代が受け継ぐもの
伊能美和子さんは、1985年に男女雇用機会均等法が成立した世代の一人として、社会の変化とともに働いてきた人物です。大手通信会社に勤め、30歳で職場結婚をした後は、母親との同居生活の中で介護も担いながら、キャリアを継続してきました。働きながら家庭の役割も担うという、当時としては難しい選択を実践してきた存在です。
現在は、複数の企業で社外取締役として活躍しながら、地方企業の成長を支援するマッチングサービスにも力を注いでいます。これは、都市部だけでなく地方にも機会を広げ、地域格差のない社会を目指す動きの一環であり、男女問わずすべての人が活躍できる場をつくるという理念に基づいた取り組みです。
一方、次の世代を代表する存在として紹介されたのが、能條桃子さんです。彼女が立ち上げた「FIFTYS PROJECT」は、政治に関心を持つ若者たちと、実際に行動する女性たちをつなぐ取り組みとして注目されています。
-
2023年の統一地方選挙では、FIFTYS PROJECTが応援した24人の女性が当選
-
若者たちが地域の課題に関心を持ち、政治参加の入り口となる仕組みを整備
-
政策だけでなく、仲間として共に動くネットワークの形成を重視
能條さんは、赤松良子さんに対して「年齢は離れているが仲間のように感じた」と語っており、これは世代を超えてつながる志の象徴です。赤松さんが切り開いた道は、単なる過去の歴史ではなく、今もなお生きていて、次の世代の行動に結びついています。
制度をつくる人、働きながら声をあげる人、そしてそれを次へとつなぐ人たち。それぞれの立場で受け継がれるバトンが、少しずつ社会を動かしています。そしてそのバトンは、今を生きるすべての人が手にできるものでもあります。
赤松さんが遺した願い
94歳で亡くなった赤松良子さんの「想い出の会」では、生前のメッセージが紹介されました。「地方議会の女性比率があまりにも低い。せめて3割は欲しい」という言葉には、今も変わらぬ課題が映し出されます。実際、日本の国会における女性の割合はわずか15.7%。2018年には候補者男女均等法が施行されましたが、さらなる取り組みが求められています。
最後に天野さんは「日本中の女性が走り回れる大地になったらいいですね」と語り、赤松さんの「男女平等実現のために長い列に加わる」というフレーズに、今も多くの人が力をもらっていることを伝えました。
この番組は、過去から現在、そして未来へのバトンをつなぐ姿を描いた記録であり、平等社会への道のりが今も続いていることを静かに、しかし確かに伝えていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


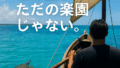
コメント