宮古島・悠久の楽園
沖縄県の人気リゾート地・宮古島を舞台にした『ブラタモリ』。今回は「魅惑のリゾート宮古島〜サンゴのシマの秘密とは?〜」をテーマに、青く澄んだ海、美しいビーチ、そして不思議な伝統行事に隠された地形の秘密に迫りました。舞台は伊良部島や島尻集落、新城海岸など、宮古列島の各地。地元を知り尽くした案内人とともに、太古の暮らしと大地の関係に光を当てた30分でした。
サバニに乗って伊良部の海へ!青い海とカニ漁の世界

旅の出発地点は伊良部大橋を渡った先の伊良部島。宮古島本島と伊良部島をつなぐこの橋は、日本でも有数の長さを誇り、まるで海の上を走っているような感覚になります。橋を渡った先にある静かな浜辺で、今回の案内人である宮古島市教育委員会の久貝さんと一緒に訪れたのが、伝統漁船「サバニ」を操るカニ漁師の吉浜さんです。
サバニは、木でできた細身の船で、かつて沖縄の島々で広く使われていた漁船。エンジンをつける前は、帆や櫂を使って海を進んでいたとされるほどの歴史ある船です。見た目は小さくても構造はしっかりしており、海が荒れても安定感があるつくりになっています。
このサバニで漁をする様子は、以下のような特徴がありました。
-
船底が浅く作られているため、干潮時でも浅瀬に入れる
-
波に強い形状で、リーフの内側の静かな海を自在に移動できる
-
船体が軽く、少人数で操縦可能
-
動力船と比べ、海への負担が少ないエコな漁法
番組では、このサバニにタモリさんたちが実際に乗り、透き通った伊良部の青い海を進んでいく様子が映されました。海の中のサンゴ礁や魚の影が見えるほど透明度が高く、漁船の底からでも海の様子がわかるほどでした。
リゾート地としての伊良部島のイメージが強い一方で、昔ながらの漁を守り続ける地元の人々の姿が、旅の中でしっかりと描かれていました。観光客には見えにくい、島の“日常”の暮らし。そこには、自然と共に生きる知恵と工夫がありました。
吉浜さんが続けるカニ漁は、エビや小魚などが入る籠を浅瀬に沈めておき、潮が引いたタイミングで引き上げるという、シンプルながらも海を熟知していないと難しい技術が求められます。自然と向き合い、潮の流れを読み、海の恵みを無駄なく生かす。それがこの土地に根付く漁のかたちなのです。
サバニに乗った時間は短くても、そこには昔から変わらぬ風と波、そして人の知恵が交わる時間が流れていました。番組は、そんな島の姿をやさしく伝えてくれました。
泥の神様が村を練り歩く!?パーントゥの奇祭

番組の旅は次に宮古島の島尻(しまじり)集落へと向かいました。ここで行われるのが、2日間で6000人もの人々が訪れる「パーントゥ祭り」です。この祭りの最大の特徴は、全身泥まみれの神様“パーントゥ”が集落を練り歩き、人や家、車に泥を塗っていくというもの。街全体が泥で覆われるほどのスケールで行われるこの行事は、厄払いや魔除けの意味を持ち、島の人々にとって大切な伝統です。
祭りに登場するのは3体のパーントゥ。それぞれが異なる仮面をつけ、同じように泥に覆われた姿で現れます。仮面は普段は別々の場所に大切に保管されており、番組ではそのうちの一つを保管する住宅を訪れ、実際の仮面を見せてもらうことができました。重厚な造りと独特の形をした仮面は、神聖なものとして大切にされてきたことがうかがえます。
このパーントゥの泥は、ただの土ではなく、「ンマリガー」と呼ばれる神聖な湧き水の底にある特別な泥を使用しています。このンマリガーは、琉球石灰岩でできた島にあっては珍しい泥岩層が地表に現れている場所で、実は地質的にも非常に興味深いポイントなのです。
-
宮古島の地質は琉球石灰岩が主体で、水がすぐ染み込む特徴を持つ
-
しかし島尻周辺は断層の影響で地下の泥岩層が地表に出ている
-
そのため、泥がたまりやすく、特殊な泥質をもつ祭りに適した場所となった
-
この地域では昔、水田も作られていたほどの貴重な土地
こうした地形と地質の条件が重なった場所だからこそ、パーントゥという独特な神様が生まれ、受け継がれてきたのです。泥に込められた意味や、神聖な場所から得られる材料、そして祭りそのものに宿る祈りの力。それらすべてが、宮古島の自然と人のつながりを象徴しています。
番組は、この不思議な祭りをただ紹介するだけでなく、背景にある地形や文化、そして人々の信仰心まで丁寧に掘り下げて見せてくれました。泥をまとって集落を清めるパーントゥの姿は、まさに大地とともに生きる島人の姿そのものでした。
伊良部島と下地島の境界線に迫る

タモリさんが注目する伊良部島と下地島の境界は、地図上では一体に見えても、実際には「入江水道」と呼ばれる細長い海峡によって隔てられています。この海峡は幅約40〜100メートル、長さは約3.5キロメートルもあり、見る角度によっては一本の島に見えることもありますが、実は海によって明確に分けられているのです。
この境界線が生まれた背景には、活断層の存在があると考えられており、プレートの動きによってサンゴ礁が隆起・沈降を繰り返す中で、2つの陸地が分断された地形的特徴とされています。地表の高低差や岩盤の違いなどからも、伊良部島と下地島の成り立ちが異なることが分かっており、地質学的にも大変興味深い場所です。
-
海峡の水深は浅く、潮の流れが穏やかであることが多い
-
干潮時には海底が見えるほど水が引くエリアもあり、地形の観察がしやすい
-
島の両岸には石灰岩の地層が露出していて、サンゴ礁由来の成層がはっきり見える
この海峡には現在6本の橋が架かっており、車や徒歩での往来が可能です。そのため、観光客の多くは「1つの大きな島」として認識することが多く、日常的な生活圏としても完全に一体化しているエリアとなっています。特に近年は、下地島空港の利用者が増え、伊良部島全体がゲートウェイ的な役割を担うように変化しています。
-
橋の中でも特に有名なのは「伊良部大橋」とは別の、入江水道に架かる小さな連絡橋群
-
自転車で巡る観光客が多く、橋上から海中を泳ぐ魚やウミガメが見えることもある
-
両島の間にはマングローブや湿地帯が点在しており、独特の生態系も広がっています
こうした地形や構造を実際に歩いて確かめることで、目に見える「つながり」と、目に見えない「分かれ」を同時に感じられる場所でもあります。タモリさんがどのようにこの境界を見つめ、地形の物語を語るのか、放送に大きな期待が集まっています。
2800年前の暮らしの跡が残るアラフ遺跡とは
番組の最後に訪れたのは、観光客にも人気の新城(あらぐすく)海岸です。この海岸は、透き通る遠浅の海と穏やかな波が特徴の美しい場所。そのすぐそばにあるのが、2800年〜1900年前の人々の暮らしの跡が残る「アラフ遺跡」です。宮古島の歴史を知る上でとても重要な場所であり、人々が自然と調和して暮らしていたことを今に伝える貴重な証拠となっています。
この遺跡が見つかった場所は、魚や貝などがとれやすい遠浅の海に面し、陸側には風を遮る小高い丘があるという、非常に生活に適した立地条件を備えていました。こうした自然環境の利点から、当時の人々がここを住まいの場として選んだ理由がよくわかります。
出土した遺物の中でも特に注目されたのが、貝から作られた「貝斧(かいふ)」です。石の代わりに使われていたこの道具は、周囲の資源を無駄なく活用していたことを示す証拠であり、当時の人々の工夫と技術の高さが感じられます。
一方で、土器は一切出土していないという点も大きな特徴です。代わりに見つかったのが、焼いた琉球石灰岩にバナナの葉をかぶせて調理する「アースオーブン」と呼ばれる遺構でした。このアースオーブンは以下のような特徴があります。
-
220基もの遺構が確認されている
-
石灰岩を加熱して調理台とし、その上にバナナの葉を敷いて食材を調理
-
土器がなくても石と植物を組み合わせて煮炊きが可能
-
自然素材を活かした環境にやさしい調理法
この調理方法からもわかるように、当時の人々は限られた資源の中で創意工夫を凝らし、暮らしを成り立たせていたことが見えてきます。また、遺跡の近くには真水が湧く場所もあり、生活に必要な水も身近で確保できる理想的な住環境が整っていたことが確認されています。
このように、アラフ遺跡は2800年前の人々が自然と共に暮らした証であり、今でもその知恵や工夫に学ぶことができる場所です。番組では、観光地としての海の美しさだけでなく、その背後にある「生きるための知恵」が宿る土地として、この海岸を丁寧に紹介していました。リゾートの風景の奥には、人間の歴史と自然との共生が刻まれていることを教えてくれる、静かで力強いラストシーンでした。
地形と文化がつくりあげた宮古島の魅力
今回の放送では、リゾート地としての顔とは異なる、宮古島の本当の魅力が数多く紹介されました。サンゴがつくった島の地形、断層がもたらす特異な地質、そしてそれを活かした祭りや古代の生活様式。どれも自然の中で生きてきた人々の知恵と結びついています。
青く透き通る海の奥に広がる、悠久の時間と人々の営み。それが今回の旅のテーマである「サンゴのシマの秘密」なのだと感じさせてくれる内容でした。次回の旅も、また新しい発見を届けてくれそうです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


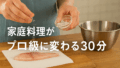
コメント