ごちゃまぜで生まれる優しさの場所・神戸の“令和の長屋”へようこそ
神戸市長田区の一角に、まるで昭和の長屋を思わせる温かい共同住宅があります。名前ははっぴーの家ろっけん。ここには、介護や看護が必要な高齢者だけでなく、子ども、若者、地域の人、外国人まで、あらゆる世代と背景の人が集まります。昼は笑い声、夜は音楽や食器の音が響き、まるで“家族でも他人でもない”不思議な絆でつながった人々の暮らしが息づいています。
この場所はNHK『ドキュメント72時間 神戸 令和の“ごちゃまぜ長屋”で』(2025年10月31日放送)でも取り上げられ、多くの人の心を動かしました。今回は、その舞台となった“ごちゃまぜ長屋”の魅力と、そこに暮らす人々の3日間をたっぷりと紹介します。
下町の中に息づく「ごちゃまぜの家」
舞台は神戸市長田区の六間道商店街のそば。震災の爪あとを乗り越えてきたこの地域は、昔ながらの下町情緒が色濃く残っています。細い路地の先に現れるのが、白い外壁に木の温もりを感じる建物――それが“ごちゃまぜ長屋”ことはっぴーの家ろっけんです。
ここは2017年3月3日に誕生。運営するのは地域密着型の福祉事業を手がける株式会社Happy。設立者の首藤義敬さんは「介護施設をつくるのではなく、人が自然に集まり、助け合う“暮らしの拠点”をつくりたかった」と語っています。
建物は6階建て、居室は約40室。入居しているのは、介護や看護が必要な高齢者や障がいをもつ人たちです。しかし、この家の最大の特徴は“開かれていること”。地域住民や通りすがりの人が自由に訪れ、まるで古い長屋の縁側のように交流が生まれています。
介護付き住宅が「地域のリビング」になった
兵庫県神戸市長田区にあるこの共同住宅は、単なる介護サービス付き住宅ではありません。ここにはおよそ40人の入居者が暮らし、年齢も、職業も、生活背景もさまざま。介護を必要とする高齢者、障がいを抱える人、夫婦で暮らす人など、多様な人々が共に過ごしています。
1階の共用リビングはいつでも開放され、入居者だけでなく近所の人も自由に出入りできます。夜になると、スタッフや近所の子どもたちが集まり、笑い声や食器の音が響きます。まるで昔の“長屋”のように、境目のない人のつながりが生まれています。
このリビングは「介護施設」というより「街のリビング」。スタッフの明るい声かけが日常の安心をつくり出しています。かつて車いすダンサーとして活躍していた女性もそのひとりです。脳梗塞で倒れた後、長く踊ることを諦めていましたが、スタッフの励ましに支えられ、もう一度前を向けるようになりました。「ここでは誰かが必ず見ていてくれる」と彼女が語るように、この場所には孤立を防ぐ“見守りの優しさ”があります。
朝5時から動き出す100歳女性の姿
2日目の朝、まだ外が暗い午前5時過ぎ。リビングの灯りがともると、100歳の女性がゆっくり現れます。手慣れた様子でテーブルを拭き、朝食の準備を始める姿は、周囲の人にとって何よりの元気の源です。誰に頼まれたわけでもない、自然な生活のリズム。長く積み重ねた人生の時間が、空間に穏やかさをもたらしています。
隣の建物では、喫茶店を営む女性が新聞を配る姿も。読み終えた新聞を住宅に持って行くのが日課になっています。彼女の夫もかつてこの住宅に入居しており、最期の2年間をここで過ごしました。「ここは、最後まで人と人が寄り添える場所」と話すその言葉には、この住宅の存在意義がにじんでいます。
さらに、元スナックママの女性のエピソードも印象的です。夫を亡くしてから認知症が進み、かつては離れていた息子が1年半前から毎週末顔を見せに来るようになりました。親子の時間を取り戻すことができたのは、ここが“帰る場所”になっているから。家族の絆を再び結び直す場として、この住宅は静かに力を発揮しています。
“誰かの居場所”ができることで生まれるつながり
ここでは、過去や肩書きに関係なく、人が自然に集まってきます。かつてゲイバーの経営者として全国を渡り歩いてきた男性もその一人。住まいが定まらず不安だった時に、施設の代表から「家が決まるまで住んでいいよ」と声をかけられたことがきっかけでした。今では、特に用事がなくてもリビングへ足が向くといいます。
誰かに「ここにいていいよ」と言われること。それだけで人は居場所を得られます。社会のどこかで孤立しがちな人にとって、この住宅は“受け入れの場”であり、人生のリスタート地点でもあります。人と人とが交わることで、まるで心のリハビリが行われているような温かさが広がっています。
「迷子」から見える地域との関係
3日目の出来事では、ある男性入居者が警察官に連れられて戻ってきました。散歩中に道に迷い、近くの交番へ駆け込んだそうです。スタッフが迎えに来ると、警察官も笑顔で送り出しました。その一連のやりとりには、地域全体がこの住宅を理解し、協力して支えている関係が感じられます。
また、元介護士の女性もこの住宅で暮らしています。数年前にがんを患い、仕事を離れ、ここでの生活を選びました。最初のうちは塞ぎ込みがちでしたが、人との何気ない会話が生きる励みになり、今ではリビングで笑顔を見せる日も増えました。誰かに頼られたり、逆に手を差し伸べたりすることで、自分の存在が再び社会とつながる。そんな循環が、この“ごちゃまぜ長屋”の中では自然に生まれています。
この共同住宅には、介護と地域の境界を取り払う力があります。介護する人・される人という関係を超えて、誰もが“誰かのそばにいる”。それが、令和の長田で静かに息づく新しい暮らしの形です。
まとめ:現代に生まれた“新しい長屋”の形
この記事のポイントは次の3つです。
・介護付き住宅が「地域の居場所」として開かれていること
・世代や背景の違いが“絆”を生む力になっていること
・孤立しがちな現代社会で「ごちゃまぜ」が生きる希望になっていること
神戸の“ごちゃまぜ長屋”は、介護施設でも共同住宅でもなく、人の心をつなぐ「現代版長屋」。生きづらさを抱える人も、支える人も、地域の人も、同じテーブルを囲む。そんな風景が、これからの社会を変えていくのかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

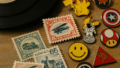
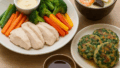
コメント