人生の最期に“希望”を持てるのか?NHKスペシャルが問いかけたこと
長寿社会を迎えた今、「長生きしたいですか?」と問われて即答できる人は少ないのではないでしょうか。実際、国立社会保障・人口問題研究所の調査では「長生きを良いと思わない」と答えた人が3割近くにのぼります。そんな中、NHKスペシャル『未完のバトン 最終回 人生の最期と“希望”』は、在宅医療の現場と海外の安楽死をめぐる最前線を取材し、私たちに「どう生き、どう最期を迎えるのか」を深く考えさせる内容でした。この記事では番組で描かれたすべてのエピソードを整理しつつ、読者にとっての気づきを分かりやすく解説します。
【NHKスペシャル】命を診る 心を診る 〜小児集中治療室の日々〜|国立成育医療研究センターの最前線 2025年7月13日放送
チーム医療が支える“希望ある在宅医療”
愛知県と岐阜県を拠点に活動する市橋医師は、患者が人生の最期まで「希望を持って生きられる」ことを大切にしています。彼が運営する総合在宅医療クリニック羽島郡では、医師だけでなく歯科医師、管理栄養士、音楽療法士といった多様な専門職がチームを組み、患者の小さな願いから生活全体まで幅広く支える体制が整えられています。食事の工夫や口腔ケア、音楽による心のケアまで取り入れることで、治療だけにとどまらず生活そのものの質を高めることを目指しています。
市橋医師はもともと大病院で最先端医療に携わっていましたが、患者が自分の生活から切り離されるような状況に疑問を持ち、16年前に在宅医療の道へ転じました。以降は、家庭という患者にとって最も安心できる場所で、本人と家族が納得できる形の医療を提供し続けています。
その姿勢が表れているのが、間質性肺炎を患う林さんとの向き合い方です。林さんはかつて国内外を飛び回る仕事をこなしていましたが、病状の進行により思うように体が動かず、「長く生きても仕方ない」と意欲を失うようになっていました。市橋医師はその言葉をただ受け止めるのではなく、なぜそう思うのかを丁寧に聞き取り、林さんが再び「日々の中で楽しみを見つけられる」よう支えました。たとえば日常の外出や好きな物を口にする機会を大切にし、本人が「まだやりたい」と思える瞬間を少しずつ取り戻せるよう努めました。
在宅医療の現場では、病気を治すことよりも「どう生きるか」が問われます。林さんのように一度は意欲を失った患者でも、寄り添う医療によって希望を見いだしながら最後の時間を過ごすことができるのです。
長寿社会の影と日本人の不安
戦後の日本は、上下水道の整備や感染症対策の徹底、栄養状態の改善など公衆衛生の大幅な向上と、抗生物質の普及や外科手術の発達といった医療技術の進歩によって、人々の平均寿命が大きく延びました。さらに1961年に導入された国民皆保険制度は、誰もが平等に医療を受けられる仕組みを整え、日本は世界でもまれにみる長寿国となりました。昭和の終わりには「世界一の長寿国」と称されるほどになり、長生きは社会の大きな誇りとされてきました。
しかし1990年代に入ると、社会の現実は変化していきます。この時期には約8割の人が病院で最期を迎えるようになり、延命のために人工呼吸器や点滴、胃ろうといった医療措置を受けるケースが増えました。結果として「命は延びても、苦痛や制約の多い時間を過ごさなければならない」という問題が浮かび上がり、本人や家族にとって望まない状況が生じることが少なくありませんでした。
2000年代になると、無縁死や孤独死が社会問題として注目されました。家族や地域とのつながりが薄れる中で、高齢者が誰にも看取られず亡くなる事例が増加し、長寿社会の裏側にある孤立の現実が広く認識されるようになりました。こうした状況から、「長生きは必ずしも幸せにつながらない」という感覚が人々の間で広がっていきます。
厚生労働省や国立社会保障・人口問題研究所が行った調査では、「長生きを良いと思わない」と回答する人が増加し、直近の調査では全体の約3割に達しています。かつては「長寿は豊かさの象徴」と考えられていたのに対し、現代の日本では「長寿=幸福」とは言い切れない現実が広がっているのです。
海外の“ポジティブヘルス”と安楽死の議論
市橋医師は、終末期の患者とどう向き合うべきかを学ぶためにオランダを訪れました。そこで出会ったのが『ポジティブヘルス』という考え方です。患者自身が「身体の健康」「心の状態」「生活の楽しみ」「人とのつながり」「日常生活の自立度」「生きがい」という6つの観点で自分の生活を評価する仕組みで、病気や痛みだけに焦点を当てるのではなく、その人がどのように生きたいかを大切にするアプローチです。ある患者は体の痛みを強く訴えていましたが、この評価を通して「まだ楽しいこともある」と気づき、気持ちを少しずつ前向きに変えていく姿が見られました。
一方、ヨーロッパでは終末期の医療をめぐって大きな動きが広がっています。フランスやイギリスでは、患者が自らの意思で死を選ぶ権利を認める法案が次々と可決され、社会全体で議論が深まっています。特にオランダでは安楽死が既に合法化されており、年間に一定数の事例が行われています。現地で出会ったインゲン医師は、「治療を続けなければ、より人間らしい形で死を迎えられる」と語りました。
しかし、市橋医師はその意見に対し、「人の意思は状況や心境によって変化し得る」と考えています。ある時は死を望んでも、別の時には生きる喜びを見出すことがある。その可能性を見逃さず、最後まで患者の希望に寄り添う姿勢を大切にしているのです。
患者の願いを叶える“寄り添う医療”
番組で紹介されたがん患者の羽角さんのエピソードは、とても心に残るものでした。医師から余命を告げられた羽角さんに対し、市橋医師は単に病気の進行を抑える治療を行うのではなく、羽角さんが「自分らしく生きたい」と思える時間を持てるよう全力を尽くしました。
羽角さんは病気の影響で体調が不安定になり、吐き気や倦怠感と戦う日々を送っていました。それでも市橋医師は、治療のスケジュールを柔軟に調整し、羽角さんが望む時間を大切にできるよう配慮しました。例えば、息子との旅行に出かける日程に合わせて治療を組み替えたり、友人たちとお泊り会を楽しめるように医療スタッフが同行する体制を整えたりと、細やかな工夫を重ねました。
そして亡くなるわずか6日前、羽角さんの「桜の下で好きな音楽を聴きたい」という願いを実現します。春の空気の中で流れる音楽に耳を傾けるその時間は、病と闘いながらも羽角さんが「生きている喜び」を実感できた瞬間でした。
この姿から伝わるのは、医療が単に命を延ばすものではなく、人生の最期まで希望や楽しみを支える力になり得るということです。市橋医師の寄り添い方は、終末期の医療における大切な意味を私たちに示していました。
最期の選択肢が多様化する時代
市橋医師は番組の中で、パリ在住の俳優・笈田さんとも深い対話を交わしました。笈田さんは10年前に皮膚の難病を発症し、日々強い痛みに苦しんでいます。そんな状況の中で、6年前に安楽死を支援する団体に登録し、自らの人生の終わり方を選択肢として視野に入れていました。彼は「死ぬことがあるからこそ、生きがいを感じられる」と語り、限られた時間だからこそ舞台への情熱を失わずに生きられるのだと考えていました。
一方で番組には、オランダで夫を安楽死で見送った女性も登場しました。彼女は夫の決断を尊重しながらも、残された者として深い悲しみを抱え続けていました。理解しようと努めても完全には割り切れない複雑な感情が、画面を通して強く伝わってきました。
市橋医師は「人類にとって長生きはかつて希望そのものだった。しかし、どのように終わるのかは今まさに問い直されている」と語りました。この言葉は、ただ医療の課題にとどまらず、長寿社会を生きる私たち一人ひとりが避けて通れない社会的テーマを突きつけています。
希望を抱いて迎えた最期の瞬間
番組のラストを飾ったのは、間質性肺炎を患っていた林さんのエピソードでした。長く外出できずにいた林さんの小さな願いは、「お気に入りの帽子をかぶって出かけたい」というものでした。市橋医師とスタッフはその思いを大切に受け止め、林さんを近所のスーパーへと連れ出しました。好きな帽子を身につけ、日常の空気に触れながら買い物を楽しむ姿には、わずかでも「生きる喜び」を取り戻した瞬間が映し出されていました。
その外出から2か月後、林さんは自宅で家族に見守られながら静かに息を引き取りました。病院ではなく、自分が暮らし続けてきた家で最期を迎えられたことは、林さんにとって何よりも大切な選択だったのかもしれません。
現在も市橋医師は、名古屋や岐阜を拠点に50人以上の患者と共に歩み、一人ひとりの願いや思いに耳を傾けています。延命ではなく、その人らしい“希望ある最期”を支えることこそが、彼の医療の中心に据えられているのです。
まとめ:この記事のポイント
-
長寿社会の課題:3割が「長生きは良いと思わない」と回答
-
市橋医師の在宅医療:チーム医療で患者の希望を支える
-
海外の動向:ポジティブヘルスの実践と安楽死合法化の広がり
-
寄り添う医療の実例:旅行や桜の下での音楽など、最後まで希望を叶える取り組み
-
多様化する選択肢:尊厳死・安楽死・在宅医療、それぞれがもたらす意味
人生の最期に何を望むのか――その答えは人それぞれ違います。しかし、この番組が示したように「希望を抱いて最期を迎える」ことは、私たち一人ひとりが考え、準備するべき大切なテーマだと言えるでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


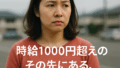
コメント