米価が暴騰する今、コメ作りの現場で何が起きているのか
「お米が高すぎて買えない」「でも農家も苦しいらしい」――そんな声が、全国のスーパーや家庭の食卓から聞こえ始めています。2025年秋、日本ではいま“令和のコメ騒乱”とも呼ばれる異常事態が起きています。
この2年でコメの価格は2倍以上に跳ね上がり、家計を直撃する一方で、生産者にも大きな混乱をもたらしています。恩恵を受けるどころか、戸惑う農家も少なくありません。
10月12日放送のNHKスペシャル『米価騒乱“増産転換”の行方は』は、その舞台裏に密着。農林水産省コメ対策チームの奮闘を通じて、日本の農政が抱える深い課題と、これからのコメ作りの未来を描きました。
北海道・旭川から見える“高すぎる新米”の現実
番組の冒頭、カメラが向かったのは北海道旭川市。全国でも有数のコメ産地として知られる地域ですが、ここでも異変が起きていました。
首都圏のスーパーでは、今年の新米が4000円台後半から5000円超という記録的な高値をつけています。
消費者だけでなく、生産現場でもその影響は大きく、JA(農業協同組合)と民間業者の間では前例のない価格競争が発生していました。
昨年、JAあさひかわが提示した概算金(コメを買い取る際の基準価格)は、60kgあたり1万6500円。
しかし、民間業者がさらに高い金額を提示し、JAへの集荷率が例年より1割以上減少。
これを受け、今年は2万9000円という異例の高値が設定され、民間側はさらに上回る3万円超を提示しました。
この高騰の連鎖が、全国の市場価格を押し上げ、店頭ではかつてない値札が並ぶ結果となりました。
旭川の農家たちは、「高値で売れても、肥料や燃料のコストが上がっているから手取りは増えない」と語ります。
一方、流通業者の間では「コメが確保できない」という不安が広がり、全国からの買い付け交渉が殺到。
地元中心だった流通構造が崩れ、“奪い合い”のような状況が生まれていたのです。
農林水産省が異例の謝罪 政策の歪みと「想定外の需要」
8月、ついに事態を重く見た農林水産省が記者会見を開き、コメ不足の実態を公式に認め、異例の謝罪を行いました。
その裏には、2年間で76万トンものコメが不足していたという衝撃の事実。
原因は「コメ余り時代」の延長線上で政策運営を続けた結果、需要の回復や気候変動の影響を読み違えたことにありました。
日本のコメ政策は、半世紀近く「減反政策」に依存してきました。
1978年から続くこの政策は、生産を抑えて価格を維持するものでしたが、
食の多様化と人口減少で消費量が減る中、いまや構造的に限界を迎えていました。
そこへ追い打ちをかけたのが、猛暑による品質低下。
全国の水田で“白濁米”と呼ばれる出荷不能なコメが増え、2年間で約16万トンが目減りしたと分析されています。
さらに、観光客の増加によるインバウンド需要、外食回復による業務用コメの需要上昇など、
複数の要因が重なって、コメ需給が一気に逼迫したのです。
国の方針転換「増産」へ 現場が抱く期待と不安
政府は8月、これまでの抑制路線を見直し、「増産転換」という歴史的な方針を発表しました。
コメの供給を増やして価格の安定を図る――一見、理にかなった政策のように思えます。
しかし、現場ではすぐに実行できる状況にはありません。
番組では、熊本県嘉島町や富山県黒部の農業法人が登場。
「増産をするなら、機械投資や人材確保の支援を強化してほしい」と語ります。
コメの生産性を上げるためには、大区画化(圃場整備)やスマート農業技術の導入が欠かせません。
農林水産省もこれらの分野に重点予算を配分する方針を示していますが、実現には時間がかかるのが現実です。
また、農業関係者からは「補助金の見直しが不可避」との声も。
これまで国は、コメから大豆や麦などへの転作に対して補助金(ずいでん活用交付金)を支給してきました。
その規模は年間3000億円にのぼります。
しかし増産を進めれば、この交付金の仕組みそのものが崩れ、
小規模農家の経営基盤が揺らぐ可能性があります。
「作れと言われれば作る、抑えろと言われれば抑える。でも、もう限界です」
ある農家の言葉が、現場の複雑な心境を代弁していました。
主食の未来を守るために――動き始めた新たな挑戦
番組後半では、コメの“未来をどう守るか”という視点から、各地の取り組みが紹介されました。
まず登場したのは、大手コメ卸企業が立ち上げた新規就農支援会社。
社員として若者を雇用し、4年間かけて技術を学ばせ、
独立時には農地の紹介や大型機械のレンタル、販売支援まで行うという“育成型農業”の仕組みです。
現在、海外出身者を含む6人が入社。次世代の生産者を育てる新たな試みが始まっています。
さらに、鳥取県のJAでは「生産費払い制度」を導入。
これは市場価格ではなく、生産コストを基準に概算金を設定する方式で、
60kgあたり2万2000円を保証。小規模農家でも赤字を出さない設計になっています。
導入初年度で集荷量は前年の2倍に増加し、農家の安定経営に寄与しています。
「コストを保障すれば、農家は安心して米づくりに専念できる」とJA関係者。
これこそが、“現場発”の構造改革の一歩です。
消費者との“距離を近づける”ことが未来を変える
番組のラストでは、新潟県で行われた稲刈り体験ツアーが紹介されました。
首都圏の消費者が実際に田んぼに入り、農家と一緒に稲を刈る――
このシンプルな交流が、食の根本的な意識を変えつつあります。
参加者の一人は「お米がどれだけの手間で作られているか初めて実感した」と語り、
別の人は「これからは値段だけで選ばず、作り手を意識したい」と話しました。
コメを“買う人”と“作る人”が再びつながること。
その意識の変化こそ、政策だけでは生み出せない“もうひとつの改革”です。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・コメ価格高騰の原因は、長年続いた減反政策の歪みと市場競争の過熱にある
・政府の「増産転換」は大胆だが、支援策と補助金構造の見直しが鍵を握る
・未来を支えるのは、生産者と消費者の距離を縮める新たな仕組みづくり
日本の主食「コメ」は、単なる農作物ではなく、文化・経済・地域社会を支える柱です。
この“令和のコメ騒乱”は、単なる価格問題ではなく、日本の農政そのものへの問いかけでもあります。
これからの日本がどんな形で「食の自立」を守るのか、その答えは私たち一人ひとりの選択にかかっています。
出典:NHKスペシャル『米価騒乱“増産転換”の行方は 密着・農林水産省コメ対策チーム』(2025年10月12日放送)
https://www.nhk.jp/p/special/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

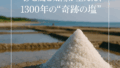
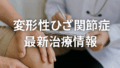
コメント