塩ってこんなに奥深い!暮らしとお金をつなぐ“しおの物語”
料理の味を決める名脇役「塩」。でもその一粒の裏には、長い歴史と科学、そして経済の物語が隠れています。「日本ではなぜ岩塩が採れないの?」「どうやって昔の人は海から塩を手に入れていたの?」そんな疑問を感じたことがある方も多いでしょう。
2025年10月12日放送のNHK総合『有吉のお金発見 突撃!カネオくん』では、「ステキな豆知識も満載!塩のヒミツ」をテーマに、私たちの暮らしに欠かせない“塩”の経済的・文化的価値を掘り下げました。
番組には、有吉弘行、田牧そら、坂下千里子、香音、伊藤俊介(オズワルド)といった個性豊かな出演者が登場し、塩の値段の裏側から、世界の塩文化まで、さまざまな角度からその魅力を紹介しました。
放送後には、番組で放映された映像・コメントをもとに詳細を追記予定です。ここでは、食文化経済学の視点から“塩とお金”の関係を深掘りしてみましょう。
海の恵みをどう活かす?日本独自の塩づくりの知恵

世界には岩塩鉱山を持つ国が多くあります。例えばオーストラリアやメキシコでは、広大な塩湖から自然に塩が採れます。しかし、日本では地質的に岩塩が存在せず、気候的にも湿気が多く、塩を自然蒸発で得るのは非常に難しい条件です。
そんな厳しい環境の中で、日本人が編み出したのが「海水を煮詰めて塩を作る」という独自の方法でした。とはいえ、海水の塩分濃度はたったの3%程度。燃料代がかさみ、コストに見合わない生産方法だったのです。
ここで登場したのが“かん水”。これは、海水を浜に撒いて砂に塩分を染み込ませ、その砂を乾かし、再び海水に溶かして濃度の高い塩水をつくるという工夫です。この濃縮したかん水を煮詰めれば、燃料の節約にもつながり、効率よく塩が取れます。まさに日本人の知恵の結晶といえます。
番組では、愛媛県の大手塩メーカーが登場し、現代の塩づくりを支える最新設備を紹介。巨大な釜での加熱、蒸気循環によるエネルギー再利用など、環境にやさしく、かつ品質を一定に保つ仕組みが紹介されました。塩づくりが“産業”として成立するまでには、科学・経済・環境への配慮が不可欠だったのです。
能登の浜で続く「手しごとの塩」

(画像元:揚げ浜式製塩の塩づくり | 奥能登塩田村)
一方で、日本の伝統的な塩づくりが今も息づく地域もあります。その代表が、石川県能登半島で行われている「揚浜式(あげはましき)製塩」。これは約400年以上続く製法で、人の力だけで海水をくみ上げ、塩田にまんべんなく撒きます。
潮風と太陽の熱で砂を乾かし、砂に付着した塩分を集めて再び濃い塩水にする――この工程を何度も繰り返して、ようやく塩ができます。
過酷な肉体労働にもかかわらず、能登の浜士(はまし)たちは誇りをもって仕事を続けています。有吉弘行も番組内で「揚浜式は本当に大変。生まれ変わっても浜士にはなりたくない」と笑いながらも、職人たちへの敬意をにじませていました。
この伝統製法を科学的に検証しているのが金沢工業大学。学生と地元住民が協力し、能登の塩を地域ブランドとして守る取り組みを続けています。塩づくりが単なる製造業ではなく、地域産業と文化をつなぐ“経済遺産”となっているのです。
塩を求めるのは人間だけじゃない
番組では、動物たちの「塩との関わり」も紹介されました。アフリカ・中央アフリカ共和国にあるザンガ・サンガ国立公園では、マルミミゾウが塩分を含む泥水を飲み、体に必要なミネラルを補給しています。
また、イタリア北部のダムでは、アイベックス(野生のヤギ)が危険を冒してまでダムの壁を登り、壁面に付着した塩分を舐め取る姿が観察されています。さらに、南米の塩湖では、フラミンゴが塩分を含んだ水中の藻や微生物を食べ、ピンク色の羽を保っています。
塩は、動物たちにとっても“生きるための栄養素”。つまり、人間社会だけでなく、生態系全体においても「塩は生命の通貨」といえる存在なのです。
フラミンゴのクイズが教えてくれた“自然の経済学”

番組恒例の「カネオクイズ」では、こんな問いが出されました。
「動物園のフラミンゴは屋根がなくても、なぜ飛んで逃げないの?」
答えは「飛ぶための助走距離が取れないから」。フラミンゴが飛ぶには数メートルの助走が必要で、狭い池の中では羽ばたけないのです。
このエピソードは、自然環境と動物の生態が密接に関係していることを示しています。塩を求めて行動する生き物たちも、限られた環境の中で生きる術を選んでいるのです。
塩は“食べる”だけじゃない!暮らしを支える力
私たちが塩を使うのは料理だけではありません。冬の道路にまかれる凍結防止剤も塩が原料です。塩水は『マイナス21度』まで凍らないため、雪国では事故防止に欠かせません。
また、世界では塩を使ったアートも注目されています。ノルウェーのアーティスト、ディノ・トミック氏は、黒い布の上に塩だけで描く『ソルトアート』を制作。照明の角度によって絵の印象が変わる繊細な作品で、SNSでも話題を呼びました。
さらに、塩は美容や医療分野でも活用されています。入浴用の岩塩、デトックスソルト、歯磨き粉など、暮らしのあらゆる場面に“塩の価値”が広がっています。
経済の視点から見た「塩の価値」
塩は古代から“お金の代わり”として使われてきました。古代ローマでは兵士の給料(サラリー)が塩から生まれたと言われています。日本でも「塩の専売制」が導入され、国の財政を支える重要な産業となってきました。
つまり、塩はただの調味料ではなく、社会のインフラを支える資源なのです。現代でも、塩の価格変動は燃料費や物流の影響を受けやすく、経済の動きを映す“ミクロな指標”といえます。
番組タイトルの通り、“お金のヒミツ”を知るには、身近な「塩」から学ぶことがたくさんあります。
まとめ:塩は“命と経済”をつなぐ結晶
この記事のポイントは以下の3つです。
・日本は地形的に不利な中で「かん水」製法を発展させ、塩産業を築いた
・能登半島などの地域では伝統的な揚浜式製塩が今も続き、地域経済と文化を守っている
・塩は食卓・道路・アート・医療など、あらゆる場面で人の暮らしを支えている
塩の価値は、料理の味を整えることだけではありません。それは、人と自然、文化と経済を結ぶ架け橋。
有吉弘行とカネオくんが見つけた“塩のお金のヒミツ”は、現代社会のあらゆる仕組みに通じるものでした。
放送後には、番組で紹介された現地取材映像や出演者の感想をもとに、より詳しい内容を追記します。
あなたのキッチンにある一振りの塩が、世界のどこかとつながっている――そう思うと、毎日の食事が少し特別に感じられるはずです。
出典:NHK総合『有吉のお金発見 突撃!カネオくん ステキな豆知識も満載!「塩」のヒミツ』(2025年10月12日放送)
https://www.nhk.jp/p/ts/K9R7PY9V6R/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

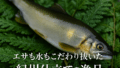
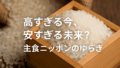
コメント