清流の女王・あゆ 和歌山が誇る“天然を超えた養殖技術”の物語
「天然のあゆこそ至高」と思い込んでいませんか?
いま和歌山県で育てられている養殖あゆが、全国の食通たちの間で注目を集めています。
『うまいッ!』(2025年10月12日放送・NHK総合)では、“天然に負けない極上の養殖あゆ”をテーマに、白浜町の清流・富田川で行われている驚きの養殖法や、あゆにまつわる伝統料理が紹介されました。
この記事では、番組で明かされた養殖技術の秘密、あゆ文化の深い歴史、そして家庭でも楽しめる郷土料理“あゆずし”の魅力をたっぷり掘り下げます。
清流・富田川の恵みから生まれる“極上のあゆ”

和歌山県白浜町を流れる富田川は、紀伊半島の南西部を代表する清流。古くから天然のあゆが遡上することで知られ、地元の人々にとっても生活と文化を支える存在です。
この富田川の地下から汲み上げられる伏流水が、養殖あゆの命の源。地下をゆっくりと流れる水は、ミネラルが豊富で一年を通しておよそ17℃。外気の影響を受けにくく、あゆの健康な成長を支えます。
生産者の岩出さんは語ります。
「富田川の伏流水は、まるで生きた清流そのもの。魚の呼吸を妨げず、酸素も自然に含んでいる」
その水にさらに酸素を送り込むため、池の中には大きな水車が設置されています。
この水車は、ただ水をかき混ぜるだけでなく、川の流れを人工的に再現する仕組み。常に流れのある水中で泳ぐことが、あゆの身を引き締め、筋肉質な体を作り上げるのです。
さらに岩出さんは、左右の流れを変えるというユニークな試みも実践しています。
時計回りと反時計回りの両方の水流を経験させることで、あゆの筋肉の付き方をバランスよく育て、よりしなやかで美しい体つきに仕上げるのです。まるでスポーツ選手のように、環境そのものが“トレーニングジム”のようになっています。
梅の力を借りた“あゆ専用ごはん”とは?
養殖の質を決めるのは、水だけではありません。もうひとつの鍵となるのがエサです。
岩出さんの養殖場では、国産のイワシやサンマを粉末にした魚粉をベースに、特別な配合飼料を使用。タンパク質が多く、あゆの筋肉をしっかり育てることができます。
そして、和歌山ならではの工夫がもうひとつ。
それが、地元特産の梅酢エキスを混ぜること。
梅酢に含まれるクエン酸が消化を助け、魚の内臓を健やかに保つ効果があります。結果として、身の締まりが良くなり、臭みのない上質なあゆに育つのです。
この“梅のチカラ”による養殖法は、和歌山ならではの知恵と自然の融合といえるでしょう。
ストレスを与えない“すべり台式”の管理方法
あゆは縄張り意識が強く、池の中で喧嘩をしてしまうこともしばしば。
そんな性格をよく理解している岩出さんは、魚たちが自然に棲み分けできるよう、すべり台のような仕切り装置を設置しています。
水の流れに乗って泳ぐあゆが、自分に合った通路を通り抜けることで、大きさごとに池を分けることができる仕組みです。
これにより、強いストレスを与えることなく、健康的に群れを維持できるのだとか。まさに“あゆの気持ちを理解した飼育法”といえます。
最後の仕上げには、“氷締め”という技も使われます。
氷水を飲ませて内臓まで一気に冷やすことで、鮮度を保ちながら旨味を閉じ込める。これにより、刺身で食べられるほどの新鮮さを実現しているのです。
和歌山とあゆ――400年続く深い縁
和歌山とあゆのつながりは、江戸時代の紀州徳川家の時代にまで遡ります。
当時、あゆは高貴な食材として扱われ、御猟場での漁を許された“あゆ師”と呼ばれる人々が特別な技を継承してきました。
その伝統を今も受け継ぐのが、紀の川で活動する小西孝明さんです。
小西さんは、代々伝わる“茜屋流小鷹網”という漁法を継承しています。
川の中で身をひそめ、魚の動きや川の流れを読みながら、一瞬のチャンスで網を投げる。まさに“静寂の中の狩人”。その姿からは、魚と自然に向き合う職人の誇りが伝わってきます。
“塩焼き”と“あゆずし”に込められた郷土の知恵
番組後半では、和歌山のかつらぎ町で受け継がれるあゆ料理が紹介されました。
まずは“あゆの塩焼き”。
小西さんの焼き方は、ただ焼くだけではありません。串を打つとき、生きているような自然な姿勢を保つのが流儀。
そのままホイロという蒸し焼き器で2時間かけてじっくりと火を通します。外はパリッと香ばしく、中はふっくら。時間をかけて焼くことで、骨まで柔らかく、香り高い逸品に仕上がります。
次に登場したのが、和歌山の伝統料理“あゆずし”。
蒸し焼きにしたあゆを甘露煮にし、酢飯にのせて柿の葉で包みます。柿の葉には抗菌作用があり、昔から保存食としても重宝されてきました。香りも良く、まさに郷土の知恵が詰まった味です。
家でも作れる!“あゆずし”レシピ
<材料(10人分)>
・素焼きあゆ:10匹(内臓を取り除く)
・酒:大さじ6
・砂糖:大さじ3
・しょうゆ:大さじ3
・みりん:大さじ3
・酢飯:3合
・柿の葉:適量
<作り方>
1)素焼きあゆを鍋に入れ、酒を加えてアルコールを飛ばす。
2)砂糖・しょうゆ・みりんを加え、30〜40分ほど煮込んで甘露煮にする。
3)冷ました後、頭と中骨を外して一口大に切る。
4)一口大に握った酢飯に甘露煮をのせ、柿の葉で包む。
押し寿司の型で数時間押せば、味がよりなじみます。
柿の葉の香りとあゆの甘露煮の旨味が重なり、噛むほどに“山と川の恵み”を感じる味わいに。
養殖が拓く、あゆの新しい未来
スタジオでは、天野ひろゆきさんがあゆの刺身を試食し、「薄切りなのに満足感がある」とコメント。
天然に近い環境で育った養殖あゆだからこそ、生食で味わうことができるのです。
10月下旬からは子持ちあゆの季節にも入り、養殖でも卵を持った個体が登場します。季節の移り変わりとともに楽しめる新しい食文化が、いま和歌山から全国へと広がっています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・富田川の伏流水と水車の力で“天然の川”を再現した養殖法
・梅酢入りエサとストレスを減らす飼育法が生食できる品質を実現
・紀州徳川家以来の伝統が郷土料理として今も息づいている
和歌山の養殖あゆは、自然と人の技術が調和した“次世代の清流の味”。
天然に寄せるだけでなく、自然を理解し、共に育てる文化の象徴でもあります。
一口食べれば、清流の香りと職人の情熱が伝わるはず。白浜やかつらぎを訪れた際には、ぜひ現地でその味を確かめてみてください。
出典:NHK総合『うまいッ! 天然ものに負けない!極上 養殖あゆ〜和歌山県〜』(2025年10月12日放送)
https://www.nhk.jp/p/umai/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

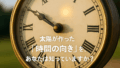
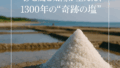
コメント