時計の針が右回りなのは“エジプト生まれ”だった!
毎日何気なく見ている時計。その針が“右回り”なのはなぜか、考えたことはありますか?
左ではなく右に動くのが当たり前すぎて、理由を意識することはほとんどないかもしれません。
そんな素朴な疑問を取り上げたのが、2025年10月10日放送の『チコちゃんに叱られる!』。
最後のテーマとして登場した「時計の針が右回りなのはなぜ?」の答えは、驚きの「エジプト生まれだから」。
歴史と自然の関係が深く結びついた、ロマンあふれる真相が明らかになりました。
時計のルーツは太陽を追った“影の記録”から
現代の時計のルーツは、今からおよそ7000年前、紀元前5000年ごろの古代エジプトにあります。
この時代、人々は太陽の位置と影の長さを利用して時刻を知る日時計を使っていました。
一本の棒(グノーモン)を立て、その影の動きを観察することで、一日の時間の流れを読み取っていたのです。
エジプトは北半球に位置しており、太陽は東から昇って南の空を通り、西に沈みます。
そのため、地面に立てた棒の影は、太陽の動きに合わせて自然と右回り(つまり時計回り)に移動します。
この“太陽の影の軌跡”こそが、現代の時計の針の回転方向の原点だったのです。
番組で登場した時計メーカーの学芸員、小池京子さんによると、
「エジプトの日時計が人類最初の“時間の可視化”であり、
その右回りの動きが、後の水時計や機械式時計にまで影響を与えた」とのこと。
つまり、私たちの“右回りの時間”という概念は、太陽と影が描いた自然の動きを受け継いでいるのです。
“もし南半球で時計が生まれていたら”のパラレルワールド
番組の中で小池さんが語ったのが、「もし時計の文化が南半球で生まれていたら、針は逆に左回りになっていた可能性がある」という興味深い仮説。
南半球では、太陽は北の空を通るため、影の動きは左回り(反時計回り)になります。
つまり、もしオーストラリアや南アフリカで日時計が発明され、それが世界標準になっていたなら、
私たちは今、左回りの時計を“当たり前”だと思っていたかもしれません。
この話にスタジオの岡村隆史も「たしかに、逆回りだと違和感あるけど…その世界ではそれが普通なんやな」と驚きの表情。
澤部佑も「南半球の人が初めて北半球に来て時計見たら、混乱しそうですね」と笑いながらコメントしていました。
チコちゃんも、「時間の感覚まで地球の場所で変わるなんて、ロマンチックよねぇ」と一言。
人間が“右回り”を当たり前と感じるのは、単なる文化ではなく、地球の自転と太陽の位置関係に根ざした自然現象の結果なのです。
太陽を神としたエジプト人の“時間観”
古代エジプトでは、太陽は単なる天体ではなく、“命をもたらす神”として崇拝されていました。
その象徴が太陽神ラー。彼は東の地平線から昇り、西の地へ沈むと信じられ、その動きが生命と死のサイクルを表していたといわれます。
つまり、太陽の右回りの動きは、エジプト人にとって「生の流れ」そのもの。
影の方向を追うことは、太陽の通り道=“命の時間”を見つめる行為でした。
それがやがて時間の単位となり、人類最初の“時間を刻む文化”が誕生。
エジプト人が太陽のリズムを尊び、その流れに沿って暮らしたことが、
現代の「時計の針の右回り」という概念の根底を形づくったのです。
機械式時計の登場と“右回りの継承”
やがてヨーロッパでは、13世紀ごろに機械式時計が誕生します。
このとき、すでに“時間=右回り”という概念が文化として定着していたため、
職人たちは無意識に右方向へ動く仕組みを採用したといわれています。
やがて時計の文字盤が「12」を上に配置し、「3」「6」「9」と並ぶデザインが標準化。
針が右へ進む動きは、世界共通の“時間の流れの象徴”になりました。
もし逆だったら、今の「進む」「未来へ向かう」という感覚も、もしかしたら“左方向”を指していたかもしれません。
現代の右回りが持つ“心理的効果”
心理学的にも、人間は「右方向に進む動き」に安心感や前進のイメージを持ちやすいといわれています。
漫画のコマ割りや映画の演出でも、右に進むキャラクターは“希望や成長”を、左に進むキャラクターは“回想や停滞”を象徴することが多いのです。
つまり、右回りの時計の針は、単なる物理現象を超えて、
「時間は前へ進む」「明日へ向かう」という人間の無意識にも影響を与えているのかもしれません。
古代エジプトの影が、現代の心理表現にまで続いていると考えると、まさに“太陽の遺伝子”ですね。
太陽が教えてくれる“時間の原点”
『チコちゃんに叱られる!』のこの回では、岡村隆史も「まさか時計の針が太陽の影に由来してたとは!」と驚きを隠せず。
澤部佑も「今まで一度も考えたことがなかったけど、知ると世界の見え方が変わる」とコメント。
チコちゃんの一言、「エジプト人に感謝しなきゃね」でスタジオは笑いに包まれました。
私たちが今、腕時計やスマホで時間を確認するその瞬間にも、
7000年前の砂漠の太陽が静かに影を落としています。
右回りの針は、太陽と人が共に歩んできた“時間の証”。
何気ない一瞬の中に、地球と歴史が息づいていると思うと、時計を見る目が少し変わりますね。
この記事のポイント
・時計の針が右回りなのは、古代エジプトの日時計がルーツ
・北半球では太陽の影が右回りに動くことから、この方向が定着
・もし南半球で時計文化が生まれていたら“左回り”が常識になっていた
・太陽信仰と時間観が“右回り”の文化を生み、現代まで継承されている
・右回りには“前進・未来”という心理的象徴もある
太陽の動きを写した影が、いつしか人の手で「時間」になり、
その“右回り”が、今も世界中で時を刻み続けている。
時計を見るたびに、古代エジプトの空を思い出してみると、
「今」という瞬間が少しロマンチックに感じられるかもしれません。
ソース:
NHK総合『チコちゃんに叱られる!』2025年10月10日放送回
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

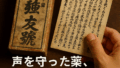
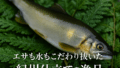
コメント