赤い座席の理由は「目立つため」ではなく“座る人をステキに見せるため”
3つ目のテーマは「なんで劇場や映画館の座席は赤いの?」。
最初に答えた岡村隆史さんは「暗くなっても席の場所が分かるように」と説明しましたが、ここでもチコちゃんに叱られてしまいます。
正解は『座る人をステキに見せるため』。
言われてみればあまり考えたことのない視点ですが、座席の色には“観客をより美しく見せる”という明確な目的があるのです。
この謎を解説したのは、劇場文化に詳しい石田麻子さん。ここから話は歴史と美の世界へ深く入り込んでいきます。
西洋オペラハウスに宿る「赤い座席」文化の原点
赤い座席の原点をたどると、西洋のオペラ文化にたどりつきます。
オペラの起源とされているのはイタリア・フィレンツェ。そこからヨーロッパ各地にオペラハウスが広まり、それぞれの地域で豪華な劇場文化が育まれました。
この時代、赤い染料は非常に希少で、高価な材料として扱われていました。赤は“権威・格調・富の象徴”。
パリのオペラ座を設計した建築家シャルル・ガルニエは、この象徴的な赤を座席に大胆に採用します。
理由は、観客をより美しく見せるため。特に女性客を“華やかで上品に見せる”ための工夫が詰まっていました。
赤は肌の血色をよく見せ、顔色を明るく見せる効果があります。オペラが社交の場として機能していた当時、この効果は非常に重要でした。劇場が単に演目を楽しむ場所だけでなく、美しさを引き立てる舞台でもあったのです。
「赤は舞台に集中しやすくなる色」もうひとつの科学的な理由
赤が選ばれたのは美しさだけではありません。暗い空間では、赤は黒に近い色に見えるという視覚的な特徴があります。
つまり、劇場が暗転した時、座席の赤は背景に溶け込み、観客の視線が自然に舞台へ向かいやすくなるのです。
・観客を美しく見せる「美の効果」
・舞台へ集中させる「機能的効果」
この2つを同時に満たす色が“赤”だったというわけです。劇場の空間設計として、非常に合理的かつ美的な選択だったことがわかります。
番組で登場した劇場&映画館をすべて紹介
今回の放送では、世界・日本の劇場文化も豊富に紹介されました。番組に登場した施設を一覧で並べておきます。
・kino cinéma
・帝国劇場
・アーキペラゴシネマ
・サン・カルロ歌劇場(イタリア)
・オペラ座(パリ)
・スカラ座
・テアトロ・ジーリオ・ショウワ
・熊本県立劇場
・エデン座
どの劇場も長い歴史を背負いながら、赤い座席の伝統を守り続けています。
特にスカラ座やサン・カルロ歌劇場のようなヨーロッパの老舗劇場では、赤い座席が“劇場文化そのもの”を象徴する存在になっています。
現代の映画館では「赤の伝統」に最新技術が組み合わさる
番組では、東京・新宿の最新映画館も紹介されていました。そこでは、全席が“革張り+電動リクライニング”。
赤ではなく上質な色合いの革を使用しながらも、観客を美しく見せるという伝統の思想を引き継ぎつつ、現代に合わせた快適性を追求した作りになっていました。
座席の色や素材は変化しても「観客を引き立てる」という劇場文化の本質は変わっていないことが強く感じられる場面でした。
赤い座席は“美・文化・機能”の集大成だった
今回のチコちゃんの解説は、普段何気なく目にする“赤い座席”が歴史と美学に支えられた選択だということを教えてくれました。
劇場や映画館の座席は、観客を美しく見せ、そして舞台に集中しやすくするという2つの役割をたった一つの色で同時に叶えていたのです。
次に劇場へ行くとき、ぜひ一度座席の色にじっくり目を向けてみてください。
何気ない赤い布の向こう側に、ヨーロッパの長い劇場文化とデザインの知恵が息づいていることに気付けるはずです。


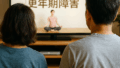
コメント