日本人が“とろとろ食感”を好きになる理由
今回の『チコちゃんに叱られる!』では、「なんで日本人はとろとろが好きなの?」という、一見シンプルだけれど日本の食文化の本質に触れるテーマが取り上げられました。
普段、なんとなく「とろとろって美味しいよね」と感じているその理由には、日本人の味覚の特徴や、離乳期から続く食文化の積み重ねがありました。
この記事では、とろとろ食感がなぜ日本人の心をつかむのか、その秘密をくわしく解説します。
味覚・文化・進化の視点から“とろとろの魅力”が立体的に理解できる内容になっています。
NHK【きょうの料理】土井善晴のふつうにおいしいもん|山芋たっぷり秋のお好み焼きレシピとあぶらげ納豆|2025年10月1日
日本人が“とろとろ”に惹かれる理由は『口の中の滞在時間が長いから』
まず最初に、チコちゃんが投げかけた質問に対して大久保佳代子さんが「高齢化で食べやすいから」と答えましたが、叱られてしまいました。
正解は『口の中の滞在時間が長いから』。
この意外な答えを解説したのは鈴木隆一さん。
日本人の食文化や味覚の仕組みを踏まえると、“とろとろ”は単なる食感ではなく、味をより深く感じるための大切な要素であることがわかります。
鈴木さんの説明によると、日本人は離乳食のころから“とろとろ”が当たり前の環境で育ちます。
しかも、世界的にみると5歳以降はとろとろ食材を食べる機会が減る国が多い中、日本ではその食習慣が大人になっても継続しやすいという特徴があります。
ここには、生食文化が深く根づいている影響も大きいとされていました。
とろとろであるほど、食材が舌に触れている時間が長くなり、味がより舌の上に広がり、うまみを感じやすくなります。
日本人はもともと『うまみ』に敏感だとされており、その特徴が“とろとろ好み”に直結しているのです。
日本人は「うまみ」を強く感じる民族。その差はデータでも明確
番組内では、日本人と外国人による“うまみ当て調査”が紹介されました。
結果は驚くほど大きな差でした。
・日本人の正解率…71%
・外国人の正解率…34%
この数値は、日本人が“うまみ成分”を見抜く能力がとても高いことを示しています。
うまみ文化が長く続いてきた背景には、昆布・かつお節・味噌といった、うまみの宝庫のような食材が日常にあふれてきた歴史があります。
そして、ここで重要になるのが“とろみ”。
とろみがあると味が舌に長く残るため、うまみをよりしっかり感じられるのです。
とろとろ味噌汁 VS さらさら味噌汁 うまみ数値の違いが明確
番組で紹介されたのは、「とろとろ味噌汁」と「さらさら味噌汁」を比べた実験結果でした。
なんと、とろみのある味噌汁の方がうまみの数値が高いという結果が出たのです。
この検証では、あばれる君が実際に2種類の味噌汁を飲み比べしました。
そのうえで、とろとろ味噌汁を「よりうまい」と選んでいます。
味の感じ方ととろみの関係は、視覚的にもわかりやすく示されていました。
この“味がよくわかる”という特徴は、うまみだけではなく苦味にも応用されます。
苦い『センブリ茶』でさえ、とろみがあると苦さが増す
番組内では、苦味で知られる『センブリ茶』を使った実験も行われました。
これも非常に興味深い内容でした。
さらさらのセンブリ茶と、とろみを加えたセンブリ茶を飲み比べると、とろみのある方が苦味を強く感じるという結果が出たのです。
つまり、“とろみ=味がよくわかる”という性質は、うまみだけでなく苦味にも共通しているということ。
味覚の強さや深さを左右するのは、舌に触れている時間が大きなカギになるという証拠でした。
ロケで登場した店も“とろとろ文化”を象徴している
ロケでは以下のような実在の店やサービスも登場していました。
・Sweet Check
・マルエツ 国領店
・頑固蛸 目黒本店
・麻布笄軒 中目黒店
どれも“とろとろ系”の食材や料理との差を見せるシーンに使われており、日常的にとろとろ食材が選ばれている日本ならではの演出とも言えました。
とろとろが“愛され続ける文化”になるまでの背景
とろとろ食感がここまで日本に根づいたのには、大きく3つの理由があります。
・離乳食から大人まで続く“食の連続性”
・生食文化に支えられた“舌の発達”
・うまみ文化に育てられた“味覚の鋭さ”
この3つが重なり、美味しさをより深く味わえる“とろとろ”という食感が、日本人の大きな魅力ポイントになっていきました。
まとめ
この記事で紹介した内容を整理します。
・日本人がとろとろを好きな理由は『口の中の滞在時間が長く、味がよく分かるため』
・とろとろ味噌汁はうまみが増し、センブリ茶は苦味が強くなるなど、味覚全体に影響する
・日本人の離乳食〜生食文化の積み重ねが、とろとろを自然と好む基盤になっている
・ロケで訪れた実在の店も“とろとろ文化”が日常にあることを示していた
普段の味噌汁やとろみ料理が、今日から少し違う味に感じられるかもしれません。
味の深さを支える“とろとろ”という食感は、日本人の味覚と文化の象徴ともいえる存在でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

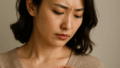

コメント