「“手綱”をつないで 〜愛媛・菊間〜」
愛媛の小さな町・菊間で、何百年も受け継がれてきた『お供馬の走り込み』。
子どもと馬が一緒に坂を駆け上がり、五穀豊穣を願う勇壮な祭りです。
この記事では、岡本誠篤さんと乗子 大黒風空くんが歩んだ2025年秋の物語をたどりながら、伝統に触れたときに生まれる「成長」「絆」「覚悟」を深く感じ取れる内容に仕上げています。
読んだあとに、菊間という土地の温度や祭りを支える人々の息遣いがそっと残るような、そんな物語をお届けします。
NHK【Dearにっぽん】馬と紡ぐ 僕らの夢〜北海道・厚真町〜 ばんえい競馬の引退馬が林業で再び輝く!馬搬士・西埜将世と女性職人・渡部真子の挑戦|2025年11月16日
菊間に根づく『お供馬の走り込み』という誇り
愛媛県松山市と今治市の間に位置する菊間町。ここで毎年行われる『お供馬の走り込み』は、菊間の象徴ともいえる伝統行事です。
参道を馬と乗子が一気に駆け上がり、その姿に地域の人々は今年の五穀豊穣を願います。乗子を務めるのは15歳までの子どもたち。まだ体も小さく、馬の力を受け止めるには覚悟が必要で、行事の危険性からも指導は厳しさを伴います。
そんな祭りを5代にわたり支えてきた馬主が、岡本誠篤さんです。誠篤さん自身もかつて乗子として坂を駆け上がった経験を持ち、馬と向き合う姿勢・地域への思い・誇りを、そのまま次の世代に渡そうとしてきました。
“馬主としての責任”と“子どもを守り育てたい気持ち”の両方を背負いながら、祭りの季節を迎えていきます。
10人の乗子と、2年目の挑戦をする風空くん
今年の乗子は10人。その中で誠篤さんが受け持つのが、2年目の挑戦となる大黒風空くんです。
風空くんは菊間とは別の地区に暮らしており、外部から参加する珍しい存在。去年の初参加で馬が大好きになり、今年も続けることを決めました。
しかし、2年目だからこその戸惑いも募ります。去年とは違う緊張、馬との距離感、責任の重さ。練習の中でその不安が少しずつ顔に出るようになります。
本番と同じ坂での練習 立ちはだかる“頂上手前”の壁
祭りまで1週間に迫った日、本番の坂を実際に駆け上がる練習が行われました。
風空くんは勢いよく走り出しますが、頂上の手前で突然止まってしまいます。
馬の力に負けてしまったのか、心の中に迷いがあったのか――そこに理由を求めるのは簡単ではありません。
走り込みは危険が伴うため、教える側は無理に追い詰めることはできず、しかし緊張を解きほぐす時間も必要です。
この日の風空くんは、ただ黙って馬の横に立っていました。
馬小屋での時間 馬が暴れた瞬間に見えた“覚悟”
練習後、誠篤さんは「馬と向き合う時間を作ろう」と風空くんを馬小屋へ連れて行きました。
そこで馬が突然興奮して暴れます。
風空くんが戸惑う中、誠篤さんは一歩も引かず、落ち着いた声と動きで馬をなだめました。
馬が落ち着くまで誠篤さんは姿勢を崩さず、手綱をしっかり握り続けました。
その姿を側で見つめていた風空くんは、「怖い」という気持ちを越えて、馬と向き合う覚悟を少しずつ形にしていきます。
この時間は風空くんにとって、言葉以上の学びになりました。
祭り2日前 風空くんが自分の力で馬を落ち着かせた日
祭りの2日前、風空くんの表情は明らかに変わっていました。
興奮気味の馬に対し、ゆっくりと声をかけ、落ち着かせることができたのです。
馬主や周囲の大人が見守る中で、風空くん自身が馬とつながる“芯”をつかんだ瞬間でした。
この時点で、2年目の不安は決して消えたわけではありません。
それでも、練習のたびに揺れていた気持ちが少しずつ整いはじめ、本番へ向けて着実に歩みを進めます。
本番前夜 誠篤さんの家で過ごした静かな時間
遠くから通う風空くんを心配して、誠篤さんは「家に泊まっていきなさい」と声をかけました。
本番を前に緊張が高まる時期。
食卓を囲み、同じ屋根の下で休むことで、風空くんの心に少しだけ余裕が生まれていきます。
祭りは“技術”だけでなく、“心の準備”も大切なのだと伝わってくる場面でした。
祭り当日 40年前の乗子衣装を受け継いで
10月19日、ついに祭り当日。朝6時からの準備で空気は張り詰めています。
この日、誠篤さんが40年前に身につけた乗子の衣装を風空くんに着せました。
代々受け継がれてきた衣装を託すのは、ただの衣装合わせではありません。
「思いを受け継いでほしい」という願いそのものです。
県内外から集まった約8000人の観客の前で走り込みが始まります。
風空くんの順番が訪れたとき、表情はもう迷っていませんでした。
坂を駆け上がり、回数を重ねるごとに安定していく姿。
去年よりも確かに強くなった背中。
誠篤さんが見つめる中、風空くんは目標を超える走りを見せました。
先輩乗子たちのクライマックスと、祭りの終わり
風空くんを含む乗子の走りが終わると、先輩乗子が迫力ある締めの走りを披露します。
人も馬も一体となり、会場がどよめく瞬間。
今年のお供馬は、人も馬もケガなく無事に幕を閉じました。
緊張と達成感が入り混じる祭りらしい終わり方です。
祭りの5日後 風空くんが選んだ“お礼”の訪問
祭りから5日後。風空くんは人参を手に、誠篤さんの馬小屋を訪れました。
馬の前に立つ表情には、かつての不安はなく、どこか誇らしげな落ち着きがありました。
馬にそっと人参を差し出す姿は、祭りが終わっても続く絆そのもの。
受け継いだのは技だけではなく、人としての大切な感覚でもありました。
まとめ
『お供馬の走り込み』には、地域の祈り、馬主の覚悟、子どもの成長が重なっています。
岡本誠篤さんと大黒風空くんの歩みは、伝統が若い世代へどのように受け継がれていくのかを鮮やかに示していました。
人と馬が心を通わせる時間は、菊間という地域の未来へつながる大切な“手綱”でもあります。
これからも、この土地の文化が多くの人の心を動かし続けますように。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


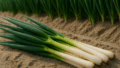
コメント