“ひとりぼっちじゃないよ”〜高知 中国残留邦人とともに〜
2025年8月31日に放送されたNHK総合「Dearにっぽん」では、高知県のデイサービスせいきょう やまももを舞台に、戦争を背景に中国で暮らしたのち日本に帰国した中国残留邦人とその家族の姿が紹介されました。33人の利用者のうち8人が中国残留邦人やその家族で、異国の地での苦しい体験を経てきた方々です。番組は、彼らの過去や今を伝えるだけでなく、施設スタッフや地域の人々が「家族のように寄り添う」姿を丁寧に描いていました。戦後80年を迎えた日本で、いまなお続く“戦争の影響”と、それを乗り越えようとする人々の絆が大きなテーマでした。
松岡春江さんの人生と苦難
番組冒頭で紹介されたのは、松岡春江さん。幼い頃に家族で旧満州に渡り、わずか4歳で異国の地に暮らし始めました。しかし、終戦後に旧ソ連軍が侵攻。父は炭鉱に連れて行かれ帰らず、母は体調を崩して命を落としてしまいました。松岡さんは孤児となり、中国の家庭に引き取られて成長。長い間「日本に帰りたい」という思いを抱きつつ、中国で生活を続けました。そして1976年、36歳の時にようやく帰国。日本に戻った後も生活には困難がありましたが、現在は高知で暮らし、せいきょう やまももに週5日通っていました。しかし自宅で転倒し骨折、しばらく施設に通えなくなってしまうという試練も。その後、1か月ぶりに笑顔で施設に戻った姿は、仲間との再会を喜ぶ様子として描かれました。
介護福祉士・田副大輔さんの思い
もう一人、番組の核となったのが若き介護福祉士の田副大輔さんです。高校卒業後、介護の専門学校に進みましたが、うつ状態に苦しみ1年間入退院を繰り返しました。その苦しい時期に支えてくれたのが祖母の照子さん。彼女が寄り添ってくれたことで、田副さんは再び立ち上がることができたのです。そして彼が出会ったのが高齢の中国残留邦人たちでした。彼らの孤独や不安に触れる中で、自分自身の経験が役立つのではないかと気づき、現在の活動の原点になったと語ります。介護は単なる仕事ではなく、人と人との心をつなぐ営みだという信念が感じられました。
武智明子さんの波乱の人生
番組では武智明子さんの歩みも紹介されました。戦後、中国の収容施設に置き去りにされ、中国人の家庭に育てられた彼女は、現地の劇団で主演を務めるほどの俳優として活躍。しかし心の奥には「両親がどこかで生きているかもしれない」という希望を持ち続けていました。41歳で帰国し、必死に親を探しましたが再会は叶わず、日本での暮らしを続けることに。その後、せいきょう やまももでは彼女が安心して過ごせるよう、スタッフ全員が中国語を学び、発音やアクセントまで工夫して接しました。さらに、彼女の大好きな歌を披露する演奏会も開かれ、武智さんは「ここは家族のような場所」と感じていました。ところがある日、体調を崩して心不全で急逝。仲間やスタッフは深い悲しみに包まれましたが、田副さんらは武智さんの自宅を訪れて弔い、その存在を決して忘れないと誓いました。
吉岡富康さんの誕生日
施設の明るいエピソードとして描かれたのが、吉岡富康さんの誕生日でした。中国では料理人として腕を振るっていた吉岡さんが久しぶりに料理を披露。仲間やスタッフ、日本育ちの利用者たちも一緒に祝い、にぎやかな時間を過ごしました。文化や背景の違いを超えて「同じ仲間」として祝福し合う様子は、施設が目指す「家族になれる場所」を象徴していました。
言葉と文化の壁を越える工夫
せいきょう やまももが特別なのは、利用者に寄り添う工夫を惜しまない点です。中国残留邦人を受け入れるにあたり、スタッフ全員が中国語を学習。細かな発音やイントネーションを意識し、相手が安心して言葉を交わせるよう努力しています。言葉だけでなく、歌や料理といった文化も共有し、利用者の思い出を大切にする姿勢が強く伝わりました。「ここにいれば、ひとりじゃない」と思える場所づくりが徹底されているのです。
ひとりぼっちじゃない居場所
番組のラストでは、骨折から復帰した松岡春江さんが再び施設に戻り、仲間たちと笑顔で再会する姿が印象的に映されました。また新しい仲間も加わり、施設はさらににぎやかに。歴史的な背景から日本に戻った中国残留邦人たちが、地域で支えられながら穏やかに暮らす姿は、多くの視聴者に希望を与えました。
まとめ
今回の「Dearにっぽん」は、戦争の歴史に翻弄された中国残留邦人と、彼らを支える高知の人々の物語でした。戦争が残した深い傷は消えることはありませんが、人と人が寄り添うことで孤独を和らげることはできます。せいきょう やまももは介護施設でありながら、文化や言葉の壁を越えた「家族のような場所」として機能していました。松岡さんの再出発、田副さんの成長、吉岡さんの誕生日、武智さんの突然の別れ…。それぞれの人生が交わり合い、「ひとりぼっちじゃない」というメッセージが強く響いた回でした。これからの地域社会がどうあるべきかを考える上で、多くの学びと感動を与えてくれる内容だったといえます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

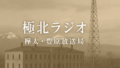
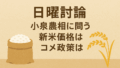
コメント