秋の海に響く太鼓の音 若き一番太鼓の決断
徳島県美波町日和佐地区。太平洋の海風が吹くこの町で、200年以上の歴史を持つ「日和佐秋祭り」が毎年10月に行われます。主催は日和佐八幡神社で、町の豊漁・豊作・海上安全を祈る祭りとして江戸時代から続いてきました。
町内の8地区がそれぞれちょうさ(太鼓屋台)を持ち、豪華な刺繍幕と太鼓の音を響かせながら町を練り歩きます。最大の見どころは、勇壮な「海入り」。波打ち際を越え、太鼓屋台が海へ突っ込む瞬間です。この独特の儀式は、全国的にも珍しい海とともに生きる地域文化として知られています。
そんな伝統の中心に立つのが、祭り全体を統括するリーダー「一番太鼓」。その年の祭りを象徴する存在です。2025年の番組『Dearにっぽん “一番太鼓”の決断 〜徳島 伝統の秋祭りで〜』(NHK総合)では、今年その大役を任された岸本和馬さんの姿が紹介されました。
NHK【祭り ヤバいぜ!】日和佐ちょうさに熱狂!女性拍子木&外国人担ぎ手がつなぐ230年の伝統|2025年11月2日
一番太鼓・岸本和馬さんの奮闘
7月26日、秋祭りを前に全体会議が開かれました。今年、一番太鼓に選ばれたのは、地元の消防署に勤務する30代の岸本和馬さん。子どものころから祭りに参加してきた生粋の日和佐の青年です。
彼はリーダーとして、通行止めの申請や運営計画など、事務的な準備もすべて担いました。しかし会議では意見が出ず、静かな空気が流れます。祭りの運営を担う若手が減り、担ぎ手の確保も難しくなっていました。
番組では、岸本さんが「どう続けていくか」に悩む姿が映し出されました。休日も返上し、仕事の合間に準備を進めながら、地域の伝統を守る責任の重さと向き合う日々。彼の父親もかつて一番太鼓を務め、祭りの改革を進めた人物でした。その父の姿が、岸本さんの背中を静かに押していました。
仲間との絆、支え合う地域の力
8月には他地区のリーダーたちと懇親の場が開かれ、岸本さんは祭りを取り巻く厳しい現実を語りました。担ぎ手不足、時間的な負担、若い世代の不参加――どの地域にも共通する課題です。
一方で、父親はかつて自ら地域の企業を訪ね、担ぎ手の「助っ人」を募った経験がありました。番組でもその姿が紹介され、地域全体で支え合う伝統の形が浮かび上がります。
そして、祭りの直前。岸本さんは他地区のリーダーたちを再び集め、準備を手分けして進めました。地域の垣根を越えた協力が少しずつ広がっていく様子に、地域の温かさが感じられました。
荒れる海、決断の瞬間
10月11日、いよいよ日和佐秋祭りが開催されました。各地区のちょうさが町中を練り歩き、太鼓の音と掛け声が響き渡ります。翌日、祭りのクライマックスである「海入り」を迎えました。
しかし、この日は太平洋が荒れていました。波が高く、風も強い。岸本さんはリーダーたちと何度も話し合い、結果として「海には入らない」という決断を下します。
この判断は簡単ではありません。200年の伝統に背を向けるように感じる人もいたでしょう。けれども、岸本さんは命を守ることを第一に考え、責任ある立場として冷静に判断しました。
祭りは無事に終了。最後には岸本さんが胴上げされ、地域の人々から大きな拍手が送られました。海には入らなかったものの、彼の決断が守ったのは「祭りそのものの命」だったのです。
次の世代へ託された太鼓の音
祭りの翌日、後片付けが行われました。岸本さんは総代会に出席し、次の一番太鼓を担う世代に向けてこう語ります。
「この祭りを続けるためには、町全体で支える仕組みが必要です」
この言葉には、地域を超えて多くの人が共感したことでしょう。日和佐の祭りは、もはや一つの町の行事ではなく、「地方がどう生きるか」を問う象徴でもあります。
近年、日和佐ちょうさ保存会を中心に外部からの担ぎ手募集やSNSでの発信、女性や子どもたちの参加促進といった新たな動きも始まっています。伝統は守るだけでなく、変わることで次世代へつながっていく――それを体現したのが、岸本和馬さんの一年でした。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
・一番太鼓の岸本和馬さんは、荒天の中「海に入らない」という判断を下し、伝統と安全を両立させた。
・日和佐秋祭りは200年以上続く祭礼で、海とともに生きる日和佐の人々の精神を象徴している。
・地域の若者や保存会が中心となり、担ぎ手不足を乗り越えるための新しい仕組みづくりが進んでいる。
日和佐の太鼓の音は、単なる祭りの響きではありません。人と人を結び、時代を超えて伝統をつなぐ心の鼓動なのです。
参考・出典リンク
・NHK公式サイト『Dearにっぽん “一番太鼓”の決断 〜徳島 伝統の秋祭りで〜』
・徳島県観光情報サイト 阿波ナビ「日和佐八幡神社秋祭り(ちょうさ祭り)」
・美波町公式サイト「日和佐八幡神社秋祭り開催情報」
・祭エンジン「徳島・日和佐のちょうさ祭りストーリー」
・徳島新聞デジタル「担ぎ手不足を補う新たな動き 日和佐ちょうさ保存会の挑戦」
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

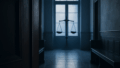
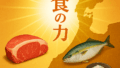
コメント