考えるときについ腕を組んでしまうのはなぜ?
気がつくと腕を組んでいる…そんな自分にハッとしたことはありませんか?会議中やテスト勉強の最中、無意識に腕を組んでしまう人は意外と多いものです。「クセかな?」と思って流してしまいがちですが、実はそこには人間の体と心の深い関係が隠れていました。今回は東京未来大学の大坊名誉教授が解説した「腕組みの3つの効果」と、番組で行われた興味深い実験をわかりやすくご紹介します。
腕組みには“バリア”の役割がある
腕組みには周囲との間に心理的な壁を作る効果があります。人は両腕を胸の前で交差させることで、自然と体を閉じる姿勢をとります。この動作は相手から見ると「近づきにくい」「話しかけにくい」という印象を与え、外部から入ってくる刺激や情報を減らす働きを持っています。つまり、考えごとに集中したいときや、一人の世界に入りたいときに無意識に腕を組むのは、このバリア効果が働いているからだといえます。
実際、心理学の分野でも腕組みは自己防衛の一種と解釈されることがあります。例えば緊張する場面や人前で考えを整理したいとき、腕を組むことで心を落ち着け、余計な干渉を防ぐことができるのです。この仕草は国や文化を問わず多くの人が自然に行うもので、まさに人間にとって本能的な「集中モード」のサインといえるでしょう。
補足として、同じように心理的なバリアを示す姿勢には、足を組む、机に肘をついて顔を覆うなどもあります。いずれも共通しているのは、外界から自分を守り、思考に集中するための無意識のサインであるという点です。
自分を落ち着かせる“安心感”の効果
腕組みにはもう一つ大切な意味があります。それは心の不安を和らげる作用です。人は腕を胸の前で交差させると、自分の体を抱きしめるような形になります。このとき肌と肌が触れ合うことで、脳内ではオキシトシンと呼ばれるホルモンが分泌されます。オキシトシンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、安心感や信頼感を高める働きを持っており、自然と気持ちが落ち着くのです。
そのため、試験や面接といった緊張する場面、あるいは大切な判断を迫られる状況で無意識に腕を組むのは、心を守り、平常心を取り戻そうとする人間の本能的な行動だと考えられます。小さな子どもが不安なときに自分の体を抱きしめたり、大人が寒いときだけでなく不安なときにも腕を組むのは、いずれもこの安心感を求める心理が表れているといえるでしょう。
補足すると、オキシトシンは本来、母と子のスキンシップや親しい人との触れ合いによって多く分泌される物質です。腕組みはその代替的な役割を果たしており、人間が一人でも安心感を得られる工夫された仕草の一つなのです。
安定した姿勢で思考に集中できる
さらに腕組みには、体の重心を安定させる効果があります。両腕をしっかりと胸の前で固定することで上半身の動きが制御され、姿勢全体がぶれにくくなるのです。これにより、気持ちが落ち着き、安定した状態で物事を考えられるようになります。
特に立っているときには、この効果がより顕著に表れます。腕を組むことで体のバランスが保たれ、フラつきが少なくなり、余計な力みを減らすことができます。こうした安定感があることで、思考に集中しやすくなり、冷静な判断を下す助けにもつながります。
補足すると、重心の安定はスポーツや武道などでも重要視されており、動きの軸をしっかりと作ることがパフォーマンス向上につながります。腕組みは日常的な仕草の中で自然とその安定を得られる動作であり、無意識のうちに人が「考える姿勢」として選んでしまう理由の一つでもあるのです。
実験で分かった“考えるポーズ”の違い
番組では東京未来大学の学生が参加し、「考えるときのポーズ」に関する比較実験が行われました。用意されたポーズは3種類で、ひとつは腕を胸の前で組む姿勢、もうひとつは机に肘をついて下を向く姿勢、そして最後が顔を手で触る姿勢です。学生たちはそれぞれの姿勢をとりながら、同じ謎解き問題に挑戦しました。
結果を平均タイムで比較したところ、最も早く正解にたどり着いたのは「顔を触る」姿勢でした。顔に手を添えることで余計な情報を遮断しつつ、リラックスした状態で思考が進みやすくなったと考えられます。しかし、ここで重要なのは「この姿勢が絶対に一番良い」ということではありません。実験を監修した大坊名誉教授は、「考えるときに最適なポーズは人それぞれ異なる」と解説しました。
つまり、腕を組むことで集中できる人もいれば、肘をつく姿勢や顔を触る動作の方が合う人もいます。大切なのは自分に合ったスタイルを見つけること。普段の学習や仕事の中で、自分が一番集中できる姿勢を意識して試してみることが、効率的な思考につながるのです。
補足すると、こうした「考える姿勢」に関する研究は心理学や教育学の分野でも注目されており、身体のちょっとした動作が思考プロセスに大きく影響することが明らかになりつつあります。
まとめ:腕組みは“心と体を守るサイン”だった
この記事で紹介したポイントを振り返ります。
-
腕組みには周囲を遠ざける心理的バリアの効果がある
-
肌の触れ合いによってオキシトシンが分泌され、不安を和らげる
-
重心を安定させることで思考に集中できる
-
実験では「顔を触る」姿勢が最も効率的という結果も出た
日常の何気ない仕草にも、人間の体と心が深く関わっています。次に無意識で腕を組んでいたら、「今、自分は安心したいのかな」「集中したいのかな」と振り返ってみると、意外な気づきにつながるかもしれません。
出典:
NHK総合「チコちゃんに叱られる!」2025年10月3日放送
NHK公式サイト
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

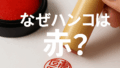
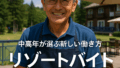
コメント