がんになったらお金は…生存率“向上”の一方で
がんの治療は進化し、生存率も向上していますが、それに伴い治療費の負担が大きな社会問題になっています。2025年5月19日放送のNHK「クローズアップ現代」では、「がんとお金」をテーマに、実際の患者の声や制度の課題、地域での取り組みなどが丁寧に紹介されました。高額な薬や長期化する治療によって生活が圧迫される現実。そしてそれを支える制度の見直しが進むなか、番組では現場で起きている“リアルな声”が取り上げられました。
がん治療にかかる高額な医療費と制度の限界

いまや2人に1人ががんになるとされる時代。そのなかで、多くの患者が直面しているのが治療にかかる高額な費用です。特に近年は新しい治療薬の開発が進み、それに伴って薬の価格も上がっています。中には10年前に比べて50倍もの価格になっている薬もあると報告されています。こうした状況に対応するため、一定額以上の医療費を軽減する「高額療養費制度」がありますが、それでもすべての負担が解消されるわけではありません。
肺がんと診断された北川綾香さん(44歳)は、4年前、次男を出産した直後にがんが見つかりました。ステージ4の進行がんで、毎日1錠の抗がん剤を服用し続けることで病状の進行を抑えているそうです。この薬の費用は月に17万円にもなります。制度を利用することで自己負担は4万4400円に抑えられていますが、現在は夫の収入のみで暮らしており、家計は非常に厳しい状況です。
・夫はフルタイムで働いているが、北川さん自身は次男出産の際にパートを辞めたため収入がなくなっている
・育児や家事をこなしながらの治療で、働ける時間も限られている
・教育費や食費が増加し、家計は毎月およそ10万円の赤字となっている
・貯金を切り崩して生活費を補う日々が続いている
北川さんは通院の回数を減らせば医療費が少しでも抑えられるのではないかと考え、病院の医療ソーシャルワーカーに相談しています。しかし、治療の性質上、簡単には回数を減らすことはできない可能性もあり、現実的な解決策が見つかっていない状況です。家計を圧迫し続ける治療費の中で、自分の病気が家族の生活を脅かしているという心理的な重圧にも苦しんでいます。
このように、高額療養費制度があってもなお、実際の生活への影響は大きく、制度の限界が浮き彫りになっているのが現状です。治療を続けながら生活を支えるための支援のあり方が、今後ますます重要になっていくと考えられます。
長期治療に伴う“経済毒性”と新たなサポートの形
がんの生存率が向上する中で、新たに浮かび上がってきた課題が「経済毒性」です。これは、治療が長期間に及ぶことで家計に深刻な影響を与える状態を指し、精神的なストレスや生活の質の低下、さらに治療そのものの継続にまで影響を及ぼすものです。希望を持って治療を続ける患者にとって、この経済的な負担は新たな壁となっています。
卵巣がんを再発し、現在も治療を続ける40代の佐々木美帆さんは、この経済毒性の影響を大きく受けている患者のひとりです。彼女は3週に1度のペースで分子標的薬の点滴治療を受けていますが、医師からは「治療に終わりはない」と伝えられているといいます。再発予防のための「維持療法」により、治療がいつ終わるかの目処が立たないまま、生活を続けていかなければなりません。
・現在の生活費は、傷病手当金20万円が主な収入源
・月に7万円かかる医療費は、通院が対象外のため民間のがん保険が使えない
・病気の影響で働けない状況が続き、収入の回復の見込みが立たない
・副作用による外見の変化を受け入れるためにウィッグやスキンケア用品など、医療費以外の出費も増加
このような現状に対し、千葉大学医学部附属病院では、生活と治療の両立を支える取り組みとして、ファイナンシャル・プランナーを招いた相談会を開いています。ここでは、患者一人ひとりの状況に合わせた家計の見直しや支出の抑え方、利用できる制度の情報提供など、具体的なアドバイスが行われています。
経済毒性のリスクを軽減するには、病気の治療と同じように計画的で現実的なサポートが必要です。佐々木さんのような患者が安心して治療を続けられるよう、病院や社会が一体となって支援する取り組みが、今後さらに求められるといえます。
医療制度をどう維持していくかという課題
医療の進歩は患者にとって大きな希望である一方で、それを支える公的医療保険制度の維持が難しくなりつつあるのが現実です。高度な医療技術や新薬の導入により治療の質は向上していますが、その分、医療費は年々増加し、保険制度の財政を圧迫しています。
大手企業の健康保険組合では、従業員とその家族あわせて約1万人が加入していますが、今年度の赤字は1億円以上にのぼる見込みです。この大きな赤字の要因として挙げられているのが、高齢者医療への拠出金の増加です。今年は団塊の世代が全員75歳以上となる年であり、現役世代の保険料負担がますます重くなることが懸念されています。
保険組合では、こうした状況を改善するために、加入者の健康状態を予防の段階で管理する取り組みを進めています。たとえば、糖尿病のリスクがあると診断された場合には、24時間血糖値をモニタリングし、食事や生活習慣の改善を促すという方法が取られています。
・生活習慣病の予防によって、将来の医療費増加を抑制
・従業員の健康意識を高め、長期的に医療費削減を目指す
・医療に頼りすぎる前に、病気を予防するという発想への転換
このようなアプローチは、今後の医療制度の持続可能性を考えるうえで重要な取り組みといえます。医療の高度化を支えながらも、支える側が破綻しないための工夫が求められているのです。保険制度の改革だけでなく、日常生活における健康管理の意識を社会全体で高めることも、安定した医療提供体制の維持につながっていきます。
地域での工夫もカギに
医療費の増加に対応するための工夫は、国の制度だけでなく、地域レベルでも積極的に行われています。その代表的な例が山形県酒田市の取り組みです。この地域では、医療費の中でも大きな割合を占める薬剤費の削減に焦点を当て、「地域フォーミュラリ」という仕組みを導入しています。
これは、地域の医師たちが協力して作成した疾患ごとの推奨薬リストを活用し、患者にとって効果が同等でありながら価格が安い薬を優先的に処方するというものです。リストには、主にジェネリック医薬品が多く含まれており、薬を選ぶ際の明確な指針となっています。
・たとえば、これまで555円だった薬が、リストにあるジェネリック薬を選ぶことで312円に
・患者の健康に影響を与えない範囲での見直しを徹底
・医師と薬剤師が連携し、地域全体で薬剤費を抑える仕組みが整備されている
この取り組みにより、2020年と比べて薬剤費を2億円以上も削減することができました。これは単なるコスト削減ではなく、患者への負担軽減と制度の持続可能性の両立を目指すものであり、地域医療の新たなモデルとして注目されています。
この「地域フォーミュラリ」について、医療制度の専門家である高久玲音さんは全国に広げるべき取り組みだと高く評価しています。制度が整っていても、実際に現場でどう活用されるかが重要であり、こうした地域の知恵と連携が医療費抑制のカギを握っているといえるでしょう。
今後、他の地域でも同様の取り組みが広がっていけば、全国規模での薬剤費削減と患者負担の軽減が実現可能になると期待されています。
国の制度見直しと今後の方向性
医療費の増大が深刻化するなか、国全体の制度を見直す動きも本格的に進められています。特に注目されているのが、患者の経済的負担を軽減するための高額療養費制度についての検討です。この制度は、一定額以上の医療費について自己負担額に上限を設ける仕組みで、多くの患者の命綱ともなっています。しかし今後、その仕組み自体をどう持続させるかが問われているのです。
国はこの問題に対し、専門委員会を設けて制度の在り方を再検討しており、2025年秋までに新たな方針を示す予定となっています。これは、現行制度の限界や今後の持続性を見据えたうえでの重要な見直しといえます。
あわせて議論されているのが、患者の自己負担割合である「3割負担」の基準見直しです。医療を必要とする人が安心して治療を受けられる反面、現役世代を中心とする保険料の負担は増しており、制度全体のバランスを保つために負担の公平性や支え合いの仕組みが見直されようとしています。
さらに、市販薬と同じ効能を持つ「OTC類似薬」を保険適用外にするという方針も検討されています。これが実現すれば、年間でおよそ3300億円の医療費削減が見込まれるという試算が示されました。たとえば、風邪薬や胃薬など、ドラッグストアで買える薬とほぼ同じ効能を持つ処方薬については、保険から外すことで、財政の圧迫を防ぐという考え方です。
・高額療養費制度は今後の再設計が進行中
・3割負担の見直しにより、世代間の公平な負担を目指す
・OTC類似薬を保険外にすれば、年間数千億円単位の削減が可能
これらの議論は、単なる節約ではなく、限られた医療資源をどう使い、どう守っていくかという選択でもあります。制度改革によってすぐにすべてが解決するわけではありませんが、患者と現役世代、そして地域や医療現場が一体となって支え合う医療の形が求められているのです。今後の方針に注目が集まっています。
おわりに
がん治療の進歩は希望である一方で、その裏にある「お金」の問題は見過ごせません。制度の見直しが進む中でも、患者ひとりひとりの生活や声を置き去りにしない支援の在り方が求められています。これからの医療制度が、誰もが安心して治療に専念できる形に整えられていくことが期待されます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

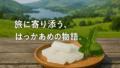
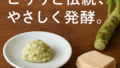
コメント