明治生まれ最後の5人が令和に残したメッセージ
「もし114歳の人生経験を持つ人から直接言葉を聞けるとしたら、あなたは何を学びたいですか?」。2025年9月16日放送のNHK総合『クローズアップ現代』では、明治生まれ最後の5人にスポットを当て、激動の5つの時代を生き抜いた人生から令和を生きる私たちに贈る言葉が紹介されました。この記事では、その放送内容を振り返りながら、長寿の秘けつや歴史の証言をわかりやすくまとめます。
沖縄の家族を支えた喜友名靜子さん
沖縄県北谷町で暮らしていた喜友名靜子さんは、取材当時「沖縄最後の明治人」と呼ばれていました。生まれは明治時代、近代の始まりとともに育った彼女は、激動の時代を生き抜いた証人でもあります。
沖縄戦が始まったのは、彼女が32歳の時でした。4人の子どもを必死に守り抜き、砲弾が飛び交う中でも母としての強さを失うことはありませんでした。避難生活の苦しさや食糧不足の中で、わずかな食べ物を工夫し、子どもたちを飢えさせないように知恵を絞り続けたといいます。その姿は、家族にとって大きな心の支えとなりました。
戦後はアメリカ統治下という不安定な社会の中で、生活の糧を得るために商店を営みました。物資の不足や円とドルの使い分けといった複雑な状況にも対応しながら、地域の人々にとっても欠かせない存在となりました。経済的に厳しい時代でも働き続け、子どもや孫たちに教育の機会を与えたことは、家族の未来を大きく変える原動力になりました。
そして113歳で亡くなるまでの長い人生は、まさに沖縄の近現代史そのものと重なります。戦争の悲劇を生き抜き、戦後の混乱を乗り越え、平和の時代を迎えるまでを歩んできたその強さは、家族にとってかけがえのない“宝”であり、今も深く語り継がれています。
国内最高齢114歳 賀川滋子さんの挑戦
現在国内最高齢114歳を誇る賀川滋子さん(奈良県大和郡山市)は、まさに日本の女性医師の先駆けといえる存在です。わずか22歳で医師となった彼女は、まだ女性が医師として働くことが珍しかった時代に、果敢に道を切り開いていきました。
1920年代の日本では、女性が医師を志すこと自体に強い逆風が吹いていました。女子の進学先として設立された医学専門学校でも、「女性医師はあくまで男性医師の妻として役立つ存在」という考えが根強く残されていました。それでも賀川さんは、そうした社会的な偏見や制約に屈することなく、ひたむきに勉強を重ね、患者と向き合い続けました。
長い年月を経て迎えた現在も、その姿勢は少しも衰えていません。最近、自宅で転倒し骨折するという出来事がありましたが、それを理由に諦めることはありませんでした。むしろ「自力で立ち上がる努力を続ける」と語り、日々リハビリを重ねています。114歳という年齢を超えてもなお前を向き続けるその生き方は、多くの人に勇気と希望を与えています。
教科書にない明治人の生活史
番組では、賀川滋子さんが学生時代に撮影された貴重な洋装姿の写真が紹介されました。昭和初期、まだ多くの女性が和服を日常着としていた時代に、洋服を身にまとうことは非常に珍しいことでした。その写真からは、経済的にある程度の余裕があったこと、そして新しい文化を積極的に取り入れようとする進取の気性が伝わってきます。賀川さんは、時代の最先端に身を置こうとする強い意志をすでに若い頃から持っていたのです。
さらに、20歳のころに出会った『カレーライス』は、彼女の食生活に大きな変化をもたらしました。当時、カレーといえばイギリスのC&Bカレー粉が主流で、高級品として扱われていました。しかしある業者が、その空き缶に国産のカレー粉を詰めて販売したところ、意外にも「国産でも十分においしい」と高く評価されました。これをきっかけにカレーは庶民の家庭にも広がり、今日の日本に欠かせない国民食となっていったのです。賀川さんはその変化のまさに目撃者であり、自身の体験を通じて「食」が社会や文化を大きく動かしていく力を実感していました。
飛行機が夢から絶望へ変わった時代
賀川滋子さんが8歳のころ、故郷の奈良の練兵場に陸軍の飛行機が飛来した記録が残されています。まだ飛行機が珍しかった時代、空を舞う姿は子どもたちや地域の人々にとって大きな驚きと憧れであり、「未来への夢」を感じさせるものでした。背景には第一次世界大戦による好景気があり、鉄鋼業や造船業の発展とともに航空隊も急速に整備されていきました。当時は市民が資金を出し合い、献納機と呼ばれる飛行機を軍に寄付するほどで、飛行機はまさに「希望の象徴」でした。
しかしそのイメージは1930年代に入ると大きく変わっていきます。飛行機はやがて戦意高揚のシンボルとなり、戦争遂行のための存在として利用されました。1941年には日本軍がハワイを攻撃し、太平洋戦争へと突入。賀川さんが暮らしていた大和郡山市の上空にも、戦闘機が飛来するようになりました。戦争末期にはアメリカ軍による機銃掃射が行われ、無防備な市民が命を落とす悲劇も起きました。特に地元の小学生2人が犠牲となった出来事は、飛行機が持っていた「夢」が一瞬にして「絶望」へと変わったことを象徴しています。
賀川さんにとって、飛行機は憧れから恐怖へと姿を変えた存在であり、その体験は長い人生の中でも強烈な記憶として刻まれ続けています。
令和に生きる私たちへのメッセージ
賀川滋子さんの歩んできた人生は、連続テレビ小説『花子とアン』の舞台となった時代背景とも重なっています。女性が学び、働くことに大きな制約があった時代に、医師として道を切り開き、多くの命の誕生に立ち会ってきました。その姿は、まさに近代から現代へと移り変わる日本社会の中で、女性の可能性を示す存在でもありました。
そして114歳となった今、賀川さんは「ここまで生きてるから、もうちょっと生きてから死にたい」と穏やかに語ります。その言葉は、一見すると控えめに聞こえますが、裏には歴史を見届け続けてきた明治人ならではの強い意志が感じられます。戦争も混乱も、平和の訪れもすべてを体験してきたからこそ語れる重みのある言葉であり、同時に未来を生きる私たちへの静かなエールでもあります。
賀川さんの人生は、単なる長寿の記録にとどまらず、「生きることそのものの意味」を問いかけてくれる貴重な証言となっています。
まとめ
今回の『クローズアップ現代』で描かれたのは、5つの時代を生き抜いた最後の明治人たちの歩みでした。
この記事のポイントは以下の3つです。
・喜友名靜子さんは沖縄戦を生き抜き、家族を守った存在
・賀川滋子さんは114歳の今も挑戦を続ける女性医師の先駆者
・明治から令和まで、生活や価値観の変化を身をもって体験した証言は教科書にない“生きた歴史”
令和を生きる私たちにとって、彼女たちの言葉は人生の指針となるものです。長寿や健康への関心だけでなく、「どう生きるか」を考えるきっかけを与えてくれました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

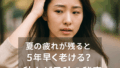
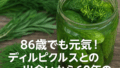
コメント