「“下水道クライシス” いま都市部で何が」
2025年9月1日に放送されたNHK総合「クローズアップ現代」は、都市生活を支える大切なインフラ「下水道」をテーマに取り上げました。普段は気にかけることのない存在ですが、道路の下に張り巡らされた管が老朽化し、陥没事故や大規模な障害を引き起こすリスクが高まっているのです。番組では実際の事故、専門家の解説、現場での調査や研究の最前線が紹介され、下水道の現状と課題が浮き彫りになりました。
八潮市で起きた道路陥没事故と衝撃の事実
特集の冒頭で取り上げられたのは、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故です。破損した下水道管は設置から42年で、耐用年数50年を迎える前に壊れてしまいました。この事故は「老朽化が進んでいないと思われる管でも危険が潜む」ことを示し、全国に衝撃を与えました。事故後、国土交通省は全国の自治体に対し、直径2m以上で設置から30年以上経過した下水道管を重点的に調査するよう要請。その結果、都市部では14.6%もの管が今後対策を必要としていることが判明しました。
さらに驚くべきは、事故の3年前の調査ではB判定を受け、緊急対策の対象とされなかったことです。専門家は「調査方法や評価基準だけでは劣化の実態を十分に見抜けない」と指摘。見過ごされたリスクが実際に事故につながった事実は、全国に大きな課題を突きつけました。
全国に広がる老朽化と調査の限界
都市部の下水道管は合計すると地球3周分に達するほどの長さがあります。例えば札幌市では約8300kmもの下水道管を抱え、毎年220kmを調査していますが、全てを調べるには38年かかる計算です。この遅れがさらなるリスクを招きます。しかも調査には危険が伴い、2025年8月には埼玉県行田市で点検作業中に作業員4人が硫化水素中毒で亡くなる事故も起きました。現場の過酷さが浮き彫りになっています。
また、番組で紹介された自治体アンケートでは7割以上が「民間業者の人手不足を感じている」と回答。調査・補修を担う人材の不足が大きなハードルになっています。八潮市の事故以降は調査依頼が殺到し、現場は対応しきれない状況に追い込まれているのです。
大阪で進む研究と効率化の試み
下水道の老朽化が深刻な大阪市では、全体の老朽化率が50%を超えるとされています。そこで注目されているのが、大阪大学と連携した劣化予測研究です。単に設置年数だけを見るのではなく、下水に含まれる微生物の分析などを通して、管の劣化速度を科学的に割り出そうとしています。この研究によって修繕の優先順位を正しく判断できれば、限られた予算や人員を効率的に活用することが可能になります。
さらに、下水道管の寿命を延ばすための新技術も研究されています。従来は古い管を掘り返して交換するしかありませんでしたが、内部に特殊な素材を貼り付けることで耐久性を高める工法や、流れる水質に応じて腐食を抑える処理方法が注目されています。
下水道と感染症対策の意外なつながり
番組では、下水道の研究が感染症対策にも役立つことが紹介されました。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の流行時には、下水に含まれるウイルスの痕跡を調べることで、地域での感染拡大を早期に察知できる仕組みが注目されました。アメリカや日本でも研究が進み、下水道が「地域の健康を守るセンサー」として機能する可能性が広がっています。インフラ整備と感染症対策が結びつく新しい視点です。
市民ができる小さな行動
下水道の維持には膨大な費用と労力が必要ですが、私たち市民の小さな習慣も大きな支えになります。番組では次のようなポイントが示されました。
-
油を流さない
-
ティッシュやゴミを排水溝に捨てない
-
タバコを流さない
-
工事に理解を示す
こうした行動が下水道の負担を減らし、管の寿命を延ばすことにつながります。普段の暮らしの中でできる協力が、インフラを守る第一歩なのです。
まとめ:下水道クライシスを“自分ごと”に
今回の「クローズアップ現代」で明らかになったのは、下水道クライシスは全国で同時進行している課題だということです。事故が示すように、耐用年数を迎える前でもリスクは存在し、調査や補修には膨大な時間と人手がかかります。一方で、科学的な研究による効率化や新技術の導入が進められていますが、自治体や専門業者だけでは限界があります。だからこそ、市民一人ひとりの意識と協力が欠かせません。
見えない地下の世界で起きていることを知り、日常の行動を見直すことが、都市の安全を守る力になります。下水道は生活に欠かせないライフラインであり、未来の世代に安心して使い続けてもらうためにも、今からできることを意識していく必要があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

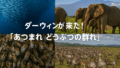

コメント