千葉県いすみ市で注目の“室内アワビ養殖”とは?
『いまオシ!LIVE』のコーナーで紹介されたのは、千葉県いすみ市で進む「室内アワビ養殖」という新しい挑戦です。アワビといえば、海の岩場に張りついて育つ高級食材。これを“陸の上”で育てるという発想は、まさに次世代の漁業を象徴する試みです。
海に出ず、室内の水槽でアワビを育てるこの方法は、近年の漁業の課題を背景に生まれました。地球温暖化による海水温の上昇、赤潮や台風の増加など、自然環境の変化によってアワビの稚貝が生き残りにくくなっているのです。その一方で、国内外でアワビの需要は高まり続けており、安定供給への期待が高まっています。
この流れを受けて立ち上がったのが、A’Culture株式会社。いすみ市大原地区に室内養殖場を構え、海に頼らないアワビの育成システムを開発しました。水槽は長さ約20メートル、深さ2センチほどの直線型構造。水流ポンプを使って波のような流れを再現し、アワビが自ら動ける環境を整えています。これにより、自然の海に近い動きを促しながら、ストレスの少ない成長を実現しています。
持続可能な“室内漁業”という選択肢
アワビの陸上養殖には、多くのメリットがあります。まず、気候変動の影響を受けにくいこと。屋内で育てるため、台風や高波、赤潮といった自然災害の被害を回避できます。また、水温・水質の管理が容易で、成長スピードや歩留まりをコントロールしやすくなります。
さらに、従来の海の漁業では難しかった“周年生産”が可能に。季節を問わず、安定した供給を実現できるのは、飲食業界にとっても大きなメリットです。アワビ料理を扱うレストランや旅館、寿司店などからの関心も高まりつつあり、「養殖=味が落ちる」という固定観念を覆すほどの品質が話題になっています。
こうした技術革新は、地域の新しい産業の柱としても注目されています。海に出る必要がないため、若者だけでなく、女性やシニア層の雇用にもつながりやすいのが特徴。地元住民が安心して働ける環境を整え、地域の経済と人材を循環させる仕組みが少しずつ形になってきています。
地域と企業が連携した“いすみ発”の挑戦
このプロジェクトには、地元の行政や教育機関も協力しています。千葉県いすみ市は、もともと漁業と農業のどちらも盛んな地域でしたが、少子高齢化によって後継者不足が深刻化していました。そこで、市が中心となって産官学連携の体制を整え、サステナブルな地域漁業モデルを目指しています。
A’Culture株式会社は、大学の研究室とも協力し、アワビの餌となる海藻や微生物の栄養管理を科学的に分析。AIを活用した水質モニタリングや、酸素供給システムの最適化なども進めています。これにより、人の勘や経験に頼らない“データ駆動型の漁業”が可能になりました。
また、地元のリゾート施設「リソルの森」との連携も話題です。観光客向けにアワビ養殖を見学できるツアーや、採れたてのアワビを味わう体験型プランの企画が進行中。海辺の町いすみを訪れる人々に、“新しい漁業のかたち”を体感してもらう試みです。今後はふるさと納税の返礼品として販売される計画もあり、地域ブランド化の動きも広がっています。
技術と地域の力で未来を変える
この「室内アワビ養殖」は、単なる水産技術の進歩ではなく、地域の再生プロジェクトとしての意味も持っています。環境問題や人手不足など、これまで漁業を苦しめてきた課題に対し、“自然を守りながら人の暮らしを支える”という新しい道を切り開いているのです。
そして何より、いすみ市の人たちが口をそろえて語るのは、「地元の海を未来へ残したい」という想い。海に出なくても、海とともに生きる。そうした新しい関係性を築く挑戦が、いすみから全国へと広がりつつあります。
今後は、この技術を応用して他の高級魚介類の養殖にも展開する予定です。サザエやウニなど、環境変化に弱い生物を陸上で育てる動きも始まっており、「いすみモデル」が日本の養殖業の未来を変える可能性を秘めています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・千葉県いすみ市で進む「室内アワビ養殖」は、気候変動に強く、安定供給を可能にする新しい漁業モデル。
・A’Culture株式会社が中心となり、AI技術や地域連携を取り入れたサステナブルな仕組みを構築。
・観光・教育・地域振興にも広がる“室内漁業”の可能性が、日本の水産業の未来を変える。
海に出なくても海を感じられる。千葉県いすみ市から始まったこの挑戦は、テクノロジーと地域の力が融合した“未来の漁業”として、全国の注目を集めています。
出典:
千葉日報オンライン「千葉県いすみ市・A’Culture株式会社 室内アワビ養殖の取り組み」
リソルの森 公式サイト
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

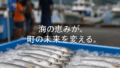
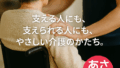
コメント