懐かしの駄菓子「ポン菓子」と99歳としこさんの物語
子どもの頃、ポン!と大きな音を立てて飛び出すポン菓子に驚いた経験はありませんか。甘い香りと軽やかな食感で親しまれてきたこの駄菓子は、ただのおやつではなく、日本の食文化や人々の思い出と深く結びついています。2025年9月15日放送の「グレーテルのかまど」では、そのポン菓子に人生をかけた女性、としこさんの物語が紹介されます。彼女は太平洋戦争の末期という困難な時代に、子どもたちを笑顔にするため国産ポン菓子機を作り出した先駆者。この記事では番組内容をより詳しく掘り下げ、知られざる背景や現代に残る意義をわかりやすくまとめます。この記事を読めば、ポン菓子が「懐かしい駄菓子」を超えた存在であることに気づくはずです。
食糧難の時代に生まれたポン菓子機
ポン菓子は、米や麦などの穀物を高温高圧で加熱し、一気に解放することで膨らませるお菓子です。昭和の子どもたちにとっては屋台での実演販売が楽しみのひとつでしたが、その起源には深い物語があります。太平洋戦争末期、食糧も資材も不足する日本で、「子どもたちにお腹いっぱい食べさせたい」と願ったとしこさんが立ち上がりました。
当時大阪に暮らしていた彼女は、鉄を扱う技術が集まる北九州に向かい、試行錯誤を繰り返しながら国産初のポン菓子製造機を開発しました。戦時中に女性が工業製品を作り出すこと自体が大きな挑戦であり、困難を乗り越えた背景には、飢えに苦しむ子どもたちへの強い思いがありました。この機械がきっかけとなり、ポン菓子は全国へ広まり、戦後の食文化を支える大きな存在になっていきます。
99歳でも現役!情熱を支える原動力
現在、としこさんは御年99歳。驚くことに、いまも自らポン菓子作りを続けています。日々の暮らしの中で鍛えられた手さばきや工夫は衰えることなく、「子どもたちに美味しいものを届けたい」という信念が彼女を動かしているのです。
長寿社会の今、年齢を重ねても挑戦し続ける姿は、多くの人に勇気を与えてくれます。ポン菓子は単なるお菓子ではなく、としこさんが体現してきた「誰かのために生きる」という生き方そのものを象徴しているのです。
番組の見どころ:瀬戸康史が挑む“家庭で作るポン菓子”
番組では、瀬戸康史さんが家庭のフライパンを使って“オリジナルポン菓子”作りに挑戦します。フライパンで作るとなると、火加減や加熱時間が難しく、簡単に焦げてしまうリスクもあります。しかしその分、工夫次第で多彩なアレンジが可能。例えば砂糖を絡めてキャラメル風にしたり、ナッツやドライフルーツを加えて栄養価を高めたりと、家庭ならではの新しい楽しみ方を紹介してくれます。
さらにナレーションはキムラ緑子さんが担当。温かくユーモラスな語りが、視聴者をポン菓子の懐かしさととしこさんの物語の世界へと引き込んでいきます。
ポン菓子が持つ文化的価値
ポン菓子は戦後の子どもたちの空腹を満たすだけでなく、地域のコミュニティ形成にも大きな役割を果たしてきました。屋台でポン!と大きな音が響くと、近所の子どもたちが集まり、笑顔と歓声が広がる。その光景は、世代を超えて共有された“思い出の原風景”です。
また、米を主食とする日本人にとって、お米を使ったポン菓子は「食文化の延長」であり、安価で栄養があり保存も効くことから、戦後の復興期に非常に重宝されました。こうした背景を知ることで、ポン菓子の持つ社会的・文化的な意味合いが一層鮮明になります。
まとめ:愛と勇気を届け続けるポン菓子
今回の「グレーテルのかまど」では、次の3つのポイントが明らかになります。
-
としこさんは戦時中に子どもたちのため国産初のポン菓子機を作った
-
99歳となった今も現役でポン菓子作りを続けている
-
番組では瀬戸康史さんが家庭で楽しめるポン菓子作りに挑戦
ポン菓子は「懐かしいお菓子」という枠を超えて、誰かを思う気持ちから生まれた“愛と勇気の物語”なのです。この記事を読んだあなたも、スーパーや駄菓子屋でポン菓子を見かけたら、背景にある情熱の歴史を思い浮かべてみてください。次のステップとして、家庭でポン菓子風のおやつに挑戦するのも良いでしょう。きっとその一口が、過去から未来へとつながる小さな架け橋になるはずです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

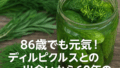
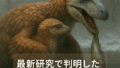
コメント