防災を「やらないと」から「やってみよう」へ変える新しい動き
大きな地震や豪雨などの災害が増えているのに、「防災の準備はしていますか?」と聞かれると自信を持って「はい」と答えられない人が多いのではないでしょうか。実際にマーケティングリサーチ会社が行った最新アンケートでは、「あまりできていない」「全くできていない」と答えた人が7割を超えるという結果が出ています。頭では大事だとわかっていても、行動につながっていないのが現実です。
この記事では、2025年9月1日放送のNHK「午後LIVE ニュースーン」で紹介された、全国で広がる新しい防災の取り組みを詳しく紹介します。ゲーム感覚で学べる体感型アトラクションや、高齢者の心を動かした大学生との手紙の交流など、日常の中で無理なく防災を取り入れる工夫をまとめます。読めば「やらないと…」という義務感が「やってみよう!」という前向きな気持ちに変わるはずです。
課題:わかっていても進まない防災準備
防災の課題は「知識」と「行動」のギャップです。非常用の水や食料をそろえても、そのまま置きっぱなしになり賞味期限が切れてしまうことは珍しくありません。避難所の生活を想像するのは難しく、必要なものが何かを具体的にイメージできない人も多いのです。さらに一人暮らしの高齢者は「備えても一人では使いこなせないのでは」と不安を抱え、準備が進まないままになってしまうこともあります。こうした背景から、体験や交流を通じて「自然に行動したくなる仕組み」が求められています。
謎解きで学ぶ!鳥取・米子市の体感型防災アトラクション
番組で大きく取り上げられたのが、鳥取県米子市で開催された「体感型防災アトラクション」です。これは、遊びながら防災を学ぶ新しいイベントで、事前予約した約150人が参加しました。会場に隠されたヒントを見つけながら、25分間で5つのミッションに挑戦します。
出題されたミッションは実生活に直結する内容ばかりです。
-
「避難所生活で備えておくと便利なアイテムは?」 → 正解はバッテリー。スマホの充電ができれば情報収集や安否確認に役立ちます。
-
「避難所で運動不足から命を守れ」 → チームでエコノミー症候群を防ぐ運動を考える。
-
「新聞紙でスリッパを作成せよ」 → 怪我防止に役立つ身近なアイテムを活用。
-
「災害用伝言ダイヤルで宝箱を開けよ」 → 実際に声を録音・確認することで使い方を体験。
単なる知識ではなく、体を動かしながら体験するので強く記憶に残ります。最後には座学も行い、ゲームで得た知識を改めて整理する時間が設けられていました。企画した松田哲さんは、阪神・淡路大震災の避難所生活を経験したことから「人は体験で学ぶことが大きい」と考え、この取り組みを始めたそうです。10年間で34都道府県、のべ9万人が参加しており、防災教育の新しい形として注目されています。
体験が記憶を救うカギになる
スタジオでは解説者の岸正浩さんが「経験があると、いざというとき自然に体が動く」とコメントしました。頭で理解するだけでは災害時に役立たず、実際に試した経験が命を守る行動につながるという指摘です。このように遊びや謎解きといった親しみやすい方法で防災を体験できる機会は、子どもから大人まで参加しやすく、地域での広がりも期待されています。
93歳の女性を動かした「手紙」の力
番組で紹介されたもう一つのエピソードは、香川県高松市に住む93歳のミユキさんです。南海トラフ巨大地震では2メートル以上の津波が想定される地域ですが、5年前に非常食などを備えたものの、それ以降は確認せず放置していました。「準備したから大丈夫」と思っていても、時間とともに賞味期限は切れていきます。
そんなミユキさんの心を動かしたのが、香川大学防災士クラブの学生たちとの手紙のやりとりでした。3年間で20通の手紙を交換し、季節の出来事や近況とともに最新の防災情報も自然に伝えられてきました。学生の勝浦弓葵さんは「一番意識してほしいのは防災」と語り、手紙の中で「水の保存場所を見直しましたか?」といった声かけをしてきました。その積み重ねでミユキさんは「また備えを見直さないと」と考えるようになったのです。
絵手紙プロジェクトと学生の役割
香川大学防災士クラブは「絵手紙プロジェクト」という活動も行っています。手紙にイラストを添えて親しみやすく伝えることで、防災を難しく感じさせず自然に受け入れてもらえるようにしています。さらに年に数回は対面交流会を開催し、最新の情報を直接共有する工夫もあります。**高橋真理さん(香川大学危機管理先端研究センター)**は「学生が日常会話の中に防災の要素をさりげなく入れることが大切」と指摘し、地域に寄り添った啓発活動の意義を強調していました。
日常に防災を組み込む具体的な工夫
番組から学べる「日常に防災を取り入れるヒント」を整理すると次のようになります。
-
ゲームや体験イベントに参加して、家族で楽しく学ぶ
-
非常食や水の備蓄は「点検日」をカレンダーに書き込み、忘れない仕組みを作る
-
一人暮らしの高齢者は、地域や大学生との交流を通じて防災を意識する
-
手紙や会話に自然に防災の話題を混ぜる
-
家族で実際に避難経路を歩き、避難所までの時間を確認する
こうした小さな行動が積み重なれば、災害時の大きな安心につながります。
よくある質問と答え
Q. 防災用品はどれくらい備えればいいの?
A. 最低3日分、できれば1週間分の水と食料を用意するのが基本です。
Q. 高齢の家族にはどうやって伝えたらいい?
A. 難しい説明より「最近の水は大丈夫?」など、普段の会話に混ぜるのが効果的です。
Q. 遊び感覚の学びで本当に役立つの?
A. 実際の動きを体で覚えることで、災害時にパニックにならずに行動できます。
まとめ:小さな一歩が未来を守る
今回の放送から見えてきたのは、防災を「やらないといけない義務」から「やってみよう」と思える体験に変えることの大切さです。鳥取の防災アトラクションのように楽しく学ぶ方法もあれば、香川大学の絵手紙プロジェクトのように心を通わせて意識を高める方法もあります。どちらも「行動につながる工夫」という点で共通しています。
まずは自宅の備蓄を見直したり、避難経路を確認したり、身近なことから始めてみませんか。防災は一人ではなく、地域や家族と一緒に進めるもの。この記事をきっかけに、「やってみよう」と思う一歩を踏み出す人が増えることを願います。
———
この記事が役に立ったと思ったら、ぜひシェアして身近な人と防災について話してみてください。あなたの行動が周りの人の意識を変えるかもしれません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

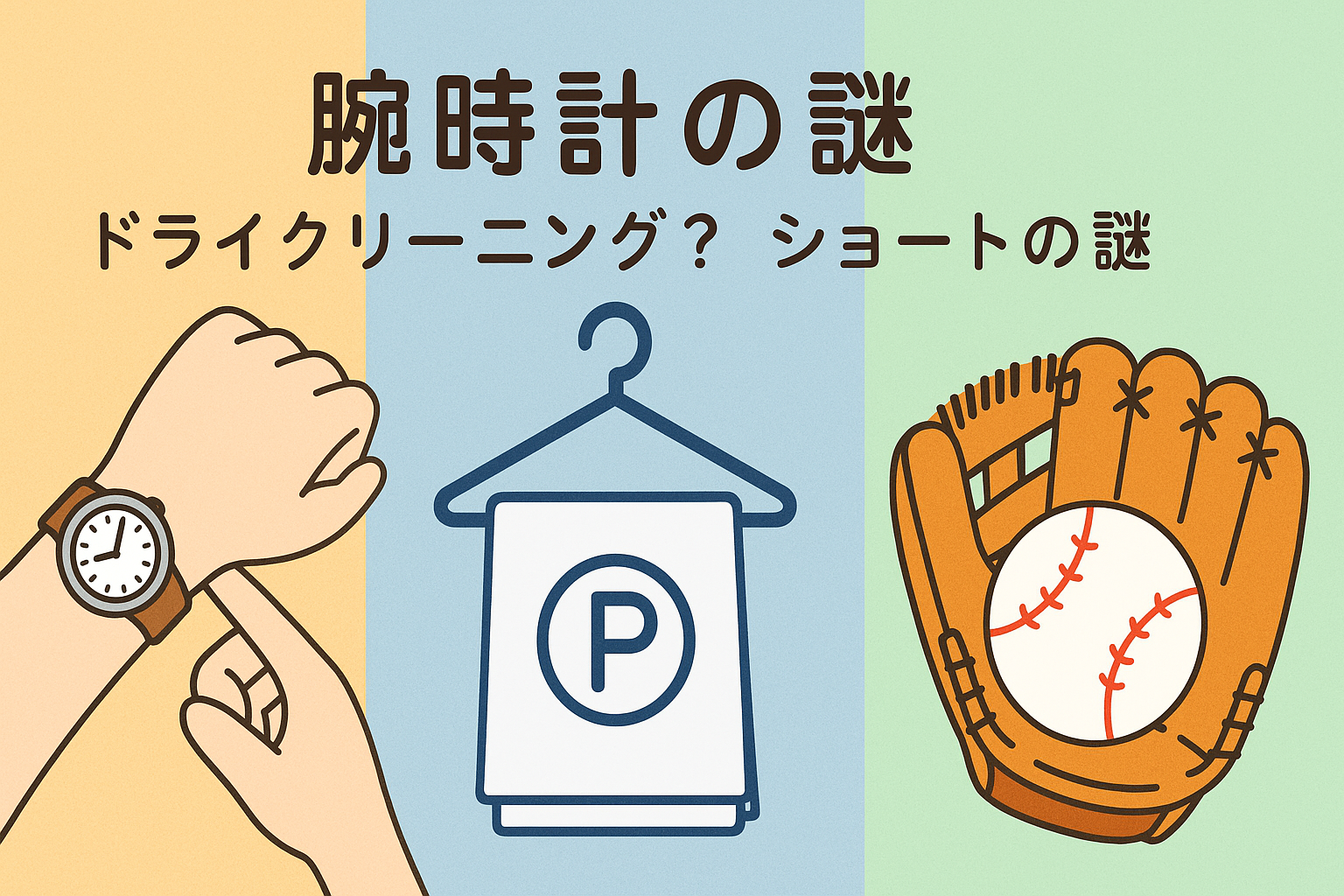

コメント