プロ野球の“ビールかけ”ってどうして始まったの?
「優勝=ビールかけ」。プロ野球ファンなら誰もが思い浮かべる光景ですが、なぜ日本のプロ野球ではお祝いのたびにビールをかけ合うのでしょうか?「最初からそういうものだ」と思っていませんか?実はこの習慣には意外な“仕掛け人”がいたのです。この記事では、南海ホークスから始まった『ビールかけ』誕生秘話と、その文化がどう根付いていったのかをわかりやすく解説していきます。読めば、次にテレビでビールかけを目にしたときの見方がきっと変わりますよ。
ビールかけは1959年の南海ホークスから始まった
プロ野球のビールかけが始まったのは、1959年の南海ホークスがリーグ優勝を果たした時でした。中心人物となったのは外野手のカールトン半田です。彼はアメリカでのプレー経験を持ち、メジャーリーグで優勝時に行われる『シャンパンファイト』の文化を知っていました。当時の日本プロ野球では、優勝後の祝いといえば宴会でお酒を飲む程度で、派手さはなく、チーム全員が一体となるような盛り上がりは欠けていました。
そこで半田は「せっかくの優勝なのだから、チーム全員で喜びを分かち合いたい」と考えます。そして優勝祝いの席で、エース投手の杉浦忠に突然ビールを浴びせかけました。この予想外の行動は周囲を驚かせると同時に、大きな笑いと歓声を呼び、選手たちは一気に熱狂の渦に包まれました。ビールをかけ合うという新しいスタイルの祝福は、たちまちチームの士気を高める象徴的な出来事となったのです。
この盛り上がりの様子は、ベースボール・マガジン社や時事通信社、毎日新聞社など多くのメディアが取り上げました。新聞や雑誌に大きく掲載された写真は、当時のファンや他球団の選手たちに強烈な印象を残しました。記事を読んだり写真を見た選手たちは「自分たちもやってみたい」と感じ、翌年には大洋ホエールズの優勝時にもビールかけが行われ、そこから一気に日本球界全体へと広がっていきました。
ちなみに1950年代後半から1960年代にかけては、プロ野球が急速に人気を拡大していた時期でもあり、テレビや新聞が大きな役割を果たしていました。特に後楽園球場などで行われる優勝セレモニーは注目度が高く、選手たちがビールでずぶ濡れになって喜ぶ姿はファンの記憶に強く刻まれました。このようにして、1959年の南海ホークスとカールトン半田の発想がきっかけとなり、今ではプロ野球の優勝シーンを象徴する伝統行事として定着しているのです。
翌年には大洋ホエールズも実施
カールトン半田の試みからわずか1年後の1960年、大洋ホエールズがセ・リーグを制し、その優勝セレモニーでさっそく『ビールかけ』を実践しました。当時、大洋ホエールズは球団創設以来初のリーグ優勝という快挙を達成しており、その喜びを全員で分かち合う手段としてビールかけは大いに盛り上がりました。南海ホークスの時と同様、選手たちが全身ずぶ濡れになってはしゃぐ様子は新鮮で、見ていた人々の印象にも強く残りました。
この新しい祝勝スタイルは、その後すぐに西鉄ライオンズなどパ・リーグの強豪チームにも広がっていきました。西鉄ライオンズは1950年代から60年代前半にかけて黄金期を迎えていた球団であり、連覇を重ねる中でビールかけを取り入れることで、勝利の象徴としてのイメージがさらに定着していったのです。やがてセ・パ両リーグの優勝シーンで定番となり、どのチームも当たり前のように行う文化へと変わっていきました。
さらに、こうしたビールかけの様子を、報知新聞や産業経済新聞社、テレビ放送などが繰り返し報じたことも大きな影響を与えました。選手たちが豪快にビールを浴びながら笑顔で喜ぶシーンは、紙面や映像を通じて全国に広まり、野球ファンの心に「優勝=ビールかけ」というイメージを強く刻み込みました。特にプロ野球の人気が急上昇していた高度経済成長期において、ビールかけは祝祭の象徴として定着し、スポーツ文化の一部となっていったのです。
文化として根付いた理由
ビールかけがこれほどまでに広まった背景には、いくつかの大きな理由があります。
まず一つ目は一体感の象徴です。選手も監督もスタッフも、立場の違いを超えて全員がビールでびしょ濡れになることで「同じ喜びを分かち合っている」という強い結束が生まれます。勝利の瞬間を全員で身体ごと共有できるこの儀式は、チームの団結を示す最も分かりやすい表現となりました。
次に挙げられるのは映像映えです。選手たちが笑顔でビールを浴びながらはしゃぐ姿は、新聞の写真やテレビ中継で大きなインパクトを残しました。特に1960年代はテレビの普及期であり、優勝シーンを家庭で見守るファンにとって、ビールかけは「勝利の象徴」として記憶に刻まれました。濡れたユニフォームや選手たちの無邪気な表情は、言葉以上に喜びを伝える効果があったのです。
さらに重要なのがスポンサーとの関係です。プロ野球の人気が高まる中で、ビールメーカーにとっても「優勝=ビール」という構図は絶好の宣伝効果を生みました。アサヒビールやキリンビールなど大手メーカーは、広告や販売促進の場面でこのシーンを積極的に活用し、ビールかけは商業的にも強い後押しを受けました。そのため、単なる選手の遊びではなく、球界全体にとってプラスとなる習慣として続けられるようになったのです。
これらの要素が組み合わさり、日本独自のスポーツ文化として『ビールかけ』は定着しました。今ではプロ野球だけでなく、社会人野球や他のスポーツ競技でも行われるほど広まり、優勝シーンを彩る欠かせない儀式として受け継がれています。
ビールかけの“裏話”とエピソード
実はビールかけが初めて行われた1959年は、後楽園球場での優勝セレモニーでも大きな話題になりました。当時の日本では、選手が祝いの場でお酒を飲むことはあっても、わざわざ頭からビールを浴びるという行為は非常に珍しく、観客や関係者からは「選手たちがビールで遊んでいる」と驚きの声が上がったといいます。その光景はユニフォームを濡らしながら笑顔で弾ける選手たちの姿と相まって、強烈なインパクトを残しました。
しかし、この一風変わったお祝い方法は、次第に「ただの余興」ではなく、優勝を象徴する特別な儀式として定着していきました。球団が変わっても世代が移り変わっても、ビールかけは必ず行われるようになり、やがて「なくてはならない伝統」とまで呼ばれる存在になったのです。
そして時代が進むにつれ、単に盛り上がるだけではなく、安全面への配慮も取り入れられるようになりました。ビールが目に入ると炎症やケガにつながる恐れがあるため、近年では選手たちがゴーグルを着用してビールかけを楽しむ姿が当たり前となりました。さらに、ビールの大量使用に代えてシャンパンや発泡性飲料を使うケースも見られるようになり、伝統を守りつつ現代的な工夫が加えられています。
このように、1959年に始まった南海ホークスの試みは、驚きと興奮を呼びながら日本のプロ野球文化に根付き、今では「優勝=ビールかけ」という誰もが知る風景となったのです。
まとめ:ビールかけの意味を知ると野球がもっと楽しくなる
この記事で紹介したポイントを整理します。
-
ビールかけの発祥は1959年の南海ホークス
-
カールトン半田が杉浦忠にビールをかけたのがきっかけ
-
大洋ホエールズをはじめとする他球団に広まり、現在の伝統になった
つまり、日本のプロ野球における『ビールかけ』は、一人の選手の発想と行動がきっかけで誕生し、今ではファンにとって欠かせないお祝いシーンへと進化したのです。次にテレビでビールかけを目にしたら、その背景にあるストーリーを思い出しながら楽しんでみてください。
出典:
NHK総合「チコちゃんに叱られる!」2025年10月3日放送
NHK公式サイト
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


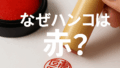
コメント